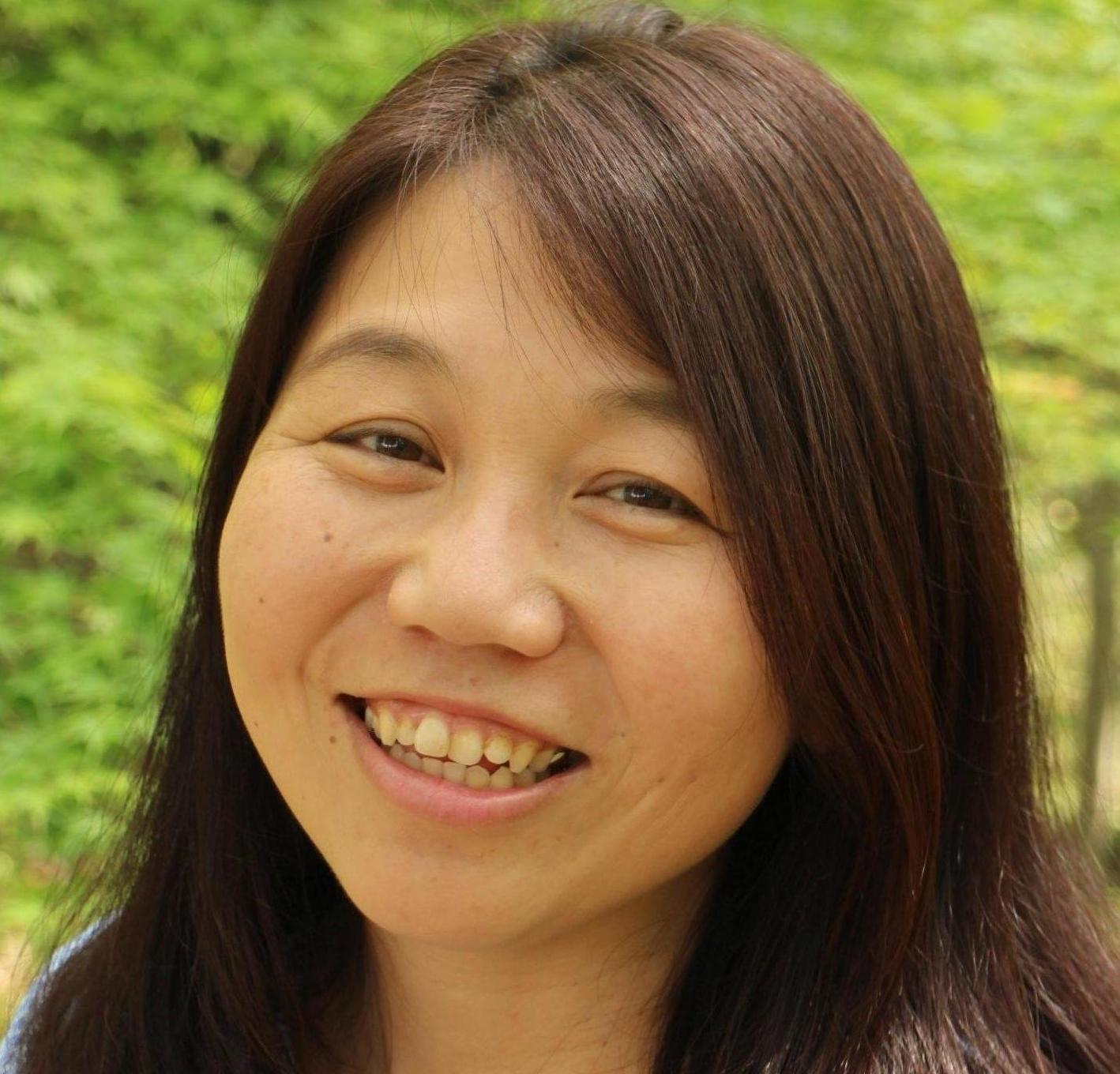ローカル局が「地域密着」「長期取材」による優れたドキュメンタリー番組を放送していることは知られていますが、その局以外の地域の視聴者が目にする機会が少ないという現状があり、ドキュメンタリー番組の存在や価値が社会に十分に伝わっていないという声も聞かれます。
そこで「民放online」では、ノンフィクションライターの城戸久枝さんにローカル局制作のドキュメンタリーを視聴いただき、「鑑賞記」として紹介しています(まとめページはこちら)。ドキュメンタリー番組を通して、多くの人たちに放送が果たしている大切な役割を知っていただくとともに、制作者へのエールとなれば幸いです。(編集広報部)
あの戦争から80年が過ぎた2025年には、戦争に関連する多くのドキュメンタリーが放送された。数多い作品のなかから、3作品を紹介したい。
『壕(ガマ)のおくり人 沖縄戦80年・遺骨収集夫婦の記録』
沖縄テレビ放送で2025年5月24日放送(フジテレビ系「FNSドキュメンタリー大賞」で2025年10月11日放送)
1945年、あの戦争で激戦が繰り広げられた沖縄には、今もなお、戦争で亡くなった多くの遺骨が残っている。この作品は25年にわたり、沖縄に通い続け、遺骨収集ボランティアを行ってきた浜田哲二さん、律子さん夫妻の記録だ。
多くの日本兵が身を潜めた暗い壕(ガマ)で、夫妻は汗や土にまみれながら、ただコツコツと遺骨を探す。画面に映し出されるのは、一見、石にしか見えない、無数の遺骨だ。この地に、どれだけ多くの人々が今も眠っているのだろう。ガマの中で響く遺骨収集の音は、彼らの声なき声に重なっていくようだ。夫妻が遺骨収集をはじめたきっかけは、新聞記者として世界の戦地を飛び回っていた夫、哲二さんが、沖縄取材時に、ガマから戦死者の遺骨を掘り出していた国吉勇さんとの出会いだった。「君ら新聞記者は、戦後50年、60年のときだけ来て騒いで帰る」「この下には遺骨が埋もれているんだよ」。哲二さんは新聞記者を辞め、同じく新聞記者だった妻、律子さんと遺骨収集ボランティアをはじめる。
二人の願いは、遺骨や遺品を親族に返すこと。だが、遺骨の返還には国のDNA鑑定が必要だという。これまでに返還された沖縄戦の遺骨はわずか6柱。気の遠くなるような作業が続くこの活動を、それでも二人は今も続けている。
2015年、ガマの中から日本軍の認識票が見つかった。それは旧日本軍歩兵第32連隊のものだった。そして、戦争中、千人近い部下のうち9割を失い、自らは生き延びた伊東孝一大隊長が、戦死した部下の家族に手紙を送り続けていたことがわかる。浜田夫妻は健在だった伊東さんを探し出した。伊東さんは600通の手紙を送り、遺族から356通の返信が届いた。遺族からの手紙には、夫や息子の最後の姿が知りたいという切実な思いが綴られていた。浜田夫妻は、伊東大隊長が亡くなる前に引き継ぎ、手紙を遺族に返すという取り組みを行っている。実は縁あって私は浜田夫妻の著書の書評を担当したことがある。遺族と手紙を結び、つなげていく素晴らしい作品だった。
二人の活動で何よりも意義深く感じるのは、若者たちに、実際に遺骨収集へ遺族への遺品の返還の場に参加させていることだ。本作品でも、何人かの若者が実際に遺骨収集を行う様子が映し出されている。さらに、沖縄に居を構え、若者たちの集う場を提供している。この遺骨収集ボランティアの活動には終わりはないだろう。国吉さんや伊東さんから思いを受け継ぎ、若い世代へとさらにつないでいこうとする浜田夫妻の姿を、これからも記録として残していってほしい。一人でも多くの戦没者の遺骨が、遺族のもとに帰ることを、心から願う。
『War Bride2 奈緒と4人の戦争花嫁』
TBSテレビ系「ドキュメンタリー『解放区』」で2025年10月5日放送
戦争花嫁とは、第二次世界大戦後、日本に駐留した米軍、連合国関係者と結婚した女性たちのことだ。今も米国で多くの戦争花嫁と呼ばれた女性たちが暮らしている。舞台『WAR BRIDE』で戦争花嫁を演じた俳優の奈緒さんが、米国で暮らす、恵子・ジョンソンさん、マリコ・スパックさん、ツチノ・フォレスターさん、桂子・ハーンさんという4人の女性に会いに行く。
戦後の貧しい日本から、米国人の妻となり渡米した彼女たちに共通するのは、「戦争花嫁」として、日米両国から、さまざまな差別を受けてきたことだ。
マリコ・スパックさんは夫の浮気相手から「あなたの主人は私を愛している。日本に帰ったらいいんじゃない?」という手紙を受け取った。傷ついたマリコさんに日本で暮らす母が「辛抱した木には花が咲くのよ」と励ました。マリコさんはその後、子どもたちを立派に育て上げた。結婚した夫が同性愛者だったと話す恵子・ジョンソンさん。自分と子どもたちを残して出ていってしまった彼女だが、夫について語るとき、「(同性愛者に対して)私たちの目で見て、違っていても、ジャッジしてはいけない」と、ご自身に言い聞かせるように語った。日米でさまざまな差別を受けてきて、その痛みを知る彼女の思いがまっすぐに伝わってきた。戦後5年で結婚し、海を渡った桂子・ハーンさんは、米国の市民権を得るための面接で、「もし戦争が起きたらあなたは日本と戦えますか?」と質問された。「私はアメリカ人にならなくてはいけない。日本と戦います」と答えたものの、涙が止まらなかったという。
奈緒さんがツチノさんに聞いた。「戦争花嫁という言葉の響きをどのようにとらえていますか?」。実は私もこの戦争花嫁という言葉にひっかかっていた。本来は戦争の関係で外国人と結婚した女性というシンプルな意味のはずだった。だが、日本では、どこか違う意味が含まれているように感じられた。ツチノさんは言う。「日本の場合は、無条件降伏、とてもみじめな立場で敗れたから、日本人の心もさびしく貧しくなっている」。軍関係の仕事として、高給で雇われる女性に対し、男の人は仕事がなかった。うらやましい思いから「感情的になって、見下げる言葉になってしまった」と。この戦争花嫁という言葉の背景には日米の戦争、戦後のさまざまな歴史と人々の思いが絡み合っているのかもしれない。
戦後、米国人の妻として渡米した彼女たちは、日本でも、米国でも、世間と戦った。そして今、米国でこうして家族に囲まれて元気に暮らしている。90歳を超えた彼女たちのたたずまいの美しさ、歌声の張りのすばらしさに心奪われた。
『特攻のための特攻~熊本から飛び立った義烈空挺隊~』
熊本県民テレビ(日本テレビ系「NNNドキュメント'25」で2025年11月9日放送)
1945年5月24日、熊本市の健軍飛行場から、義烈空挺隊168人を乗せた12機の爆撃機が飛び立った。目的地は米軍に占領されていた沖縄の飛行場。当時、すでにはじまっていた特攻作戦の障害を取り除くために、米軍の飛行場を破壊する、いわゆる「特攻のための特攻」が、彼らの任務だった。熊本県菊池市にある菊池飛行場ミュージアムでは、2017年から毎年、義烈空挺隊に関する企画展が開かれているが、熊本から出撃した唯一の特攻隊である義烈空挺隊のことは、ほとんど知られていない。番組では、菊池飛行場ミュージアム館長の永田昭さんを中心に、義烈空挺隊について深く掘り下げていく。永田さんは、来館した客、一人ひとりに丁寧に義烈空挺隊について語っていく。私自身、元特攻隊員の方々からお話を聞いたり、知覧特攻平和会館を取材で訪れたりしたことはあるが、義烈空挺隊については、詳しくは知らなかった。高校でも義烈空挺隊について講義する永田さんは、若者たちに問いかける。「特攻隊に行けと言われたら、行きますか?」と。
もともとは精鋭のパラシュート部隊だった彼らは、戦況の悪化に伴い、特攻を命じられることになる。体中に爆弾を付けて爆撃機で飛行場に突入するのは、もちろん命を落とすことが前提の作戦だ。義烈空挺隊に関する6分間の国策映画が残されている。映像には、笑顔で日の丸を振る隊員たちの姿が。彼らは本当に笑っていたのだろうか。死を前にした20代の若者たちが、つかの間の安らぎの時間を過ごすことができたのは、出撃前の2週間を過ごした熊本の、観音湯での女将、堤ハツさんとの時間だった。姉のように、母のように接してくれたハツさんに、出撃前、隊員たちがこう声をかける。「小母さん、いろいろお世話になりました 今から出発します この金は私共にはもう使い途がなくなりましたから」。そしてハツさんに金一封を渡した。その後、ハツさんのもとに届いた遺書には「私達も笑って嵐に向かい、笑って元気一杯に戦い、笑って国に殉じ、笑って皆様の御期待に報ゆる覚悟です」と記されていた。
たった1度の特攻のための特攻で隊員168人のうち113人が戦死した。
ハツさんは隊員たちからのお金をもとに、観音湯の敷地内に菩薩像を立てた。そして亡くなる直前まで毎日、隊員たちを思い、手を合わせ続けたのだという。観音湯は廃業し、菩薩像は健軍飛行場の近くの寺に移された。そこに、菊池さんが知覧の慰霊祭で出会った隊員の遺族たちも集う。出撃のとき、ふるさとに向かって「お母さん」と叫んだ義烈空挺隊の隊員たち。戦後80年が過ぎた今、彼らの思いに触れ、あらためて深く心に刻む。もう二度と、このような戦争は起こしてはならないのだと。