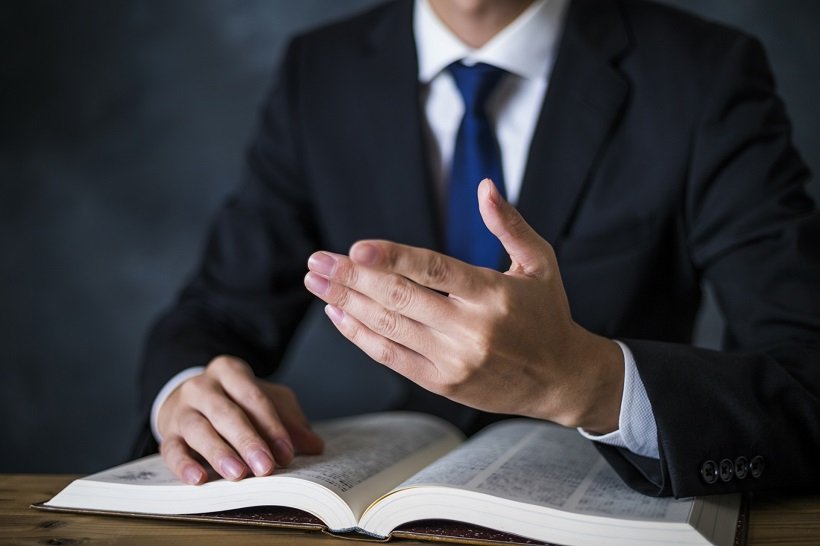1.はじめに
著作権法には、一定の条件を満たす場合には著作権者の許諾を取らなくても著作物を利用できる方法がいくつか用意されており、こうした方法に沿って番組に使用されている素材も少なくありません(これらを「権利制限規定」といいます)。とはいえ、条件を満たさない著作物の無断使用は著作権侵害になるおそれがあり、日頃から番組の著作権保護をうたう放送局としては絶対に避けたい事態だともいえます。したがって、番組制作に携わる者としては、上記のような著作権法のルールを正しく理解しておくことはとても大切なことです。というわけで、「引用」について解説した前回に引き続き、今回は権利制限規定の中で放送局がよく使うことになる「時事の事件の報道のための利用」について、あらためて基本的事項のおさらいをしていきたいと思います。

2. 時事の事件の報道のための利用(著作権法41条)
(1)権利が制限される趣旨
日々社会の中で起こるさまざまな事象を伝える報道(ニュース)は、われわれ国民にとって欠かせない情報取得のツールであり、「知る権利」を充足するための重要なインフラです。何か事件が発生したとき、メディアとしては、その情報をより正確に分かりやすく、また素早く伝える必要がありますが、その際、たとえば事件に関連する他人の映像や写真などを使用する上で、すべて著作権者の許諾を取っておかなければならないとなると、どうなるでしょうか。著作権者は誰か? 連絡先は? 使用料はいくら? など、いろいろ調べたり交渉などしているうちに、情報を伝えるスピードは失われ、また許諾を得られなかった場合や、その交渉時間を確保できないときは、伝えるべき情報の量に制限がかかってしまいます。そこで、著作権法では、こうした情報流通の重要性とのバランスを図るため、報道で伝える事象に関連する著作物に関しては、著作権者の許諾を得ずともよい、という「時事の事件の報道のための利用」という権利制限規定を設けたのです。
(2)要 件
では、どのようなケースで「時事の事件の報道のための利用」が認められるのか、条文に沿って要件を確認していきましょう。
① 「時事の事件」
国民に知らせるべき情報の迅速な伝達、という公益のために誰かの著作権を犠牲にするわけですから、その情報には、一定程度「【今】伝える必要性」(時事性)があることが求められます。もっとも、「今日の朝、著名な絵画が盗まれた」といったような、速報性の高いブレイキングニュースに限定されるかといえばそうではなく、その事件を今伝えるべき必要性が新たに生じれば、過去の出来事であっても「時事の事件」といえると考えられています。先ほどの絵画の盗難の例でいうと、これがたとえ数年前の事件であったとしても、「絵画の窃盗団が逮捕された」と伝える最新ニュースの中で、過去の代表的な犯行として当該窃盗事件を取り上げることは、全体として「時事の事件の報道」といえるでしょう。
なお、「事件」というと一般的には刑事事件や事故を連想する人も多いと思いますが、ここでの「事件」は要件として特に大きな意味はなく、報道の対象となる何かしらの出来事、といった広い概念として捉えておけば問題ありません。
② 「当該事件を構成」する著作物
報道によって伝えるべき事象そのものに著作物が含まれているようなケースです。そこで、先の例でいいますと、「絵画が盗まれた」というニュースにおいては、当該絵画はニュースで伝えるべき対象そのものですから、当該事件を構成する著作物といえます。したがって、当該絵画を、「これがその盗まれた絵画です」と映像で流すことは、著作権者の承諾なく行うことができます。
③ 「当該事件の過程において見られ、もしくは聞かれる」著作物
上記②のように、報道対象そのものが著作物であるケースではないものの、特定の事象(事件)を報道によって伝える場合、その事象に視聴覚的に付随するがゆえに、当該著作物の使用が避け難いようなケースを指します。同じく「絵画が盗まれた」というニュースで説明すると、絵画が盗まれた美術館の現場を映像で報じる際、隣に飾られている他の絵画が映り込んでしまうような場合です。あとは、よく例として挙げられるのは、スポーツ大会の入場行進を映像で伝えるニュースの中で、会場で流れる行進用BGMが聞こえているようなケースですね。このような場合は、当該絵画やBGMの利用許諾を取得する必要はないことになります。
④ 「報道の目的上正当な範囲」
この要件は、分かりやすくいえば「やり過ぎはダメ」ということを示すものです。上記①や②を形の上では満たすとしても、もはやニュースは二の次で、当該著作物を鑑賞させること自体が目的化しているような使い方は、本条を悪用した不当な著作物の利用だとして、この要件を満たさない(=原則に立ち戻って著作権侵害になる)ことになります。「絵画が盗まれた」というニュースの中で、被害品の絵画を脈略もなく延々と映し続けたり、明らかに隣の絵画を映し込んで視聴者の目を引こうとしたりするような使い方ですね。
(3)補足~訃報や事件の際の過去作品の使用について~
人気グループの解散時や著名人の逝去の際など、著名人が絡む大きな出来事があったときに、当該著名人が過去に出演していた番組や映画などの切り抜き映像が使用されることがありますが、こうした過去映像の部分使用が「時事の事件の報道のための利用」に当たるかというと、要件の上では「当たらない」というのが正しいです。「解散」や「逝去」という出来事そのものに含まれる映像ではない(=当該事件を構成するとはいえない)し、そのニュースを伝える上で必然的に付随するような映像でもない(=当該事件の過程において見られ、もしくは聞かれるとはいえない)からです。もっとも、著作権法の分野で著名な学者には、「常識的に考えて、このような場合には権利者の損失にも繫がることもほとんどないであろうし、緩やかな解釈をして、ある事件と相当な関連があれば41条の適用を認めるべき」と提言する人([1])もいて、法的な解釈に関してはやや揺らぎのある分野だといえますね。
この点、実務に目を向ければ、純粋な一部使用だと割り切って許諾を求めていくケース、上記の学者のような見解を取るケース、あるいは、「引用」などの他の制限規定などによって整理を試みるケースなどもあり、業界全体で統一的な解釈・運用が行われているという状態ではありません。映像の権利者から問い合わせを受けたときのために、制作・編集担当者は、こうしたニュースを制作・編集する際、自局においてはどういった根拠で部分的使用が行われているのかを、知っておくとよいでしょう。
3.終わりに
以上、2回に分けて「引用」と「時事の事件の報道のための利用」という権利制限規定を確認してきました。放送局は、あらゆるジャンルのあらゆる情報を取り扱いますが、近年の状況をみるに、テレビだからといって誰でも気軽に権利を預けてくれる、許可をしてくれる、といった時代は過ぎ去りつつあります。
時として誰かの権利の対象となる「情報」を、いかなる法的根拠に基づき、迅速かつ効果的に視聴者に届けていくのか、その知識とノウハウは、テレビ制作の現場では今後ますます重要になっていくだろうと思います。ぜひ、こまめに知識にアップロードしていっていただければと思います。
[1] 中山信弘著『著作権法[第2版]』(有斐閣)
このほかの【「現場で活かせる」法律講座シリーズ】の記事はこちらから。