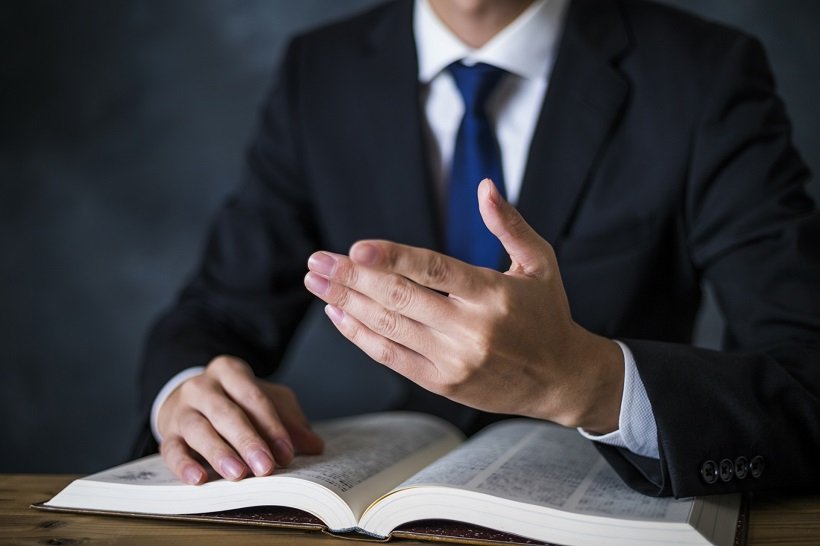1.はじめに
放送局は年間、数えきれないほどの放送番組を制作・放送していますが、その中では、自ら制作し、著作権を保有する素材(映像、写真、テキストなど)だけでなく、第三者が著作権を有するさまざまな素材を使用することも多いです。もちろん、著作物の利用にあたっては、著作権者から許諾を得て使用するのが原則的な対応となりますが、著作権法では、一定の条件を満たす場合には著作権者の許諾を取らなくても著作物を利用できる方法がいくつか用意されており、こうした方法に沿って番組に使用されている素材も少なくありません。
たとえば、番組制作でよく使われる代表的な例は、「引用」や「時事の事件の報道のための利用」ですね。こうした例外的な方法を「権利制限規定」などといったりしますが、時折「これは条件を満たさないのでは?」と思われるような使い方を目にすることがないとはいえません。条件を満たさない著作物の無断使用は著作権侵害になるおそれがあり、日頃から番組の著作権保護をうたう放送局としては絶対に避けたい事態だともいえます。
したがって、番組制作に携わる者としては、上記のような著作権法のルールを正しく理解しておくことはとても大切なことです。というわけで、この連載では2回に分けて、権利制限規定の中で放送局がよく使うことになる「引用」と「時事の事件の報道のための利用」について、あらためて基本的事項のおさらいをしていきたいと思います。第1回目のテーマは「引用」を取り上げます。
2.引用(著作権法32条1項)

(1)公表された著作物
利用したい著作物は、「公表」されたものでなければいけません。公表とはいつの段階か? ということが問題になりますが、簡単にいえば、著作権者やその許諾を得た人が、その著作物を世間一般(不特定もしくは多数の人)に向けて、演奏したり、上演したり、放送したり、展示したりした時点のことをいいます(著作権法4条参照)。たとえば、まだ限られたグループ内でしか共有されていない未発表のコンテンツは公表されたものとはいえませんので、いかに他の条件を満たしていても、「引用」が成立することはありません。「最近亡くなった著名作家の遺作が見つかった」として、引用を根拠に放送でその内容を紹介することはできないということです。とにかく「未発表のコンテンツ」は引用では使用できない、と覚えておきましょう。
(2)公正な慣行に合致する
「公正な慣行」が何を指すかは、著作権法で明文化はされておらず、商用利用か非商用か、書籍なのか映像なのか、論文なのか娯楽小説なのか、といったように、コンテンツの使用媒体や種類などによって異なり得ると理解されています。放送に関していえば、放送は番組を通じた視聴覚的方法によって、多種多様な情報を伝えていくことを目的とする媒体ですから、まずは番組の中で分かりやすく情報を伝える際の一助として関連する著作物を使用している、といえる関係値が重要になります。
①明瞭区分性
そのうえで、最高裁判例(※)に基づいた伝統的な考え方によると、引用する著作物が引用物だと分かるように、きちんと線引きをした編集をしておくことが重要だといわれています(明瞭区分性)。編集の繋ぎ方や紹介の仕方などからみて、視聴者が局側で制作したコンテンツなのか、引用している著作物なのか区別がつけられない使い方はダメだということです。この点は、使用する引用著作物には、その表示中にテロップなどで「〇〇より引用」といった形で引用の旨や出典などを明示しておく、ナレーションやコメントで他人の著作物であることに言及する、といった方法が考えられます。とにかく、自前のコンテンツと、しっかり区別して使うことを意識しましょう。
②出所明示
公正な慣行に合致するかどうかを判断する上で、出所明示(著作者、著作権者、著作物名など出典を示すこと)の有無が考慮されることがあります。この点、著作権法は「複製」によって引用を行う場合は出所明示を義務付けています(著作権法48条1項1号)が、「放送」に関しては「出所明示の慣行がある場合だけでよい」としており(同3号)、放送番組の中で著作物を使用する際に出所明示がマストという建付けにはなっていません。したがって、放送というジャンルにおいては、単に出所明示がないことをもって、即座に「公正な慣行に合致しない引用」だと判断されることにはならないと考えられます。とはいえ、一般論としては出所明示があった方が相当程度リスクは低減できるといえますので、基本的には、尺や表示画面の制約から難しいケースを除き、引用するときは出所表示を行うことをお勧めします。
(3)引用の目的上正当な範囲内
この要件はものすごく平たくいえば、「引用が必要だからといって、やり過ぎはダメ」ということです。著作権法は、著作権者側の利益も考慮して、引用する目的に沿って、その目的達成のために必要な部分だけ使うことを許しているのです。では、やり過ぎかどうかは具体的にどのように判断すればよいのでしょうか。
上記の明瞭区分性とともに、最高裁判例で示された分かりやすい判断基準の一つは、引用の受け皿になる自己のコンテンツと、引用する著作物との間にきちんと「主従関係」があるかどうか、という点です。ここでの「主」は自己のコンテンツ、「従」は引用する著作物のことを指します。イメージしやすいように極端な例でいえば、60分の番組中、1分が自己制作で、それ以外の59分は他人の映像を使用した、という状態では主従関係が逆転してしまっており、引用だとは認めてもらえないということになります(実際は単純な量の比較だけではなく、引用の目的や方法なども加味して、主と従を見定めます)。要するに「番組で伝えたい情報がまず前提として存在し、それを伝える一助のために関連する著作物を使用している」という大事な関係値が崩れている(引用する著作物の方がもはやメインコンテンツになってしまっている)ということですね。
そのほか、一部でこうした関係値は一応維持できているものの、明らかに関係ないところまで使いすぎ、というパターンも、引用の必要性がないとして、正当な範囲内の引用とは認めてもらえないことがあります。たとえば、情報番組で火災事故の際の注意点を伝える際、実際の火災の様子が撮影されたYouTube動画を使うようなケースで、その動画に含まれている火災以外のシーンまで使用するのは、必要性なしと判断されるおそれがあるでしょう。
以上から、放送において「正当な範囲内」の引用を行うには、(ⅰ)視聴者に伝えたい情報をベースに自己のメインコンテンツ(番組そのもの)をきちんと制作すること、(ⅱ)視聴者に分かりやすく当該情報を伝えるという目的との関係からみて必要な範囲にとどまっていること(関係のないところを使わない)、というルールを意識するようにしてください。
3.終わりに
以上、主に放送番組における他人の著作物の利用を念頭に、「引用」に当たるか否かを判断する基本的なポイントについて解説しました。時間的制約がある中で、日々大量の番組を制作・放送する放送局の現場においては、他人の著作物を使用する上で、確かに「引用」という手段が用意されていることは非常に助かることではあります。しかし、「引用」という受け皿があるからといって、上記のようなポイントを押さえないまま、なんとなくの感覚で引用を多用した番組制作を進めると、いずれ法の許容する範囲を超えた著作権侵害を引き起こすリスクに直面するおそれがあります。繰り返しになりますが、放送局にとって著作権侵害は絶対に避けなければならない事態だといえますから、特に番組制作に携わる現場の方は、これを機会に上記のような基礎だけでも押さえていただけるとよいかと思います。
次回は「時事の事件の報道のための利用」の基本的なポイントを解説します。
(※)モンタージュ写真事件/最高裁昭和55年3月28日判決・民集34巻3号244頁
適法な引用と認められるためには、「引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区分して認識することができ、かつ、右両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合でなければならない」との判断基準を示した。なお、「明瞭区分性」と「主従関係」の要件の位置づけは、文化庁の考え方を参考にしています(令和6年度 著作権事務担当者講習会 「著作権制度の概要について」28頁、外部サイトに遷移します)。
このほかの【「現場で活かせる」法律講座シリーズ】の記事はこちらから。