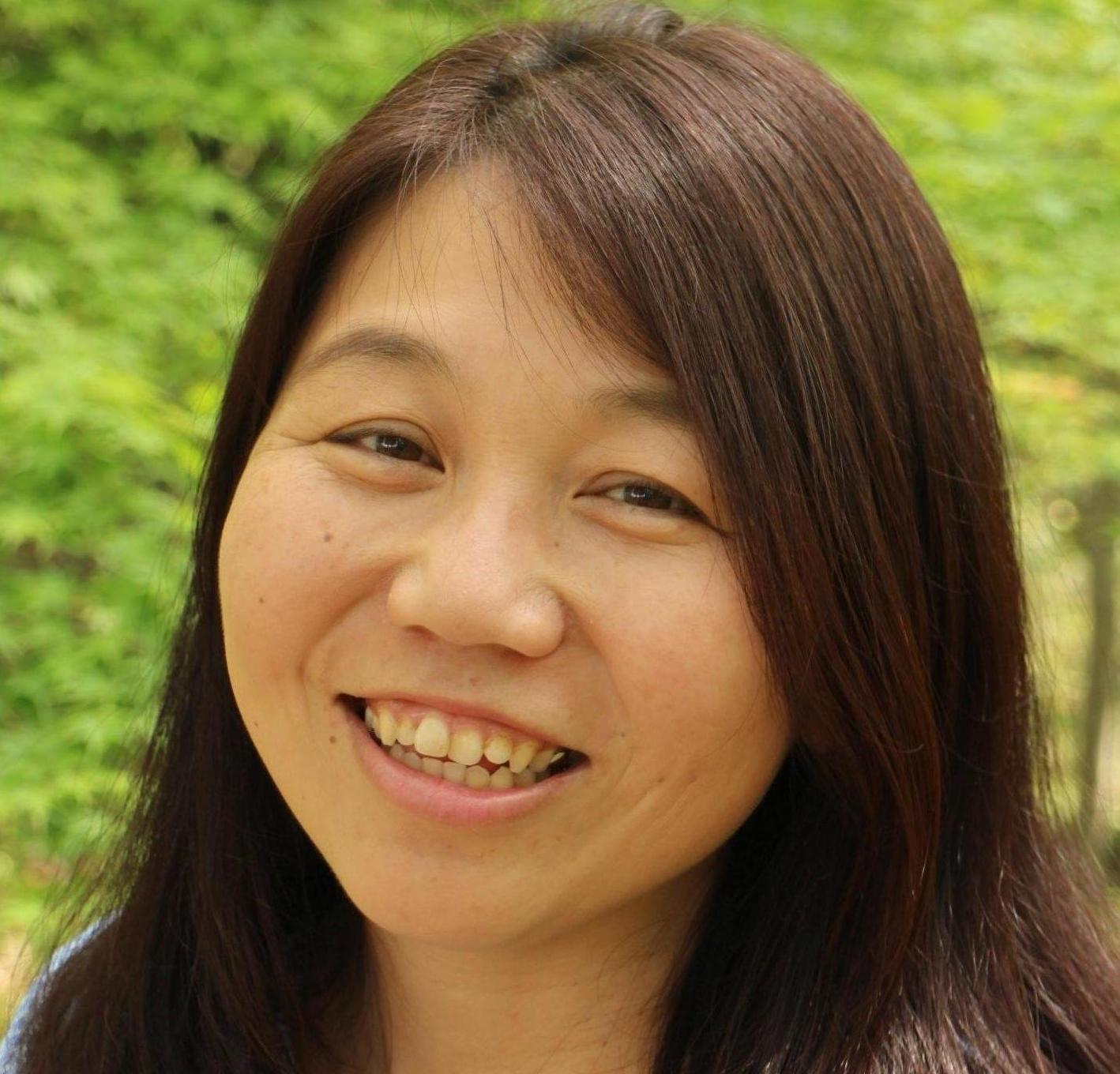ローカル局が「地域密着」「長期取材」による優れたドキュメンタリー番組を放送していることは知られていますが、その局以外の地域の視聴者が目にする機会が少ないという現状があり、ドキュメンタリー番組の存在や価値が社会に十分に伝わっていないという声も聞かれます。
そこで「民放online」では、ノンフィクションライターの城戸久枝さんにローカル局制作のドキュメンタリーを視聴いただき、「鑑賞記」として紹介しています(まとめページはこちら)。ドキュメンタリー番組を通して、多くの人たちに放送が果たしている大切な役割を知っていただくとともに、制作者へのエールとなればと考えます。(編集広報部)
『私はナニモノ?~中国残留邦人の80年~』
関西テレビ放送「ザ・ドキュメント」で2025年8月29日放送
本作品の主人公、大学生の高橋小晴さん。曾祖母が戦後の中国に残された中国残留邦人だった中国残留邦人4世だ。
小晴さんの母親は残留邦人3世、父親は中国人。日本で生まれ育った彼女だが、自宅では父親が中国語を話し、家では中国の料理が出てくる。同級生たちに「お父さん中国人やんな」と言われたとき「ちゃうよ」と強く否定した。幼いころから抱いていた違和感を描いた作文を読むと、胸が締め付けられる。
「ずっと生きるのがつらかった 日本で生まれ育った私の中でも、中国の存在がとても大きく、物心ついたときから自分は周りの人と何かがちがうと思っていた」「大好きな故郷の中国を否定したとき とても後悔した」
揺れ動く中国残留邦人4世、小晴さんの姿が、30年前の私自身の姿と重なった。実は私の父もまた中国残留邦人だった。小晴さんと違うのは、私の父は日本に帰国してから日本人女性と結婚したこと。だから私には中国の血は流れていない。それでも私もまた日本文化のなかで、周囲の中国に対する視線を気にしながら生きてきた。父のことを知りたいと思い立ったのはちょうど、小晴さんと同じ大学生のとき。小晴さんと同じように一人で中国を訪れた。留学生活のなかで、自分が中国と日本の歴史のことを何も知らなかった事実に強く打ちのめされたのを鮮明に覚えている。
中国残留邦人2世で大学教授の大久保明男さんは小晴さんにこう言った。「ご家族の経験を持っているから、国の歴史観から離れて個人の家族史という視点で歴史を見つめ直せば違う見方ができると思う」。実は彼は私の古くからの友人の一人だ。彼が彼女にかけた言葉は、私自身が、自分のルーツをたどるなかで見つけた一つの答えでもある。まさに日中のはざまで思い悩む若者たちへ届いてほしい言葉だ。
小晴さんに、母、慶子さんが、祖母から聞いた話を話す。彼女にわかるようにかみ砕いて丁寧に伝えるこのシーンがとても素晴らしかった。曾祖母が渡された薬の話を聞きながら涙ぐむ小晴さん。家族と一緒に、家族につながる歴史について話す時間をとても尊く感じた。テレビ電話で「はるちゃんは日本で生まれたからそんなん関係ないのかと思った」と話す叔母。「なんで自分はこんな運命に生まれたんやろう」「なんで私だけ普通の日本人じゃないんやろう」中国残留邦人2世、3世から私が何度も聞いた思いだった。
戦争は80年前に終わっても、戦争によって引き起こされた家族の歴史は続いていく。この日本が、彼女たち4世たちが胸を張って自分のルーツを語ることができる国であってほしい。最後に、中国残留邦人の娘として、4世を取り上げた番組を制作していただけたことに心から感謝を伝えたい。
『老いて、輝く 99歳の看板俳優』
瀬戸内海放送で2025年7月12日放送(テレビ朝日系列「テレメンタリー2025」で2025年7月5日放送)
岡山市在住の岡田忠雄さんは15年以上、認知症の妻の介護をしてきた。妻は自分のことを20代と思い、忠雄さんのことも忘れてしまっている。「今日こそ殺してやろうかと身が震えた」。忠雄さんの日記には、介護の苦悩がつづられていた。忠雄さんが88歳の時に出合ったのが、劇団OiBokkeShiの主宰で介護福祉士の菅原直樹さんのワークショップだった。認知症の方の世界に寄り添い、笑いを取り入れることで、忠雄さんの笑顔も増えていく。そして忠雄さん自身も役者として舞台に立つようになる。演じられるのは、忠雄さん自身が体験した認知症の妻との日々をもとにした物語だ。妻が見ている世界を否定せず、演技で受け入れることで笑いが絶えない介護になっていく。
私は4年前から認知症対応型のデイサービスで仕事をしている。利用者の方が笑顔になれる瞬間を探して、絵をかいたり、歌をうたったり、試行錯誤の毎日だ。認知症の方を介護する家族の苦悩する姿を、何度も見てきた。何が正解かわからない介護の世界で、孤独に陥る家族たちも多い。忠雄さんたちの劇が、認知症にかかわる多くの人に光を当てているように感じた。
忠雄さんはその後、脳梗塞で入院する。年齢を重ねることで、できないことが増えていった。2023年には妻が他界する。自身も体に麻痺が残り、介護する側から、介護される側になった。セリフの覚えもさらに悪くなっていく。それでも、演技への情熱は増していくばかりだ。
久しぶりに菅原さんが会いにきたときの忠雄さんの言葉が胸にくる。
「降ろされたと思った。それを素直に受け入れるべきだと思った。一生懸命に考えて
捨てられるのがいいと。そしたらきちっと諦めがつく。だけどもね......舞台は出たい」
2年ぶりの舞台『恋はみずいろ』への出演がきまった。99歳になった忠雄さんの舞台は困難の連続だった。直前まで劇の流れを把握することに苦労して、リハーサルもうまくいかない。それでも彼の思いをかなえようと周囲の人々が懸命に支え続ける。待ち時間も睡魔と戦いながら、始まった本番。緊張感が走るなか、なかなかセリフが出てこない忠雄さんをだれもが静かに見守る。ひょいと表情を変えた忠雄さんがセリフを発した瞬間、何とも言えない感動に包まれる。どこまでが演技なのか、どこからが素なのか、わからない。それでもそこには舞台に立つ一人の人間としての意地があるように感じた。忠雄さんの言葉に、表情に、私もすっかり引き込まれていた。
老いて、輝く。素晴らしい言葉だ。高齢化が進み、3人に1人が高齢者となった今、老いてこそ輝こうとする忠雄さんの生きざまが、多くの人の心に届くことを願う。
『太一の光~全盲ストライカーの見つめる世界~』
長野放送で2025年5月30日放送(フジテレビ系「FNSドキュメンタリー大賞」で2025年9月8日放送)
ブラインドサッカーとは、アイマスクを付けた選手がボールから出る音、ガイド、監督の声をたよりにゲームをすすめるスポーツだ。全盲の平林太一さんは、6歳の時にブラインドサッカーに出合った。学校の先生や家族の協力を得ながら、ブラインドサッカーに夢中になっていく太一さん。番組は、小学3年生から10年間の太一さんの成長を追い続けた。番組関係者の顔に手をあてて、無邪気に笑う小学生の太一さん。彼の夢は、ブラインドサッカーの日本代表になること。夢に向かって太一さんは歩んでいく。
小学6年生の時には、平日は自宅を離れ、盲学校の寄宿舎で生活をはじめた。決めたのは太一さん自身。自立のための訓練だ。そこで、その後長い付き合いになる親友にも出会った。高校は、盲学校ではなく、普通の高校に通うことを決意した。
高校で初めて晴眼者とともに学んだ。学校には点字ブロックが設置され、支援担当の教師も配属された。点訳ボランティアや友人など、さまざまな人のサポートで、無事3年間を過ごすことができた。ブラインドサッカーでも、日本代表に選出され、パリパラリンピックに出場。子どものころからの夢をかなえることができた。
ただ、彼は言う。盲学校より普通の高校がいいというわけではない。そういう選択肢があってもいいのだと。太一さんが目指しているのは、障害がある、なしにかかわらず、どんな人でも対等に暮らすことができる共生社会だ。きっかけは、小学生のときの出来事だった。近くの小学校に交流に行った。目が見えないことを不思議に思われ、うまく交流できず、つらい思いをした。だが、自分自身を知ってもらうために目の見えない状況を体験する授業により、同級生たちが太一さんの状況を理解してくれた。音のなる太一さんのサッカーボールで「一緒にサッカーしよう」と誘われた。「こうやって世界は分かり合えるものだ」太一さんは喜びを作文にそうつづった。
障害のある方を取り入れた番組は、どうしても堅い、あるいは暗い印象になりがちだ。だが、太一さんの明るさが、番組を常に明るく引っ張っているように感じた。明るさの先に垣間見えるのは、自身の思いをしっかりと言葉にする意志の強さだ。太一さんの言葉には力があった。
さまざまなことにチャレンジし、自ら進む道を切り開いてきた太一さん。彼がどのような道を歩んでいくのか。これからも彼から、目が離せない。
(編集広報部注)『太一の光~全盲ストライカーの見つめる世界~』は2025年日本民間放送連盟賞「青少年向け番組」優秀に選ばれた。審査講評はこちらから。