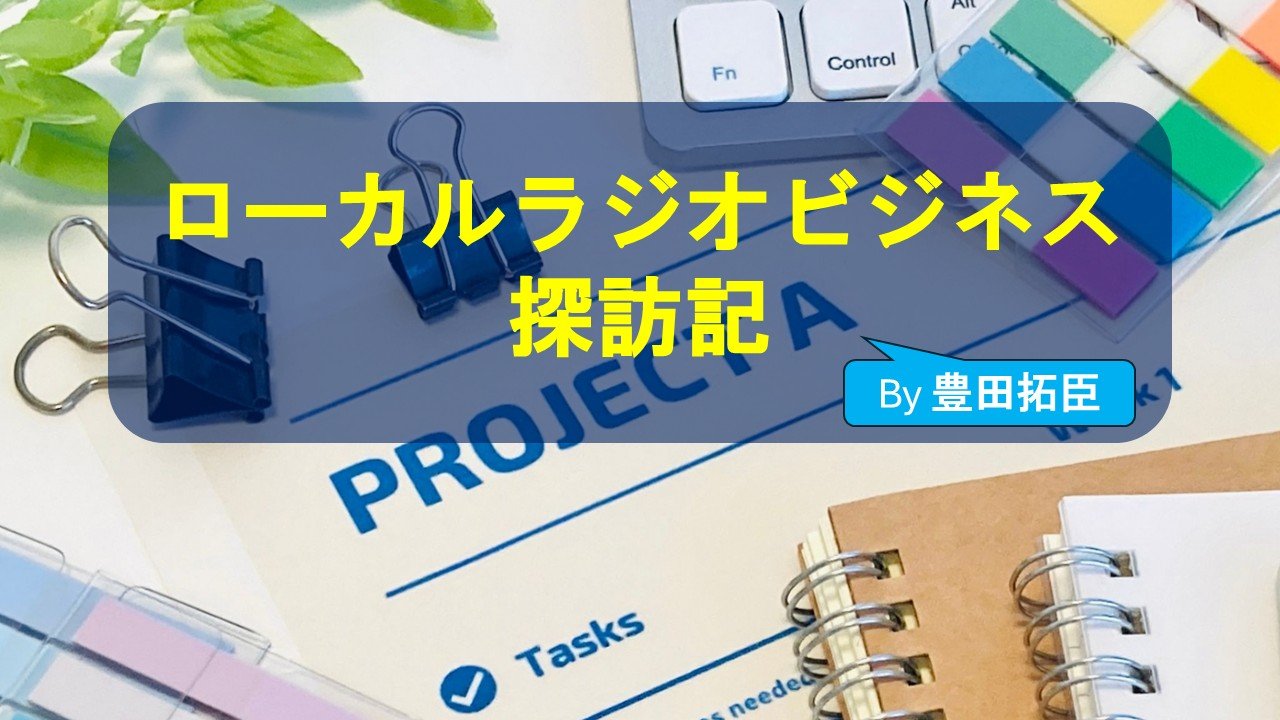ラジオ局が手がけるイベント、グッズ販売、ポッドキャスト配信etc.――。ローカルラジオを中心に放送外ビジネスの事例を取り上げ、ラジオ事業の可能性を探ります。ライターの豊田拓臣さんが各局の担当者などへの取材をもとに経営の側面にも焦点を当て放送外ビジネスのノウハウの一端に触れていきます(まとめページはこちらから)。第1回は、IBC岩手放送の「IBCシニアフェス2025」。(編集広報部)
各地で開催されている「フェス」。ひと昔前は音楽イベントを指すことが多かったが、今や「食」「スポーツ」「アート」などさまざまなテーマで行われている。放送局が主催しているものも多くあるが、その中で異彩を放つタイトルを見つけた。IBC岩手放送が2025年5月24日と25日に開催した「IBCシニアフェス2025」がそれだ。
「シニア」と「フェス」。イメージとしては相容れない。さらに、シニア、すなわち高齢者向けのイベントというと、「終活」をテーマにしたものを最近よく耳にする。それら終活イベントとの違いは何か――。IBC岩手放送営業局長兼テレビ営業部長の佐々木昭人氏に尋ねた。
「終活もテーマとしてあるのですが、それだけにとらわれず、『元気なシニア』をターゲットにできないかと思いスタートしました」
確かに、終活というと介護や医療などの「死を目前にしたとき」や、葬儀や相続などの「死後」が中心となる。しかし、「アクティブシニア」という言葉があるように、まだ終活を必要としない高齢者も多い。その層を対象としたわけだ。
なお、「IBCシニアフェス2025」は、同じTBS(JRN)系列である中国放送(RCCラジオ)の「RCC終活博覧会~シニアにYELL~」と、南日本放送(MBCラジオ)の「GO!GO!アクティブフェア」を参考にしたそうだ。MBCラジオからは、人生相談トークショーについての実践的なアドバイスを受けたという。

<「IBCシニアフェス2025」開場を待つ来場者のみなさん>
新しいテーマに取り組むイベントの苦悩
さて、「IBCシニアフェス」のウェブサイトを見るに、①ゲストを招いてのいわゆるステージイベント、②協賛社によるセミナー、③協賛社によるブース出展の3つの柱で構成されている。このうち②と③を販売し、得られた協賛金が主な売上となる。具体的にどうやって協賛社を集めたのか。前述の佐々木氏に聞いた。
「まずは法律関係、保険、健康、葬祭関係といった分野ごとの企業リストを作り、それを基に本社と東京のラジオ・テレビの営業マンがセールスを行いました」
「シニア」から連想される企業への販売を行ったわけだ。とはいえ、「IBCシニアフェス」は今回が初開催。大変さはなかったのだろうか。
「スタート時のイメージの共有が難しかったですね。私は言い出しっぺなのでイメージができるのですが、それをどう伝えるか。『どういう人がどれぐらい来るか』が分からない中でのセールスは、営業としては大変だったと思います」(佐々木氏)
既に世間的な認知がある「終活」ではなく、より広い「シニア」をテーマにしたがゆえの悩みといえよう。そうした困難を乗り越え、最終的には地元に根ざした企業から全国的な知名度のある企業まで、20の協賛社が集まっている。
ラジオがセールスに与えた好影響
また、IBCラジオ・テレビ共同イベントの「IBCシニアフェス」だが、佐々木氏はラジオとの親和性を強く感じる点があったという。
まず、イベントのターゲットとリスナーの年齢層の近さが挙げられる。ラジオリスナーは年齢層が高いと常々いわれており、総務省が2025年3月に発表した「ラジオ放送聴取等の実態に関する調査研究報告書<概要>」にも、「年齢層は、男性・女性ともに50代~70代の割合が高く、ラジオ聴取者の半数を占める」とある。佐々木氏も「IBCラジオは60歳を越えたアナウンサーが根強い人気を誇ることもあり、シニアに強い」と口にする。

<ラジオ番組『テレフォン人生相談』出演者による人生相談トークショーは立ち見客も出る人気(2025年5月25日)>
次に、セミナーのセールスとの連続(連動)性が挙げられる。セミナーのスポンサーには事前にラジオに生出演し、どんな内容かを説明してもらったという。つまり、「もう少し詳しく知りたい人はセミナーへ」と誘導できたわけだ。さらに、ラジオは1人で聴くことの多いパーソナルなメディアであるため、リスナーはマイクの前の声を「自分に語りかけている」と捉える。結果、話に興味のある人だけを集めることができ、スポンサーの満足度も高まるという好循環を生み出せる。
そして、これはブース出展にもいえる。リスナーは自分事と捉えてイベントに参加するため、ブースでの相談や商談、体験コーナーへの参加率が高くなる。事実、佐々木氏は出展社である「JR東日本 大人の休日倶楽部」(JR東日本盛岡支社)から、開催2日間トータルで120~130件程度の相談があったといわれたそうだ。「IBCシニアフェス」の来場者数が2日間で約1,000人だったというから、かなりの割合の人が話を聞いていったことになる。次回の出展を望む声もあったとのことで、満足度の高さがうかがえる。

<ブースでの相談者も多かった「JR東日本 大人の休日倶楽部」>
「シニアフェス」の今後の展望
自社を会場にするなどして支出を抑えたことで、バランスの良い収支で終えられたという今回の「IBCシニアフェス」。来年に向けた改善点はあるのか。佐々木氏に聞いた。
「結構、1人で来た方が多かった印象なんです。もう少し人を集めるためにも、例えばお孫さんと一緒に来てもらったり、家族連れで楽しめたりするものにできないかと考えています」
当初は2日間で2,000人来場を目標としていたが、前にも触れたように実際は1,000人。届かなかった要因はこの辺りにありそうだ。では、次回の動員を伸ばすために、協賛についてほしい業種などはあるのか。
「本当に今、元気な女性のシニアの方も多いので、『美容』や『健康』といったジャンルを押し出したいですね。他にもスポーツ店に協力してもらってウォーキングポール(手に持って歩行を補助するなどの目的で使うポール)の体験ができたりだとか、楽器店と協力して音楽などの趣味に関する部分を強くしたりできると、イベントとしての幅も広がりますよね」
「シニア」と「ラジオ」と「イベント」の相性の良さは以前から感じていたが、この取材でも納得できた。であれば、この「IBCシニアフェス」がより大きなイベントに育ち、成功例となれば、ラジオ業界は「終活イベント」より間口の広い「シニアイベント」を新しくセールスのアイテムに加えることができる。そういった意味でも、今後の展開を注視したいイベントだ。