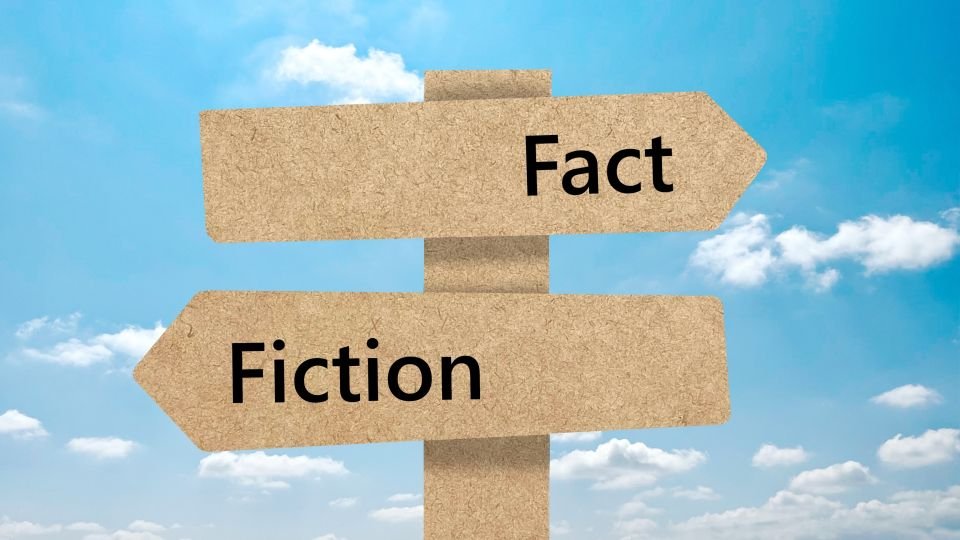SNS選挙とマスメディア不信の新局面
2024年7月の東京都知事選、10月の衆院選、11月の兵庫県知事選では、SNSや動画サイトが有権者の投票行動に強い影響を与えた。だが、いわゆる政治系切り抜き動画のなかには、誤解を招く編集が多く見られ、一部の有権者が誤った認識を持つ要因にもなった。特定の候補者を支持するインフルエンサーが大量の動画を投稿し、それが偽情報の拡散につながったことも指摘されている。
インターネットに真偽不明の情報が蔓延するなかで、「新聞やテレビは既得権益を守ろうとしている」「マスメディアは真実を隠している」といった論調に対して、多くの有権者が共感を示した。それにもかかわらず、新聞やテレビの選挙報道は依然として抑制的で、マスメディア不信に歯止めをかけることができなかった。また、政治家や候補者がSNSを通じて、マスメディアの公平性に疑問を呈し、「偏向報道」と批判する場面も目立つようになった。
こうした現状は、2016年のアメリカ大統領選、および第1次トランプ政権下のメディア状況を彷彿とさせる。よく知られているように、当時はSNSを駆使した扇動的な選挙工作によって、膨大な有権者がフェイクニュースや陰謀論に翻弄された。また、トランプ大統領は就任後、気に入らない報道を「フェイクニュース」と呼び、マスメディアを敵視する姿勢を鮮明に打ち出した。ジュリアーノ・ダ・エンポリ『ポピュリズムの仕掛人:SNSで選挙はどのように操られているか』(林昌宏訳、白水社、2025年)は、SNSに蔓延する極論がいかにして中道を切り崩し、社会の分断を加速させてきたかを詳しく跡づけている。
それに比べて、日本では近年まで、ネット世論と選挙結果は必ずしも一致せず、SNSによる選挙工作の効果や影響も限定的だった。しかし昨年来、状況が大きく変わりつつある。SNSと政治の関係は混迷の度を深めるが、SNSを通じた市民の声やオンライン上のムーブメントにも変化の兆しがみられる。
欧米では2017年、いわゆる「#MeToo運動」が大きな広がりをみせた。エンターテインメント業界に限らず、さまざまな職場で働く女性の安全配慮や尊厳確保を追求する世界的運動に発展したが、日本への波及は限定的なものにとどまった。ところが今年、フジテレビの社内問題への関心がピークを迎えた1月下旬以降、「#私が退職した本当の理由」というハッシュタグを通じて、主に女性たちが、職場で経験したハラスメント、性差別や性暴力などを告発する動きが広がっている。
こうして良くも悪くも、SNSの影響力が高まるにつれて、マスメディア不信は不可逆的に進行している。そして欧米の後を追うように、日本でも社会の分断が加速する懸念が強まっている。放送メディアが今、信頼回復のためにできることは何だろうか。
「伝えない」ことの説明責任
そもそも20世紀においては、新聞やテレビが「伝えない」と判断したことがらについて、多くの国民は知る手段を持たなかった。報道機関は、国民の「知る権利」との兼ね合いを考慮しながら、何を伝え、何を伝えないかを判断してきた。たとえば、テレビの事件報道において、加害者や被害者の氏名や顔写真を報じるかどうかは、法令や放送基準を踏まえた判断が積み重ねられてきたが、その基準を公に説明する必要はなかった。
しかし、現在は状況が大きく異なる。インターネットで調べれば、テレビで報道される以上の周辺情報を知ることができる。プライバシー保護などに配慮して、慎重な判断のもとで報道を控えたとしても、SNSではすぐに批判の対象となり、情報操作や忖度が疑われることもあれば、「マスコミが伝えない不都合な真実」といった陰謀論として拡散されることもある。
一見すると語義矛盾のようだが、報道機関には、「伝えないことの説明責任」を果たすことが求められる時代になっているように見える。たとえば、WHO(世界保健機関)が定める自殺報道ガイドラインの趣旨は広く知られており、報道機関があえて説明しなくても、抑制的な報道が批判されることは少ない。一方で、読者や視聴者の理解を得にくい事案については、ウェブサイトで報道方針を説明するなど、すぐにでも取り組めることがあるのではないだろうか。
手の内をさらし、ネット世論との棲み分けを
選挙報道の話に戻ろう。放送法第4条には「政治的に公平であること」が定められており、選挙報道のたびにそのあり方が問われてきた。2024年の兵庫県知事選では、報道番組での生討論にすべての候補者が呼ばれなかったことが、SNSで「偏向報道」と批判された。
過去の選挙でも、主要候補のみを取り上げた番組は繰り返し批判されてきた。それを受け、BPO放送倫理検証委員会が2017年に公表した「2016年の選挙をめぐるテレビ放送についての意見」(外部サイトに遷移します)では、放送局には「選挙に関する報道と評論の自由」があり、求められるのは「量的公平」ではなく、政策の内容や問題点など、有権者の選択に必要な情報を伝えるために、取材で知り得た事実を偏りなく報道し、明確な論拠にもとづく評論をするという「質的公平」であると指摘している。こうした整理を踏まえながら、現在の選挙報道がかたちづくられていることを、もっと分かりやすく伝える努力も重要だろう。
一方、フジテレビは今年1月、1度目のクローズドな記者会見での杜撰な対応が厳しく批判されたが、2度目のオープンな謝罪会見では、10時間以上にわたる追及のなかで、一部質問者の乱暴な発言にSNSで批判が集中し、取材者のリテラシーや人権意識まで厳しく問われる事態となった。共倒れである。
オープンな会見が評価される風潮が強まる一方で、「#私が退職した本当の理由」を通じて可視化されたハラスメントや性暴力の告発のように、プライバシーや心理的ケアへの配慮が必要な会見もある。このような場合、記者クラブなどによる調整のもと、綿密なすり合わせを経てクローズドにおこなわれるのが通例だ。しかし、こうした配慮はテレビの画面越しには伝わりにくい。
いずれにしても、放送メディアは、長年つちかってきた報道の指針や工夫など、手の内を積極的にさらしてはどうか。ネット世論との棲み分けを粘り強く模索し、少しずつ理解を広げていくことなくして、信頼の回復、SNSとの共生の道筋を見いだすことは難しいはずだ。