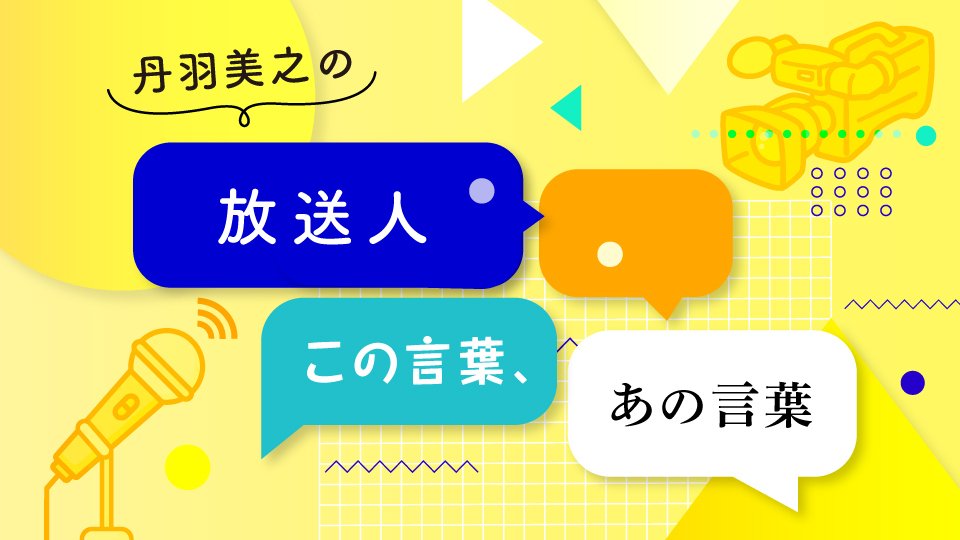面白い番組、優れた番組の背後には魅力的な作り手や演じ手がいます。彼らの残した印象的な言葉は番組制作の極意を伝えるとともに、一種の演出論や映像論、社会論とも言えます。連載【放送人 この言葉、あの言葉】はこれら珠玉の言葉の数々を、東京大学でメディア論の教鞭を執る丹羽美之さんの視点で選んでいただき、毎回ひとつずつ紹介していきます。第2回目はTBSの記者・ディレクターから参議院議員、千葉県知事に転じた堂本暁子さんの「この言葉」です。(編集広報部)
かつてTBS(当時)の報道記者、ディレクターとして活躍し、後に参議院議員や千葉県知事を務めた堂本暁子¹ は、『時代の狩人 ドキュメンタリストの視点』 という本のなかで、テレビの仕事について次のように語っている。
テレビの仕事を始めたころは、自分の主人公は自分自身、という意識が強かった。ドキュメンタリーにあこがれる若者なら誰もが思うように、早く自分の考えで番組がつくりたかった。が、いまは違う。三十年の間に、仕事が私を変えた。いまは、可能な限り白紙の状態でいたいと、いつも考える。自分自身を空っぽにしておくのが理想である² 。
長く報道畑を歩み、独自の視点で優れた調査報道やドキュメンタリーを生み出した堂本が、「白紙」や「空っぽ」が理想というのはどういうことだろうか。1980年代に堂本が取り組んだ画期的な調査報道「ベビーホテル・キャンペーン」を手がかりに考えてみたい。
ベビーホテル・キャンペーンとは?
きっかけはたった一通の投書だった。1980年3月、関東ローカルのニュースワイド番組『テレポートTBS6』に「娘が公立の保育所に入れませんでした。ベビーホテルがブームだそうですが、レポートしてください」という主婦からの声が届いた。当時、「ベビーホテル」と呼ばれる認可外の保育施設が街中に目立つようになっていた。この投書をきっかけに、堂本がベビーホテルの実態を取材して伝えたところ、大きな反響を巻き起こした。「子どもをあざだらけで返されました」「ベビーホテルの取材を続けてください」。放送直後から電話が鳴りやまなかったという。こうして約1年におよぶキャンペーン報道がスタートした。
とはいえ、堂本は最初から明確な問題意識を持って取材を始めたわけではなかった。当時、レジャーや旅行でベビーホテルに子どもを一時的に預ける若いカップルが増えているというのが一般的な受け止められ方だった。堂本も流行の社会風俗を追いかけるという程度の軽い気持ちだった。しかし取材を進めるうちに、劣悪な環境のベビーホテルが乱立している深刻な実態が浮かび上がってきた。またその背後に、仕事を続けたいにもかかわらず公的な保育園で受け入れてもらえない母親や、昼夜を問わず働かざるを得ないシングルマザーが数多くいることもわかってきた。堂本にとってもそれは驚きの連続だった。
1980年の3月に、ベビーホテルの取材をはじめるまで、私は、その存在すら知らなかった。ましてや、その問題性の深さを予想できるはずがない。ベビーホテルを現代的な子供用預かり所程度に軽く考えていた。私の認識を根底から覆したのは、堰を切ったように寄せられた子供をもつお母さんたちからの訴えであった。ベビーホテルに働く保母さんからの内部告発。認可保育所に対する不平、不満。そして福祉事務所や児童相談所の窓口の誠意のなさへの憤り。ベビーホテル出現の背景には、根深い社会的、歴史的な原因があった。しかも、そこには、現代社会のさまざまな矛盾や歪みが複雑に錯綜している。1年間、取材を重ねるうちに、「ベビーホテル問題」のわかりにくさやむつかしさを理解すると同時に、ことの重大さも知った³ 。
オープンな手法による調査報道
『テレポートTBS6』では、この問題を毎週のように取り上げた。放送に対して視聴者の声が届き、その声をもとにまた取材を重ねて放送するという好循環が生まれ、この問題の広がりと深さが明らかになっていった。取材過程を公開し、読者や視聴者とともに真相に迫っていくその手法は、今でいう「オープン・ジャーナリズム」の先駆けとも言えるだろう。その反響の大きさにも後押しされ、ベビーホテル・キャンペーンは関東ローカルの同番組だけでなく、『モーニングジャンボ・奥さま8時半です』『報道特集』など、TBS全国ネットの他の番組やニュースにもしだいに波及していった。
堂本の活動はここでは終わらなかった。この問題に明確な形を与え、解決を促すには客観的な「数字」が必要と考えた彼女は、局内外の人々と連携し、総合的な調査にも取り組んだ。当時は、ベビーホテルの数やその利用者の実態すら不明だった。調査・解析にはTBS調査部の専門家や、保育・福祉に関わる研究者・学生らが全面的に協力した。毎晩のように面接調査に出向き、その成果を持ち寄っては話し合いを重ね、客観的なデータを積み上げていった。集計の結果、ベビーホテルは都内だけで208カ所、その利用目的は90%以上が仕事のためであり、レジャーはわずか0.2%にすぎないことが明らかになった。
データに裏打ちされた調査報道の力は大きかった。結果的に、ベビーホテル問題は他のメディアでも大きく取り上げられた。世論を動かし、国会でも質問が相次いだ。TBSはキャンペーンの総集編として『ホリデースペシャル こどもの日特集 赤ちゃんは訴える〜ベビーホテル考〜』を1981年5月5日に放送。ついに6月には、ベビーホテルなど認可外の保育施設に対する規制を盛り込んだ児童福祉法の改正へとつながった。たった一通の投書から始まったキャンペーン報道が政治を動かした瞬間だった。
「白紙」から生まれるコミュニケーション
創造は「白紙」に宿る。「白紙」や「空っぽ」とは、決してマイナスの意味ではなく、自分の狭い考えを超える発想の可能性に常に開かれているということである。ベビーホテル・キャンペーンは、視聴者や取材先の人々から寄せられた声に耳を傾け、専門家たちと対話を重ねるなかで、予想外の方向に発想を広げ、隠れた現実を掘り起こすことに成功した。堂本にとってそれは、局内外の人々との創造的なコミュニケーションをとおして、自分の限界を超えていく作業だった。堂本は言う。
だから"白紙"でいたい。小さな自分の頭や考えを超えた広がり・発想をどんどん吸収したい。そのことによって、目に見えないさまざまな事実、水面下でのうごき、隠された鉱脈を掘り起こすことが可能になるのではないか。少なくとも、それが、私のドキュメンタリーづくりから学んだ方法論である⁴ 。
調査報道やドキュメンタリーの現場では、強い信念や正義感を持つことがしばしば求められる。しかしそれがかえって自由な発想やコミュニケーションを邪魔することもある。だから「白紙」でいるためには修練と経験が不可欠である。自分のなかにあるイメージや思い込みにとらわれることなく、どこまで現実の複雑さに迫ることができるか。予断や偏見を排して、いかに目に見えない事実を掘り起こすか。自分の考えや思いに執着せず、「白紙」の状態でいようとすると、これがなかなか難しいのである。
¹ 堂本暁子 1932年生まれ。1959年TBS入社(当時はラジオ東京)。記者・ディレクターとして取材・報道に携わる。教育・福祉などの社会問題をはじめ日本女性マナスル登山隊の同行取材やチベット、北極などの極地取材も。この間、「ベビーホテル・キャンペーン」が児童福祉法改正につながり、民放連賞・新聞協会賞・放送文化基金賞などを受賞。1989年参議院比例区から立候補し当選、95年再選。2001年千葉県知事に当選し、2期8年務める。
² 日本民間放送連盟編『時代の狩人 ドキュメンタリストの視点』MG出版、1988年、p.93-94
³ 堂本暁子編『ベビーホテルに関する総合調査報告書』晩聲社、1981年、p.380
⁴ 日本民間放送連盟編、前掲書、p.95