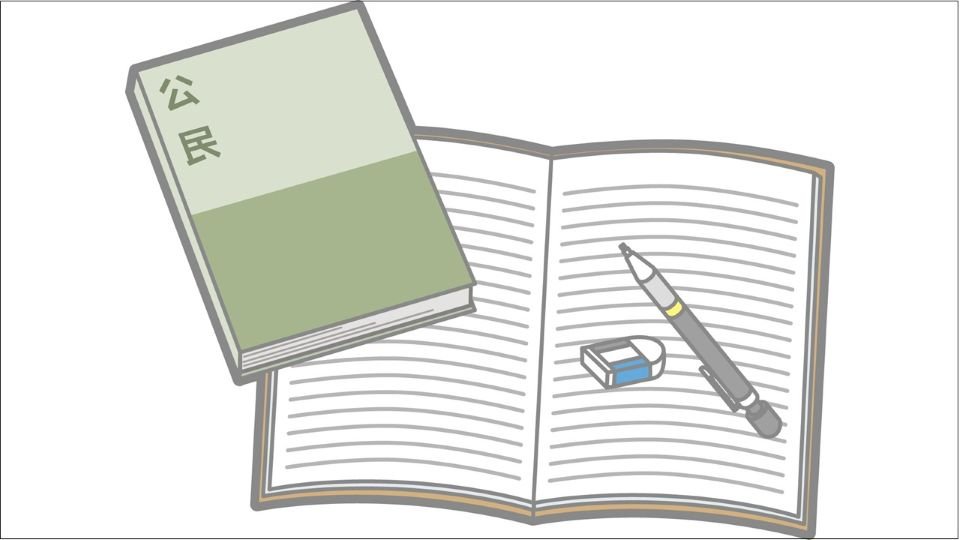サステナブル・ジャーナリズム
昨今、「オールドメディア」への批判が高まっているが、マスメディア批判には二つの側面がある。一つは、業界内の慣習やタブー、自主規制などで、国民が知るべき情報が十分に伝えられていない点を指摘する建設的な批判だ。もう一方は、自分の気に入らないメディアを侮辱的な言葉で攻撃し、自身が支持する政党や政権が批判されたり、扱いが小さかったりすると「偏向報道」として非難する攻撃的批判である。
現在、現実的に権力監視を行えるのは組織ジャーナリズムであり、報道機関としての役割を担っているのは主にマスメディアである。マスメディア不信や攻撃的批判が過度に高まれば、民主主義自体にも危機が及びかねない。 民主主義社会が機能するには、 報道機関が政府や大企業など権力を監視する必要があり、その監視が健全に行われるには、民主主義が機能し、自由な報道が認められていることが不可欠とされてきた。つまり、民主主義の存続には、ジャーナリズムの持続可能性が問われるのであり、車の両輪の関係にある。
教科書の中の「報道」
ジャーナリズムの重要性を踏まえたとき、教育の現場で報道がどう教えられているかにも目を向ける必要がある。現在、新聞の購読率が低下し、ネット広告への移行で経営基盤も危うくなっている。結果、世界中で、地域の課題を報じるメディアのない「ニュース砂漠」の拡大が深刻な危機として認識されている。一方、日本の学生や若い世代と話すと、そもそも「放送」と「報道」の区別すらつかない場合もあり、基礎的知識の欠如を感じることが多い。
それでは、社会科の教科書で、民主主義とマスメディア報道の関係をどう説明しているのか。筆者は「教科書の中のジャーナリズム[i]」で、2024年度に使用されていた中学「公民」・高校「公共(旧 現代社会)」「政治経済」の教科書24冊を内容分析し、参考として1994年度に使用されていた「現代社会」の教科書11冊を比較対象とした。その結果、マスメディアや報道についての扱いはきわめて小さく、役割や機能も十分説明されていないことが明らかになった。
小学校では、5年生の「社会」で、 新聞や放送、インターネットなど情報産業について学ぶ。民主主義との関わりは明確に述べられていないが、教科書には、マスメディアの送り手の声が多く掲載され、正確で公正な情報を届ける工夫や責任について、多くのページが割かれている。
しかし、180~270ページある中学・高校の教科書では、マスメディアや報道について2~4ページ程度しか触れられていない。「ジャーナリズム」という用語にいたっては、分析対象24冊中1冊でしか扱われていなかった。ネット情報の真偽を問うリテラシーをめぐる記述が加えられている一方で、マスメディア報道の意義と役割についての記述がきわめて少ないのが現状だ。
報道の役割は「世論形成」だけか
学習指導要領との関係から、マスメディア報道の扱いは、市民の政治参加における「世論形成」と、それに必要な情報提供機能に焦点が絞られている(新しい権利の領域でも多少扱われるが、本稿では割愛)。本来、マスメディア報道には、人びとの困りごとをすくい上げて問題化したり、問題を議論したりする意見交換の役割もある。しかし「意見交換機能」については、24冊中2冊。また、意見を持つ上で必要な「論点整理、分析、評論機能」も7冊しか取り上げていない。
また、民主主義社会における健全な世論形成には、企業や環境、政治や行政などの「権力監視」報道が不可欠とされる。しかしこの役割も、「公民」で6冊中1冊、「公共」で12冊中4冊、「政治経済」で6冊中2冊しか扱われておらず、しかもほとんどがコラムや注で小さく扱われているだけだ。「権力監視」は1994年度「現代社会」の教科書でもあまり扱われてはいない。
マスメディアをめぐる教科書のプロット
1994年度の教科書から変化したのは、マスメディア報道をめぐる視座と世論形成の扱いである。では、世論形成において、マスメディアはどう扱われているだろうか。すべての教科書が、まず、マスメディアの影響力を指摘する。そして巨大な影響力を持つマスメディアが、「営利主義」や意図的/非意図的な「誇張・省略・歪曲」「センセーショナリズム」や「メディア・スクラム」といった批判を受けてきたことを示し、そうした「情報操作」「世論操作」に対抗するためにメディアリテラシーが必要と締めくくるのが、多くの教科書に共通するプロットである。
1994年度の教科書にも似た説明があるが、2点で異なる。例えば「マスメディアは情報を広く国民に伝えるだけでなく、国民に積極的にはたらきかけて、世論を方向づけるリーダー的な役割」など、肯定的役割も説明される。2点目に、「世論操作」の主体である。1994年度では、第二次世界大戦の反省を踏まえてか、「権力によって」マスメディアが操作されることへの警戒が目立つ。そして対処法として、メディアの「独立」と競争が必要と述べられるとともに報道機関には説明責任が求められている。
2024年度の教科書では、政党や圧力団体、政府によるメディア操作だけでなく、「情報の伝達を操作・誘導することができる立場にある新聞社や放送局などは、『世論による政治』と言われる今日において、大きな権力を持っている」など、メディアそのものが情報操作の主体として描かれることが少なくない。そしてその問題解決は、メディアリテラシーという個人の判断に委ねられている。
記述をめぐる課題 批判的思考の落とし穴
世論調査を批判的に見る記述も増加している。1994年度の「現代社会」では、その課題を指摘するのは11冊中2件だったが、「公共」では12冊中6件で操作性が指摘され、世論調査の質問や結果を分析するワークも多く設定されている。これらは、論理的・批判的思考を育む上で有用な体験的作業だが、マスメディアの編集によって「誇張・省略・歪曲」される可能性があるという説明を伴うことで、一つ間違えば、報道機関は公正ではなく、独自の視点や見解を持つという「主観性の確認」だけを結論とする作業になりかねない。
もう一点、気になるのは、1994年度も現在も、ほとんどの教科書で、報道の主体を「マスメディア」と記述している点である。「マスメディア」は、バラエティ番組やセンセーショナルなゴシップメディアも含む広い概念で、インターネットを含める教科書もある。こうした曖昧な用語で報道を捉えると、厳しい事実確認を経て正確な情報を出すべき報道の正確性が理解されない恐れもある。メディア環境の変容を踏まえ、教科書で使われる用語も、より厳密に定義、説明する必要があるだろう。
また「マスメディア」という巨大権力の構造的問題を批判し、情報操作への注意喚起を促すプロットは、もっともな批判ではあるが、「操作」という過激な語と結びつくことで、攻撃的批判やメディア不信、さらには陰謀論に引き込まれる危険性もある。報道やジャーナリズムが果たす肯定的役割もあわせて説明する必要があるのではないか。
持続可能な報道、そして民主主義のために
冒頭で述べたように、「ニュース砂漠」を民主主義の危機と捉えた取り組みが世界で始まっている。韓国では2004年に「地域新聞発展支援特別法」が制定され、韓国言論振興財団を通して、記者教育、デジタル化、購読料補助、メディアリテラシー教材の開発などが支援されている。英国では、公共放送BBCが資金を拠出し、地域メディアに記者を派遣する制度を開始。北欧諸国などでは、報道の自由と多様性を守るための報道助成金が存在する。大学も多様にジャーナリズムを維持し、改革を支援している。いずれも、制度的支援を通じて持続可能な報道環境を構築し、地域の民主主義を支えようとする試みだ。しかし日本ではまだ危機感が薄い。

<韓国・地域新聞発展支援特別法のもとで支援された各ローカルメディア監修の「メディアリテラシー」教材>
冒頭で、民主主義とジャーナリズムが両輪だと述べたが、日本の地域社会とメディアの持続可能性も同様だ。地域の新聞社や放送局は、マスメディアでありながら、教科書で批判されるセンセーショナリズムや情報操作の誘惑をさほど受けず、地道に報道を続けてきたはずだ。地域のメディア状況は決して安泰とは言えないが、地域のメディアが権力の行き過ぎを監視し、人びとの困りごとを問題化し、必要とされる情報を的確に伝えることで、地域社会の存続が可能になる。そして地域社会の繁栄がメディアの存続を可能にする。
報道をめぐる一般の理解が十分でない今、地域のメディアはその意義と責任をあらためて自覚し、遠慮せず、その重要性と矜持を人びとに示す必要がある。地域の学校や団体などとセミナーやキャンペーンでつながり、対話し、新たなデバイスや手法で多様な声を聞き取り、ともに未来を考えることで、地域の人びとと信頼関係を結び直していく取り組みを期待したい。
[i] 小川明子(2025)「教科書の中のジャーナリズム:中学・高校社会科教科書における「報道」をめぐる記述の現在」法政大学図書館司書課程『メディア情報リテラシー研究』第6巻1号, pp.73-90.