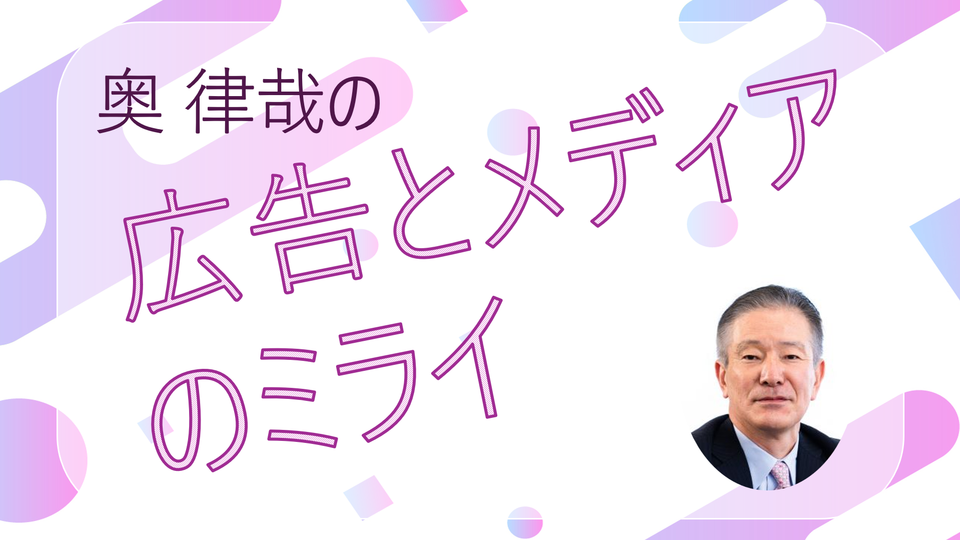電通、電通総研で長年にわたって広告業界・メディア業界を考え見つめてきた奥律哉さんの新連載です。大きな転換期にある広告・メディアの現在地を確認しながら、さまざまな角度から広告・メディアの未来を展望していただきます。(編集広報部)
連載にあたって
民放onlineに寄稿する機会を得た。連載するにあたり、初回はマクロなテレビビジネス環境を整理することから進めていきたい。将来を予測するにも、あるべき近未来を語るにも、現在地を理解することが第一歩であることは論を俟たない。登山に例えれば、行き先が明快であったとしても、現在地がわからなければ、地図もコンパス(羅針盤)も意味をなさない。中期経営計画やミッション・ビジョン・バリュー(MVV)からバックキャスティングすることがはやりであるが、そのアプローチにも現在地の確認は必須である。
2025年はNHKのラジオ放送が始まって100年という節目の年にあたる。放送100年という切りのいいタイミングで次の100年いや3年、5年をどうデザインしていくのか。中期の経営課題は、日本では放送業界に限らずあらゆる領域で共通である。特にテレビ放送とラジオ放送にとっては、近年インターネットの普及拡大による視聴環境の変化の波を大きく受けている。今までの100年の延長上に、「慣性の法則に従うような、自ら舵を切らない成り行き任せの未来像は存在しない」と認識している。だからこそ今一度、このタイミングで放送メディアのポジションを確認しておきたい。
2024年日本の広告費
25年2月に電通から発表された「2024年 日本の広告費」によると、2024年暦年の総広告費は、7兆6,730億円(前年比104.9%)で3年連続で過去最高を更新した。なかでもインターネット広告費は3兆6,517億円(前年比109.6%)となり、総広告費の伸びを牽引、マスコミ四媒体広告費は、2兆3,363億円(前年比100.9%)で3年ぶりに前年を超えたとされている。
日本の広告費は、マスコミ四媒体(新聞・雑誌・ラジオ・テレビ)、インターネット、プロモーションメディアの大きく3つに区分されている。近年成長が著しいインターネット広告費に注目すると、2019年にテレビメディア広告費を超え、2021年にはマスコミ四媒体広告費を上回ったことが記憶に新しい。
今回の発表では、総広告費に対するシェアについて、インターネット広告費(47.6%)がマス4媒体広告費(30.4%)を17.2%ポイントリードしたことが注目される。媒体別広告費にフォーカスすると、物販系ECプラットフォーム広告費と制作費を除いたインターネット広告媒体費は2兆9,611億円、テレビメディア広告費1兆7,605億円、ラジオ広告費1,162億円となっている。
日本の広告費は、その年の広告主のメディアニーズを表していると捉えることができる。特に無料広告モデルを主なビジネスドメインとしている地上波テレビやラジオは、その事業収入のほとんどを広告費で賄っている。その点においては、広告費の他に購読費(購読者が支払う金額)が一定の割合で存在する紙媒体(新聞や雑誌)とは事情が異なる。地上波テレビやラジオにとって、広告収入の減少は経営に与える影響が紙媒体より大きい。
総広告費を時系列データとして過去に遡って確認すると、名目国内総生産(名目GDP)との関係性が大きいことがわかる。過去のトレンドでは名目GDPの約1.1%~1.2%の規模がおおよその総広告費となる。しかし、近年ではその比率が上昇し2024年は1.26%となった。コロナ禍でさらに弾みがついた社会インフラとしてのインターネットの重要性と関係していることを感じさせる。日本の総広告費が景気動向とマクロに連動していることは、今後を展望するにあたって重要なファクトである。
映像視聴環境の変化 テレビとは何を指すのか?
インターネットの出現によって、万人が動画情報を簡単にやり取りできる環境が整った今日、あらためてテレビ視聴環境を俯瞰しておきたい。
テレビとは何を指すのか? 放送事業者、広告主、広告会社、総務省、出演者、生活者それぞれの立場でその捉え方は微妙に異なっている。テレビ受像機に加えて、PCやスマホ、CTV(コネクテッドテレビ)などでも映像視聴が可能であり、若年層を中心に広く浸透している。視聴シーンもリビングルームや居室に限らず屋外や移動中でも可能である。
以下の図に示す言葉の領域は、どの項目も右側が指し示す領域が広い。すべての項目で左側<右側、左側⊂右側となっている。この感覚は特に生活者視点に近い捉え方ともいえる。以下それぞれについて詳細を記す。

●テレビ番組⇒動画コンテンツ
放送局が放送する番組や映画館で上映される映画、それらのパッケージソフト以外に、YouTubeやTikTokでの共有を前提にした動画を、生活者がスマホを使って簡単に作成し発信/共有することができる。また最近ではタレント自身や事務所がオウンドメディアとしてサブスクリプションの動画サイトを運営するケースもある。広告主も戦略広報としてオウンドメディアでの発信に重点を置いている。これらの番組(コンテンツ)数はテレビ番組よりも明らかに数が多い。その意味でも動画コンテンツの一部がテレビ番組と捉えることができる。NHKプラス(10月1日以降はNHK ONE)やTVer、らじる★らじる、radikoなどは、一部の例外を除いて基本が放送同時配信やキャッチアップサービスであり、そのためコンテンツ数の増加には寄与しない。一方、Netflixなどの配信サービスは新規会員の加入促進を目的としてオリジナルコンテンツを常に制作・配信している。最近話題の日本におけるWBC独占配信もそれに該当する。
●放送局(免許)⇒プラットフォーム
地上波テレビや衛星放送は、放送免許・認定に基づいて特定の周波数を使って放送を行う。この放送免許・認定は5年ごとの更新が必要であり、新規参入のハードルを高くしている側面もある。一方、プラットフォームと呼ばれるサービスはインターネットを伝送路としてサービスを行うものであり、市場はオープンであり参入も撤退も事業者の意思で決まる。TVerやradikoに加えて、YouTubeやNetflix、Amazon Prime Videoなどの外資系プラットフォームが日本においても動画サービス市場を牽引している。
●テレビ受像機⇒CTV・チューナレステレビ・スマホ・PC
映像を見るデバイスに注目すると、従来のテレビ受像機(この場合はテレビチューナー内蔵を指す)を加えて、スマホの普及が著しい。またモニターとしてのチューナレステレビも安価で一定の需要がある。これに加えてさらに多くの課題(メリット・デメリット)を包含しているのがCTV(コネクテッドテレビ)の普及拡大である。従来のテレビ受像機もその7割近くがインターネット接続してネット動画サービスを見ることができる環境が整っている。主にリビングルームにあるメインテレビがそれに該当する。これらのテレビではテレビ放送(地上波・衛星放送)、録画した番組の再生、DVDやブルーレイ(Blu-ray)などのパッケージソフトの視聴に加えて、ネット動画サービスを楽しむ選択肢がある。
●放送(電波)⇒インターネット(配信)
電波による映像視聴にはメリットが多い。視聴者が特定の番組やチャンネルに集中しても放送波での受信は何ら影響を及ぼさない。しかし衛星放送の場合、台風や線状降水帯の発生による不安定な天候の場合、降雨減衰が発生して画面がフリーズし視聴できなくなるケースもある。一方ネット配信では、各家庭内には光回線などのブロードバンドネットワーク環境が整いつつあり、Wi-Fiによって家庭内のあらゆるデバイスがネット接続可能である。またひとたび屋外に出れば、5Gスペックのモバイル回線でネット接続が可能であり、行く先々ではそれぞれWi-Fi 環境が整備されていることが多い。つまり、人々はどこにいても、ネット回線とつながることができ、あらゆるインターネットサービスが自宅内外を問わず利用可能である。
通勤・通学での地下鉄利用や繁華街での地下街を例にあげれば、ネット接続は可能であるが、地デジワンセグを含む放送サービスの電波経由の視聴は困難である。このように整理すると、放送波よりもネット回線の方がユーザー利便性は高い。しかし、ネットの特定のサイトやコンテンツに視聴が集中した場合、輻輳状態となることは依然として課題である。放送波での受信は親局や中継局から自宅のアンテナまでは無線でも、各アンテナから自宅内F型コネクタ(Fコネ)までは同軸ケーブルによる宅内配線が必要であり、そのFコネにテレビ受像機をつながなければならない。ラスト10mが有線接続であることが視聴者の使い勝手を大きく制限している側面はある。
放送は「中身」と「仕組み」でできている~立場で異なるテレビへの想い~
このように整理すると、テレビビジネスは「中身」と「仕組み」でできていることをあらためて感じさせる。図表の「テレビ番組⇒動画コンテンツ」が中身であり、「放送局(免許)⇒プラットフォーム」「テレビ受像機⇒CTV・チューナレスTV・スマホ・PC」「放送(電波)⇒インターネット(配信)」が仕組みに該当する。
この状況のなかで最も厄介なのが、それぞれの立場で捉え方が異なることだろう。生活者にとっては、仕組みの話はほとんどスルーである。関心は、「見たいコンテンツ、見逃したコンテンツ、推しのコンテンツを見たいときに見たい」「どこで見られるのか?」「無料や課金か?」なのである。
一方、広告主や広告会社の立場からは、広告主のキャンペーン目的を達成できるメディアなのかどうかという視点である。リーチやターゲット、広告主別のKPIに基づく効率性が重視される。
放送事業者はグローバルなIP開発を掲げているが、制作現場は放送ファーストであり、編成タイムテーブル上のコア視聴率拡大をKPIとして試行錯誤している。コンテンツ軸を起点にウインドウ戦略を立て、中長期レンジでリクープする戦略にはまだ乗り切れていない。また、番組にかかわる権利は、放送と配信を明快に区別しており、その権利処理にはノウハウが必要である。
地上波デジタル(アナログ停波)が2011年7月24日(東日本大震災で岩手・宮城・福島3県は2012年に延期)に実施されてから14年が経過し、その間にメディア環境は激変した。いまや各家庭でのテレビ保有率は90%程度、若年層においては70%を切る(内閣府消費動向調査 2025年3月データ)。
「良いものをつくれば見てもらえる」は半分正しいが半分は間違いである。生活者の日常(普段使い)の中に溶け込んでいるかが、無料広告モデルのコアポテンシャルだと私は認識している。彼らの日常の視聴動線に存在しない番組(コンテンツ)が視聴される機会は極めて少ない。次回以降、さまざまなデータを紹介しながら、さらに読者の皆さまと現在地を共有していきたい。
※【奥律哉の「広告とメディアのミライ」】連載まとめはこちらから