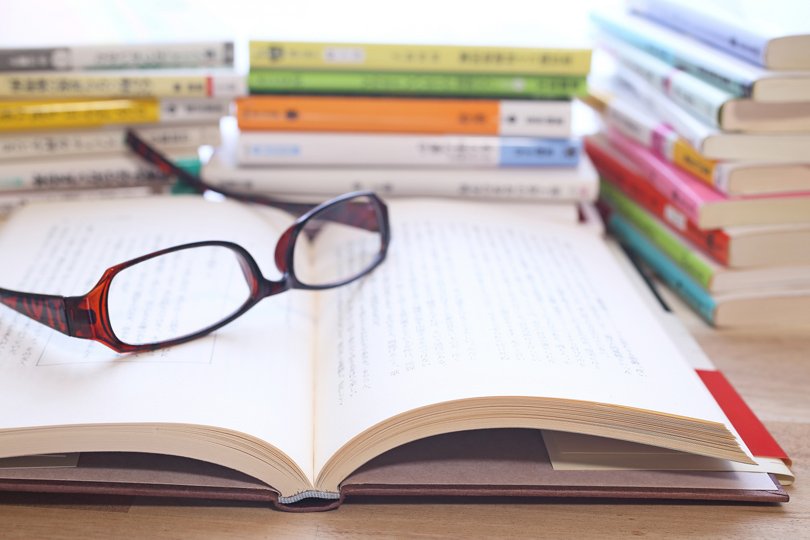放送やドキュメンタリー、ジャーナリズムにまつわる書籍が多数刊行された2021年。2回にわたりこれらを紹介する。今回は、報道現場の実態やジャーナリズムの根源を検討した9冊を取り上げる。
ドキュメンタリー、報道の実相
2020年で40回目を迎えた「地方の時代」映像祭。その歴史を振り返り、今後のあり方を深掘りするのは『地域発ドキュメンタリーが社会を変える 作り手と映像祭の挑戦』(ナカニシヤ出版)だ。編集は映像祭の市村元プロデューサーら。執筆陣には、民放から服部寿人(チューリップテレビ)、奥田雅治(毎日放送)、山下晴海(RSK山陽放送)、平良いずみ(沖縄テレビ)と歴代のコンクール受賞者のほか、NHKやケーブルテレビの制作者、さらに大石芳野、境真理子、森達也といった審査員経験者らが名を連ねる。地域の視点で普遍的な課題を取り上げ、時代を捉えてきた数々のドキュメンタリー。その制作の裏側や、映像祭が果たしてきた役割、さらに映像祭を支えてきた人々の熱意と努力を伝えるアンソロジーとなっている。
これまでハンセン病をテーマに9本のドキュメンタリーを制作してきた三重テレビ。01年のらい予防法違憲国家賠償請求訴訟の判決を機に取材にあたってきた小川秀幸・報道制作局長が、『虹のむこうには 為さん・大作さんの言葉 ハンセン病取材二十年の記録』(皓星社)を刊行した。岡山の長島にある2つの国立療養所を主な舞台に、元患者たちが受けた差別と苦難の歴史を丁寧に書き記した。また、長島への架橋運動や三重県による県出身者の里帰り事業、さらに三重テレビも主催に加わる療養所への訪問事業を振り返り、それらに携わった人々の思いやドラマをつづっている。終盤では、コロナ禍から見えるハンセン病への社会の向き合い方や、十分な報道ができなかったメディアの責任にも触れる。番組でナレーションを務めた俳優・常盤貴子さんの寄稿も収めた。
「オウム真理教」「アメリカ同時多発テロ」「東日本大震災」「井上陽水」「小澤征爾」「立花隆」......。時代と深く結びついた固有名詞が表紙に並ぶのは、金平茂紀『筑紫哲也『NEWS23』とその時代』(講談社)だ。TBSで長く報道に携わり、「NEWS23」編集長も務めた金平が、番組と筑紫を軸とした18章を講談社のPR誌『本』に連載。"23"への思い入れから5章を書き足して書籍化した。政治家、文化人らとのやりとりや、社内外のさまざまな人物の織り成す群像劇から、"自由でアナーキーで誠実な"テレビ報道の時代を活写。「オウムビデオ事件」の項では、筑紫の降板を議論する会議から除外された外部スタッフに重きを置いて回顧し、番組作りに命がけだったスタッフとのつながりを「家族のようなもの」と振り返っている。
瀬川至朗編著『民主主義は支えられることを求めている!「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」記念講座2021』(早稲田大学出版部)は、同賞の受賞者らを講師に招いて行う早稲田大の講座「ジャーナリズムの現在」の講義録だ。ジャーナリストがどのような視点・プロセスで報道や作品の制作に至ったかなど、講座で明らかにされた内容をまとめた。講師が受講者からの感想を踏まえて執筆したコラム「講義を終えて」も収録。民放からは、19年度に文化貢献部門奨励賞を受賞したTBSラジオ・鳥山穣とRKB毎日放送・神戸金史(「SCRATCH 差別と平成」)、20年度ファイナリストの沖縄テレビ・平良いずみ(「ちむぐりさ 菜の花の沖縄日記」)の講座を取り上げる。
『幻の村 哀史・満蒙開拓』(早稲田大学出版部)は、信越放送で数多くのドキュメンタリーを手掛けてきた手塚孝典が、国策として推進された満蒙開拓の語られなかった実態に迫った。村長として村人を満州に送り出し、戦後に自死した胡桃澤盛の残した日記。この日記との出会いが、悲劇として描かれがちだった満蒙開拓に加害の視点を突き付ける"取材の原点"となった。20年にわたる取材から生まれた、「公の歴史」に対する「民の歴史」を伝える一冊。
相次ぐTBSラジオ本
TBSラジオの開局70周年を記念し、『開局70周年記念 TBSラジオ公式読本』(リトルモア)が刊行された。「アシタノカレッジ」パーソナリティのライター・武田砂鉄による責任編集で、TBSラジオを代表するパーソナリティにロングインタビュー。それぞれの個性や番組、リスナーへの向き合い方を余すことなく伝えている。同局の元アナウンサーで、フリー転向後も同局の顔として活躍した久米宏の寄稿文も必読だ。1951年に東京初の民間放送局・ラジオ東京として開局以来、数々の長寿番組を通じてリスナーの生活の一部であり続けてきたTBSラジオ。往時の写真もふんだんに盛り込み、長く愛聴してきたリスナーが懐かしさを覚えるのはもちろん、シンプルな装丁と構成はラジオになじみのない人への入門書としても手に取りやすい。
そのTBSラジオの報道記者・澤田大樹初の著書が『ラジオ報道の現場から 声を上げる、声を届ける』(亜紀書房)。同局唯一の専業記者として幅広く取材活動を行う澤田が注目されたきっかけは、21年2月の森喜朗・東京五輪・パラリンピック組織委員会会長(当時)の女性蔑視発言。会見で本音の反応を引き出した澤田の当時の心境がリアルにつづられ、受け手を意識したラジオ記者ならではの視点がうかがえる。「ラジオは話し手が『個』としてリスナーに認識される」と記すとおり、澤田は福島出身者の目線で震災報道にあたるなど、常に「個」のパーソナルな視点とジャーナリストとしての客観性の双方を重んじた報道を心掛ける。本書は、記者が取材対象と受け手の間にどのように立つべきかを示してくれるだろう。
ジャーナリズムと研究
報道にまつわる研究書も紹介する。関谷直也による『災害情報 東日本大震災からの教訓』(東京大学出版会)は、東日本大震災を中心に、災害時の情報伝達や人々の心理、メディアの働きを多数の調査を踏まえて社会科学的に論じる。このうち災害報道をめぐっては、その意義を①ジャーナリズムを担う報道機関、②被害軽減を目指す防災機関、③災害を忘れずに啓発する役割――の3点に整理。被害の大きい地域への報道の過集中や、風評被害、人材育成などの観点で課題を指摘する。さらに災害と広告の関係についても検討。東日本大震災直後のCMに関するアンケートから人々の受け止めを概観し、「災害のたびに広告が機能しなくなっていては、長期的にメディアが衰退する」と述べている。
山田健太『ジャーナリズムの倫理』(勁草書房)は、ジャーナリズムの現場で直面するであろう数々の問題への処方箋を示すものだ。昨年6月刊行の姉妹本『法とジャーナリズム〈第4版〉』(同)と併せて活用することで、言論法における法と倫理の両面をより深く理解できるよう構成。ジャーナリズムの権力監視機能が弱まり、職業専門家としてのジャーナリストの存在が希薄化していると指摘される中で、ジャーナリズムが自ら守るべき姿勢を「真実性」「透明性」などの9章に分けて検証・検討する。見開きのレイアウトで左側に本文が続き、右側には本文に関連する事例や資料などを掲載。抽象的な議論になりがちな倫理の問題を具体的にイメージできる実用性ある内容となっている。
(一部を除き敬称略)