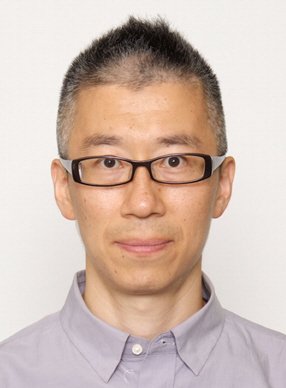新社屋へようこそ!
テレビ大阪は1982年3月1日の開局以降初めて社屋を移転し、2024年5月13日5時45分から新社屋より放送を開始しました(=画像㊦)。早いもので、あと1カ月半ほどで1年を迎えます。移転後まもなく全国の放送関係者が見学にお越しくださり、延べると週に一度は社内をご案内している状況です。
新社屋は放送局とホテル(ダブルツリーbyヒルトン大阪城)の両方の機能を持つ、地上21階、地下1階の複合ビルであり、屋上のヘリパッドから大阪城を見下ろす眺望を前に、見学者に歓声を上げていただくのが常となっています。
しかし見学者の主たる関心はフルIPで構築した放送設備が実稼働している状況を確認することにあります。その設備を構築するに至った経緯を中心にご紹介します。
<テレビ大阪新社屋外観>
英断だった放送システム全体のIP化
社屋移転の構想は2015年に立ち上がり、候補地の選定が行われていました。旧社屋の道を隔てた東側にある旧日本経済新聞大阪本社跡地へ移転することが決まり、社内で正式に新社屋計画がスタートしたのが2019年のことでした。当時は同じ敷地内に建設される新社屋がホテルとの複合ビルになるのか、単独ビルになるのかは決まっていませんでしたが、マスター設備の更新時期が近かった系列4局(テレビ北海道、テレビ大阪、テレビせとうち、TVQ九州放送)でIPマスターを採用することが決まっていました。
系列局の放送設備の仕様を共通化し、共同発注することで、導入コストの低廉化と放送運用の効率化、4K等の放送サービスの高度化への柔軟な対応を図るための試みでした。従来のSDIマスター仕様で更新するなら、更新の時期的に全国の放送局でも最後の放送局になる。一方、IPマスター仕様で更新すれば最初の放送局になる。どちらかを選ぶなら後者でいこうという判断もあったようです。
ただマスター設備以外も新社屋で全てIP化することについては、執行役員でもあった当時の技術局長も確信を持っていたわけではなく、社屋移転後の将来として、いずれ必ず全てIP化することになるという話をしていたころ、それなら新社屋で全てIP化しようではないかとの経営判断にまで至ったというのが、フルIP化の経緯になります。当時現場ではまだ首をかしげている状況でしたので、経営陣の決定に驚いたというのが本音になります。
IP化について経営陣にどのようにボトムアップしたのかとよく聞かれますが、当社の場合はトップダウンでした。情勢を判断してビジョンを打ち出した当時の経営陣の英断があっての現在ということになります。
IP化の特長とこれまでの使用環境の変化
「本当にフルIP化はうまくいくのか?」暗中模索の中、よすがとなったのは、共同でIPマスターの仕様検討を進める系列局でした。2019年3月から始まった系列間での共通仕様の打ち合わせは、コロナ禍で利用が進んだリモート会議の効用も手伝って、カットオーバーまで約100回に及び、密に情報共有を行いました。先行してIPネットワークの検討を進めていた系列局から得た知識を社内に展開、発展させることで、マスター(=冒頭画像/マスター監視室前景)に続く、回線・スタジオサブシステム(=画像㊦)の仕様検討につなげることができました。

<1サブ>
そうして実現に至ったフルIPの放送設備の特長は何といっても、従来のSDI規格による放送用信号の伝送が、Media Over IP(MoIP)と呼ばれる、放送用信号をIP化して伝送する仕組みに置き換わったことです。HD-SDI信号(1.5Gbps)を同軸ケーブル1本で伝送していたものが、例えば基幹IPネットワークで用いている100Gbpsの光ケーブル1本で60以上の放送用信号を伝送することができます。そのため旧設備に比べて使用するケーブルが半数に減り、マスターの機器を収めるラック(=画像㊦)の本数は約3分の2まで削減することができ、省スペース化を実現しました。
<マスターラック室(約152㎡)>
またIPマスターでは、番組・CM・速報CG等の放送素材を、要となる統合型ビデオサーバ(HD-IPO)へファイル転送し送出します。旧設備では、放送素材を取り扱う周辺機器それぞれにマスターへSDI信号を渡すための送出機がありましたが、それらが不要となりました。さらにIP化された放送信号は映像・音声・字幕などの補助データを受信する装置で組み合わせることができるため、旧設備で使用していた音声・補助データの重畳装置も不要となりました。
2カ所のスタジオサブを同じ構成とし、IP化された放送信号を同時に使用できるリソースシェアの機能を活かすことで、クロス運用が容易になりました。デイリーのニュースは1スタ(=画像㊦)を使用していますが、特番等で1スタを使用することになれば、ニュースを2スタや報道フロアにあるニュースセットに移動し、報道フロアに隣接する1サブのままで運用します。
旧社屋からスタジオサブの数を1つ減らした制約をIP化の特長を活かした柔軟な運用でカバーすることができています。マスターとスタジオサブが汎用のネットワーク機器で構築したIPネットワークで相互に接続されていることがフルIP化の最大の特長ですが、普段の運用ではあまり意識することはありません。
社内を行き交う放送用信号が最も混雑する大阪天満宮の「天神祭」の生中継での運用を念頭にIPネットワークを構築したため、同番組での初運用には緊張しましたが、問題なくスムーズに放送を終えることができました。

<スタジオ風景(使用機材)>
トラブル発生に備えたバックアップ体制
トラブル発生に備え、マスターは旧設備と同様、三重化構成にしています。またスタジオサブについても映像制作の主たる装置であるIPスイッチャーが故障した際は、マルチビューワーで使用するIPスイッチャーを緊急用のスイッチャーとして切り替えて運用を継続できるようにしています。マスターとスタジオサブを相互に接続するIPネットワークについても、2つのネットワーク面を備えた冗長設計としています。1つの面でトラブルが発生した際はシームレスに、もう一方の面に切り替わるようになっています。新しい設備で放送を開始してからトラブルがなかったとは言えませんが、IPに起因することはほとんど起こっていません。
いかに部署内外でIPについての知見を広めていくのかという悩みから始まった取り組みが、ようやく実を結びました。少しでも今後、IP化を検討される皆さまのご参考になれば幸いです。