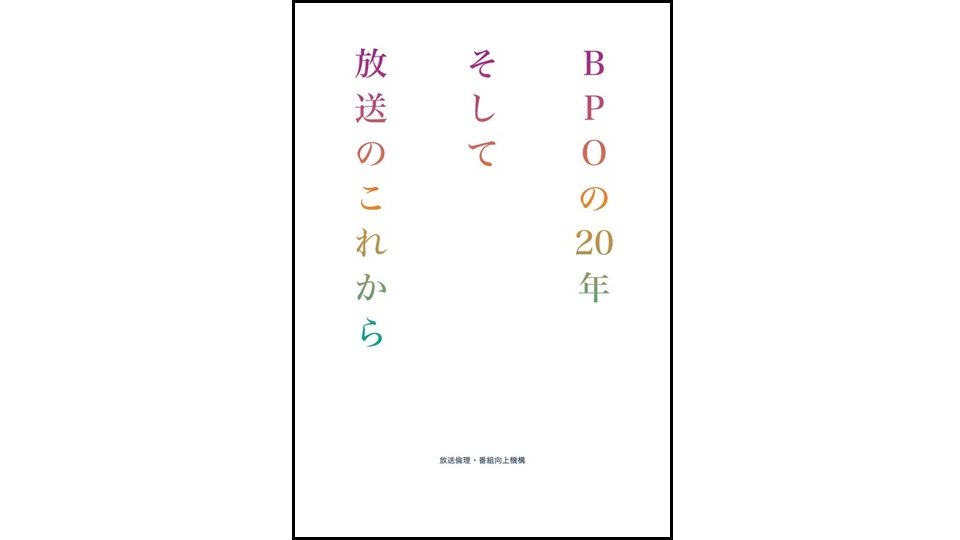設立から20年を迎えたBPO(放送倫理・番組向上機構)が去る3月、記念誌『BPOの20年 そして放送のこれから』を刊行した(BPOのウェブサイトにデータ版 を掲載)。さまざまな識者による寄稿や談話で構成されているが、ことBPOの存在意義に関する語りに着目するとき、同書のなかで繰り返し浮上してくる問題意識がある。すなわち、放送界が公的規制を受けず自律するための第三者機関として設けられたはずのBPOがしばしば、単に放送メディアを縛りつける存在として認識されてしまうという困難だ。
同書の巻頭対談で、BPO理事長の大日向雅美と意見を交わす前理事長の濱田純一が口にするのは、放送の自由と自律との間に明快な境界線はないこと、そして「自由と自律の間に常に緊張があって、ある意味ではお互いに育て合うという関係が維持」されることの重要性である。
ここでイメージされているのは、放送されたコンテンツの内容に対して"規制"する側がマルかバツかの固定的な診断を下すような構図ではない。日々生み出されるコンテンツが内包するメッセージや社会的な影響などについて、放送に携わる人々総体が自ら問い直し葛藤し続けるような、動的で終わりのない営為こそがここでは想定され、BPOはいわばそのいとなみを促す存在として位置づけられる。
しかし、大日向が言及するように、そうした意図は作り手に必ずしも伝わらず、BPOは作り手を締めつける「規制機関」「お白州」的な立場のように目されることも少なくない。大日向が具体的に挙げるのは、2022年にBPOの青少年委員会が公表した「痛みを伴うことを笑いの対象とするバラエティー」に関する見解が作り手にうまく伝わらず、「面白い番組をつまらなくしている」存在としてBPOが受け止められた例である。
同委員会が2022年4月に公表した文書では、作り手に対して何らかの禁止や規制を施そうとはしていない。同見解がバラエティー番組に対して特定の基準やルールを提示するものでないことを前提としてしっかり明記したうえで、発達心理学や脳科学の研究蓄積などを踏まえて対象番組の構造を分析、今後考慮に入れたほうがよい点を示す内容であった。
そこで行われるべきは、発信されたコンテンツが持ちうるあやうさを省みつつ、投じられた問いを取捨選択してフィードバックするプロセスであり、"作り手側対クレームをつける側"のような素朴な対立構図を設定することではない。その構図で捉えられた途端に、コンテンツを洗練させるための問いは、窮屈さをもたらす規制として解釈され、それらをいかにやり過ごすか、あるいは拒否するかという発想に結びついてしまう。それは意見・立場の相違や葛藤というよりも、ディスコミュニケーションに近いものになる。
理念が理解されないままコミュニケーション不調に陥る弊害は、同書に収録された映画監督・是枝裕和の語りからもみてとれる。
BPOの放送倫理検証委員会の委員もながらく務めた是枝は、政治的な案件を扱う番組の作り手が、賛成・反対各意見の秒数を同等にしたり、両論併記をしたりすることによって「政治的公平」を担保しようとする振る舞いにふれて、そうした対処が放送法の立法趣旨を踏まえずに「不偏不党」や「公平」といった文言を解釈し、思考停止したものであることを指摘する(この放送法をめぐる議論については、是枝や放送倫理検証委員会の初代委員長の川端和治弁護士らが著し、今年3月に緑風出版から刊行された『僕らはまだテレビをあきらめない』に詳しい)。
公権力に介入されないための盾としてある放送法の理念を咀嚼し、自らの立ち位置をみつめるようなプロセスが育まれるのではなく、コンテンツが「締めつけ」を受けないよう目先の防衛反応のみをしてみせる。是枝の指摘からみてとれるのは、そんな寂しさを感じさせる風景である。
発信されたコンテンツに対する反響を、過剰な「締めつけ」を行うものとのみ捉え 、素朴な対立構図を生んでしまう様子は今日、放送メディアとSNS上の反響との関わりにおいても、各所でうかがえる。例えば3月9日放送の『R-1グランプリ2024』(関西テレビ・フジテレビ系)に出場した芸人・吉住が披露したネタに対して生じた批判をめぐっても、類似の構図がみられた。吉住による、デモ活動を日常的に行う人物が交際相手の両親に挨拶にいく場面をモチーフにした当該のネタでは、交際相手への親密さと、示威活動を過度に楽しむような振る舞いとが同居したキャラクターが演じられ、そのエキセントリックさが上演の肝になっていた。吉住特有の人物造型と演技力が発揮された同ネタ は番組内でも高く評価された一方、視聴した人々からは、切実な意思をもってなされるデモや抗議活動を揶揄・冷笑するものではないかとする批判が少なからずなされた。そうした批判的な反応が"SNSで賛否"といったフレーズでまとめられニュース化していくと、今度はそれら批判の声を「何にでも過剰に反応する」ものと解釈して反発し、当のネタを擁護するリアクションもまた、同業である芸人などからも含めて多く発された。
さまざまなイシューに関するデモや抗議活動が、現実社会においてしばしば揶揄されたり偏見を向けられたりすることを踏まえるとき、当該のネタに向けられた問いや疑念は得心のいくものである。他方でその批判は、作り手を全否定するためにではなく、ベターな表現の模索に向けて有機的にフィードバックされるためにあり、"作り手側対クレームをつける側"といった単純な構図で決着させるべきものではない。行われた批判が、賛か否かといった二者択一の発想に回収されることは、相互理解がなされないままの分断、ディスコミュニケーションを呼び込んでしまう。本件に限らず、批判に至る理路を理解し踏まえたうえでなお、各人がどのような立場をとるかはそのつど多様であるはずだ。
もっとも、当該のネタを披露した吉住自身による振り返りは、その点において建設的な視点をみせていた。自身がパーソナリティを務めるインターネットラジオアプリ「GERA」内の番組『吉住の聞かん坊な煩悩ガール』3月23日配信回では『R-1グランプリ2024』に言及し、原型のネタを作った際に払った注意の仕方や、それを番組の規定時間に合わせて構成したことによる見え方や反省、またハレーション的な反響も含めたSNS上のさまざまな声への受け止めなどを、冷静かつ軽快に俯瞰しつつ率直に語った。その視野は、置かれた状況を的確に把握しながら、立場や意見の対立に落とし込むのでなく総括するものだった。
わかりやすい対立構図を前提にして分断や防衛に終始するのではなく、批判の意図を受け止めつつ省みて消化していくようなその語りは、批判というものが本来もつポジティブな機能も思い起こさせてくれる。賛か否かの単純な立場に落とし込まない吉住の振る舞いは、実践者自身による着地のあり方としてひとつの参考になる。放送メディアに対する種々の指摘が、単に「窮屈さ」として受容されることも少なくない現在であるだけに、「叩かれるかどうか」で思考を止めない姿勢がより大切にされればと思う。