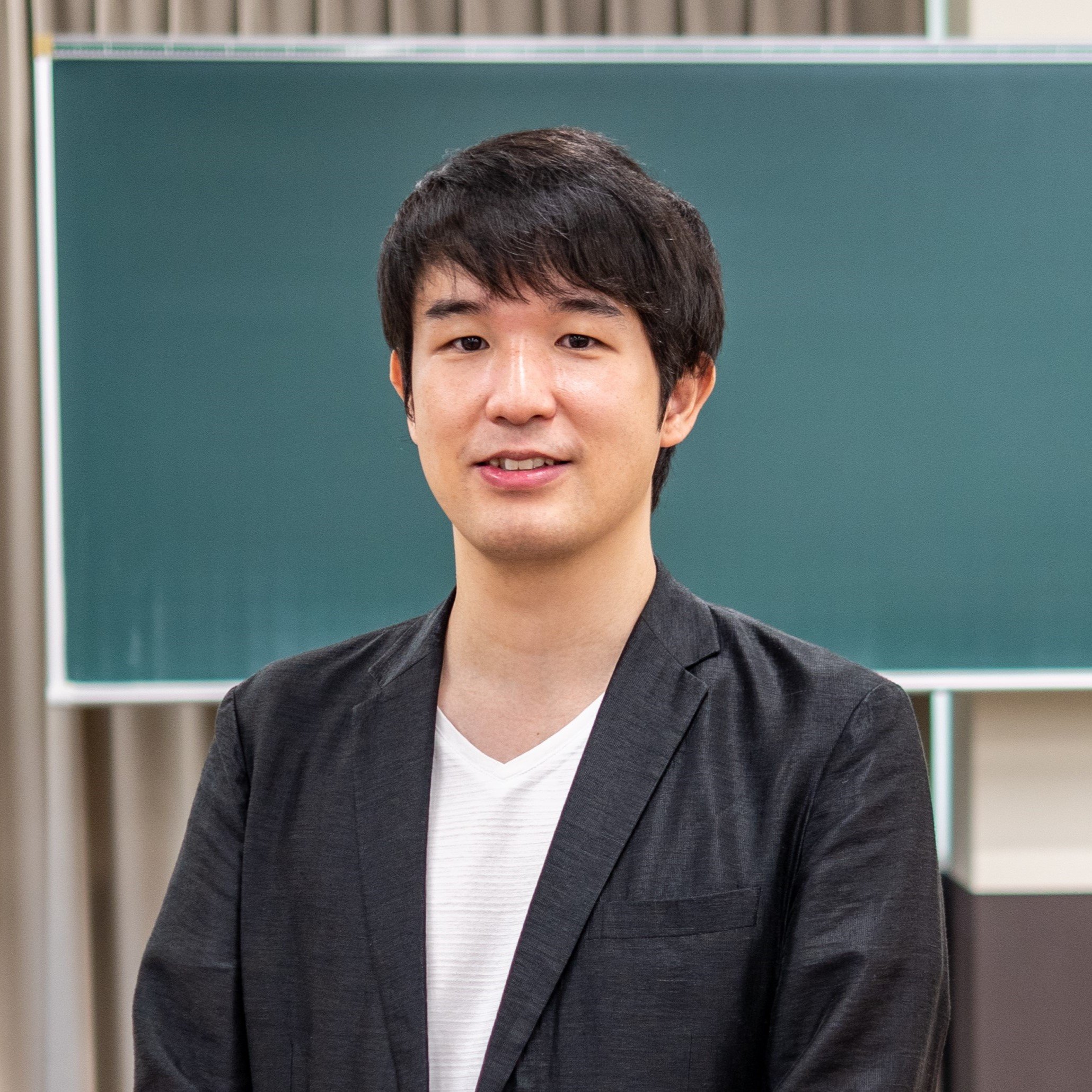テレビ放送が日本で産声を上げたのは1953年。2月1日にNHK、8月28日に日本テレビ放送網が本放送を開始しました。それから70年、カラー化やデジタル化などを経て、民放連加盟のテレビ局は地上127社、衛星13社の発展を遂げました。そこで、民放onlineは「テレビ70年」をさまざまな視点からシリーズで考えます。今回は、テレビメディアにとっての水先案内人である「テレビ論」について、メディア研究者の松山秀明さんに寄稿いただきました。
なぜいまテレビ論?
最近、『はじまりのテレビ』(人文書院)という本を書いた。初期テレビの約10年を論じたものである。「いまさらテレビの歴史を書いてどうするの?」と思われる方がいるかもしれない。テレビなんかオワコンで、SNSやフェイクニュース、生成AIについて書いたほうが目を引くし、みんな「メディアの未来」を知りたいに決まっている。書店ではそうした本であふれ、私も気になるから、ときどき手にとったりする。
でも、私がテレビの歴史を書こうと思ったのは、テレビ論やテレビ研究というものに、これからのメディアを語る「ヒント」が隠されていると信じているからである。これまでのテレビ研究の蓄積のなかに、学ぶべきものがたくさんあると思っているからである。つまり、メディアの「過去」から、「現在」や「未来」をまなざす視点が得られるのではないかと考えている。
ここには、現在の状況を語ること(現在を客観視すること)は、きわめて難しいという個人的な思いがある。たとえば金魚鉢のなかの金魚が、透明な鉢の縁を知ることができないように、現在のメディア状況を正確になぞることは、とても困難なことである。日進月歩で開発される生成AIは言うまでもなく、たった一人の経営者の気分によって容易に変わるプラットフォームの現在を論じることは、私の能力では到底できない。
メディアのいまを知るために
それでも透明な金魚鉢の縁に気づくためには――すなわち、現在のメディア状況を把握するためには――いくつかの方法論があると思っている。ひとつは「空間を変えること」。たとえば諸外国のメディア環境に触れ、それらと比較することで、自分を取り巻くメディア状況を知ることができる。他の国や地域のメディアはこうなのに、自分のところはこんな形をしていたんだと俯瞰することができる。
もうひとつは「時間を変えること」。未来に行ければ本当はいいが、それはいまのところできないから「過去」に行ってみる。すなわち、かつては違った鉢の姿を見ることで、現在のメディア状況を知ることができる。昔はこんな形をしていたのに、いまはこうなったんだと気づくことができる。そうしていまの金魚鉢の輪郭を理解する。
私は後者の立場をとり、時間を変えることで、メディアの現在や未来を語りたいと思っている。そうすると、必然的に「テレビ」というマスメディアの盛衰をとらえることが、一番有効な手段であることに気づく。かつてメディアの王者だったテレビとはいかなる歴史をたどってきたのか。いまのメディア状況は、テレビ文化のうえにどのように連なっているのか。YouTubeだって、Netflixだって、TikTokだって、日本ではすべてテレビ文化が築いた土台のうえに成り立っていると私は感じている。だから、いまこそテレビ論を講じ、テレビの歴史を知るときなのだ。そうすることで、いまのメディア状況を連続的に、俯瞰的に、そして客観的に眺めることができるのである。
大胆な問いを立てること
もちろん、これまで日本では多くのテレビ研究がされてきた。古くを見れば、東京大学新聞研究所(のちに社会情報研究所、現 東京大学大学院情報学環・学際情報学府)やNHK放送文化研究所、日本民間放送連盟放送研究所などの機関がテレビ文化を研究してきた。個人でも、後藤和彦、藤竹暁、志賀信夫、松田浩といった研究者たちがいる。けれど、これらのテレビ研究は、テレビ草創期から全盛期へと向かうときに書かれている。つまりテレビが文化の中心となっていくときに研究されたものが多く、高視聴率だったときに「テレビとは何か」を語ることは相当難しかっただろう――それはいま、生成AIを的確に論じることが難しいように――。やはり「テレビ離れ」と言われはじめ、テレビ文化が相対化できるようになったときに、その輪郭が見えてくるものである。
だからいま、ようやくテレビというメディアを見通せる地点にきたと思っている。事実、私の所属する日本メディア学会でもテレビ史に関する発表が徐々に増えてきた。ただ、それらの発表内容を見ていると、きわめて「小さな事象」を扱っていることが多い。ある特定の番組に注目するとか、ある地域に絞ってみるとか、視聴者だけを見るとか――。もしテレビの過去からメディアの現在をまなざそうとするならば、それだけでは足りないことは言うまでもない。もっと大きく「テレビとは何か」という大胆な問いを立てなければならない。これだけ巨大になったマスメディアの本質をとらえようという、一見無謀に思える意志をもたなければならない。そうしないとテレビからメディアの未来を見透かすことはできない。
テレビを見ずにテレビを論じる時代に
いまこそ巨視的なテレビ研究が立ちあがるときである。テレビの歴史を本格的に編むときである。いろいろな人が協力し、テレビの本質を議論するときである。しかし、悲しいことに、時代はテレビを見ずにテレビを論じる方向へと向かってしまっている。ほとんどの人がテレビを見ずに、安易にテレビを批判する世の中になってしまった。2024年に放送された宮藤官九郎脚本のテレビドラマ『不適切にもほどがある!』のなかで、膝を打つセリフがあった。第8話。SNSから波及していくテレビ批判の現在地である。
『朝ッパラTIME』という(架空の)番組に、不倫スキャンダルで閑職に追いやられていたアナウンサーが復帰したとき、テレビ局内ではたった2人のSNS投稿に怯えていた。主人公の小川市郎(阿部サダヲ)は言う。「なんだ、観たの2人だけ」。しかし、局員で娘の犬島渚(仲里依紗)は言いかえす。「この書き込みが『#朝ッパラTIME』で検索したであろうウェブライターの目に止まり、コタツ記事その1を書きます」/「この薄っぺらい記事をコピペした投稿がSNSで拡散され、それを抜粋してウェブライターがコタツ記事その2を書く」/「その記事のコメント欄『復帰、早くなぁい?』に共感した人が2万7千人」。市郎は言う。「見てないよねコイツら! 誰も!......ま、俺も見てないけど」。そして隣にいたリスクマネジメント部の栗田一也(山本耕史)が、こう締めくくる。「わかったでしょ、もはやテレビが向き合う相手は視聴者じゃない、観てない連中なんです」(宮藤官九郎,『不適切にもほどがある!』,KADOKAWA,2024より)。
いまやテレビが相手にしているのは「観てない連中」であるという、宮藤官九郎の鋭さに脱帽する。研究者以上に鋭敏に、しかもエンターテインメントに昇華していく彼の才能には嫉妬するばかりだが、私も、こうした風潮に抗っていきたいと思う。おそらくコタツ記事は根絶できないだろう。一日中、テレビを見張って仕事をするウェブライターを支えているのは、その記事をクリックする大衆だ。芸能スキャンダルや放送事故は、ページビューを稼げる。そのコタツ記事のコメントには、テレビという権威を攻撃したい人々が群がる。とりあえずマスコミ批判すれば、"いいね"がつく快楽が味わえるからだ。テレビは見ていなくても攻撃でき、インプレッションを稼げて承認欲求を満たしてくれる装置なのだ。「コンプライアンスで最近のテレビはつまらなくなった」と定型を語る者ほど、コンプライアンスの意味も分からず言葉だけをふりかざし、"いいね"が欲しくて批判する、テレビを見ないクレーマーだ。
テレビ中心の生態系をとらえる
こうした時代にあって、テレビ論はどうしていけばよいのだろうか。まずしなければならないのは、まだテレビは情報の「中心」であることを確認し、テレビ文化からメディアの全体像を把握しようと努めることだろう。依然としてテレビは「幹」としてあって、その情報がまるで胞子のように、ネット空間に飛び散り、それらをSNSが必死に拾いあって、騒いでいる。だからウェブライターたちはテレビを見ながら記事を書き、大衆はそれをクリックし、拡散するのだ。ゆえに、「テレビ離れ」イコール「テレビ無関心」ではない。次世代のテレビ論とは、こうした生態系をとらえ、ときに修正を促しながら、メディアを語る言説全体を豊かなほうに向かわせることだろう。そのために、まずきちんと学術的にテレビを論じることの意義を示さなければならない。
冒頭で述べたように、テレビ研究にはこれからのインターネットやSNS、AIを語るための「ヒント」に満ちている。日本のテレビ研究だけでなく、海外の研究にも射程を広げれば、もっと「ヒント」が見つかるだろう。これまでテレビがどういう視点で研究されてきたのか。これまでテレビがどういう歴史を歩んできたのか。テレビを含め、いまのメディア状況はどうなっているのか。その本質をつかむことができれば、メディアの未来を語るための指針を得ることができる。
だからテレビ局も視聴率が下がったと悲観ばかりしていないで、いまだにテレビは情報送出の「中心」にいるという自負とともに、よりよいメディアの未来を担っていくという覚悟をもつべきだ。たしかにコタツ記事の隆盛はリアルタイム視聴には直結せず、テレビ局の経営を苦しめている。しかし、そうした記事の氾濫は、テレビ局がまだ情報を生みだす力をもっていることの証左でもある。テレビ局はそれを自覚し、自身の歴史を学びなおしながら――ジャーナリズム精神やバラエティ番組の文化的価値も含め――、メディアの先頭を走ろうという意気込みを示すべきだ。そのとき、テレビ研究は、きっと未来を創るための強力な武器になるはずである。
【編集広報部注】冒頭ご紹介のあった著書は以下のとおりです。
はじまりのテレビ 戦後マスメディアの創造と知
松山 秀明 著 人文書院 2024年3月22日 5,500円(税込み)
四六判/550ページ ISBN:978-4-4092-4159-2