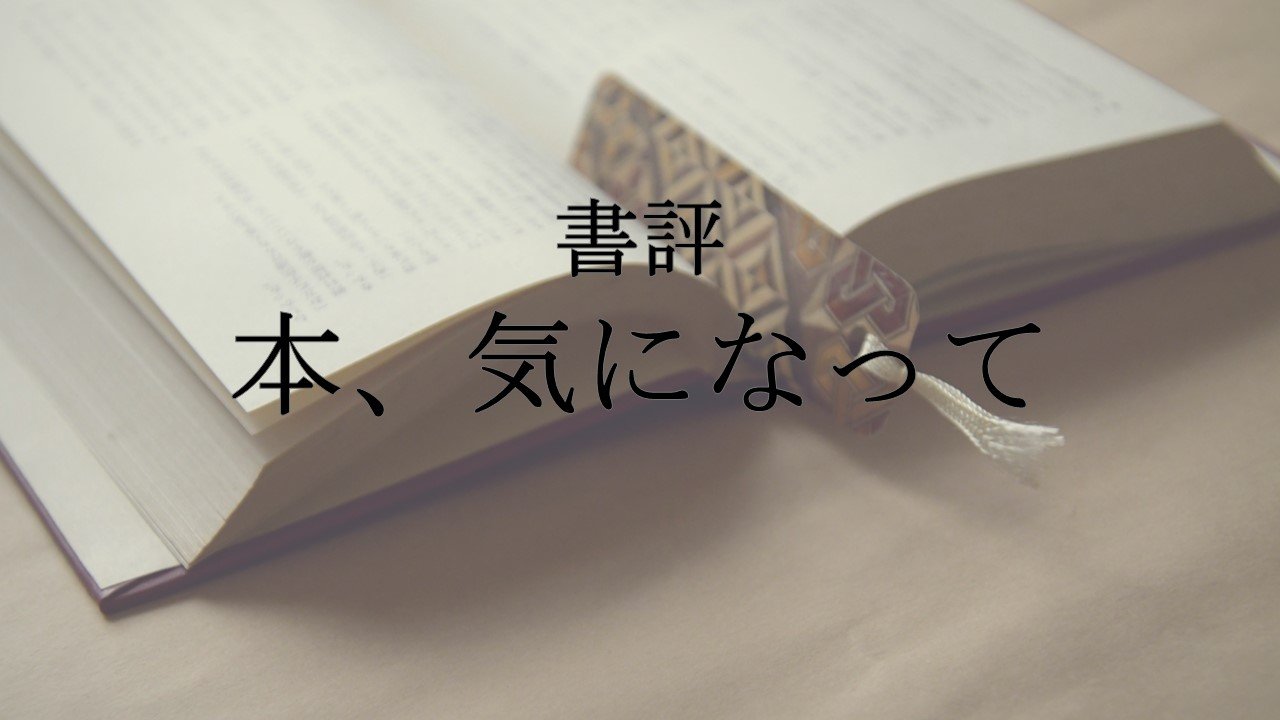気になる本=外岡秀俊という新聞記者がいた
及川智洋 著、田畑書店
激動する現代を、一陣の風のように駆け抜けた新聞記者がいました。朝日新聞の故・外岡秀俊さん(以下敬称略)。
外岡は1977年朝日新聞社入社。支局に配属された後、本社学芸部などを経て、ニューヨーク支局。帰国してAERA編集部、論説委員を兼務した後に2002年ヨーロッパ総局長。06年から東京本社編集局長=ゼネラルエディターに就任。1年半で退任する約束のとおり07年からは香港在住の編集委員へ。11年3月、北海道に住む両親が元気なうちに、そばにいる時間がほしいと考え、早期退社。ただ退社後も東日本大震災の被災地を訪ね歩き、支援物資を現地へ届けながら記事を書き続けます。その名文はつとに有名で、30代の頃からいつか外岡に「天声人語」を書かせようと、多くの人が考えていました。
本書は、2021年に心不全で急逝した外岡秀俊(享年68)が、34年間の記者生活を振り返りながら、年下の同僚だった及川智洋に語った記録です。取材は2015年11月から17年5月まで18回行われ、「検証のために自分だけでなく他の人からも聞いてほしい」という外岡の要望で、彼の同僚などへもインタビューがされています。外からの視点で外岡の誠実な人柄と、いかなる時も公正であろうとした立ち居振る舞いが、くっきりと浮かんできます。
私自身、外岡さんとは一度だけお会いしたことがあります。朝日新聞で彼の同僚だった隈元信一さん(当時、がんの闘病中だった)の本を、広く寄付を募って出版しようとしていた時期でした。早稲田ジャーナリズム大賞の表彰式会場で初めてご挨拶すると「石井さん? 石井彰さんですか。本来は私たちがやるべき仕事をしていただき、とても感謝しています」と、深々と頭を下げられた姿が忘れられません。外岡さんからは多額の寄付もいただいていました。
及川が面識のない先輩の外岡に、オーラル・ヒストリー(口述歴史)の記録=本書を作ろうと提案した理由がありました。2014年、朝日新聞は従軍慰安婦問題の検証報道と東京電力福島第一原発調査の報道に関連して、その対応を誤り他のメディアから激しく批判されます。また購読停止の申し出が殺到して幹部の辞任など、社内は大混乱していました。
「朝日の労働組合が、早期退社した外岡さんに依頼してこの問題に関する講演会を行った。(略)その講演録を後から読んで感銘を受け、個人的に面談をお願いして、ジャーナリズムに関する意見をうかがう機会を頂いた。何度かお話するうち、この人の経験と知見は細大漏らさず保存しておくべきだ、と思いつき、長期にわたる聞き書きをお願いした」
外岡は、東大在学中に小説『北帰行』で文藝賞を受賞して話題になっていました。ウォーターゲート事件を暴いた新聞記者を描く映画『大統領の陰謀』と、ロッキード事件の報道に影響を受け新聞記者を志します。朝日新聞の役員面接では早期退社を心配する役員に「当面、小説は書きません。社の仕事に専念します」と答えて入社、まず新潟支局へ配属されます。
外岡は当時をこう振り返っています。「とにかく私は新聞記事が下手だった。街ダネひとつ書くのにもうまくない。シャープじゃないんですよ。新聞記事はシャープでシンプルなものでなければならない。(略)新聞記事で独特の用字制限、用語制限も違和感が強くて、それに従って書くと自分の文章じゃないような気がしていた」といいます。
彼の認識が大きく変わるのは、6年後に東京学芸部で日曜版「世界名画の旅」の取材をしてからでした。取材班のキャップは「戦後の新聞の文体を作った」と言われた名物記者の疋田桂一郎。「疋田さんの文章は、新聞の文章じゃないんです。体言止めはしない。(略)普通の文章で新聞記事を書きなさいと言って、無味無臭の文章を理想としておられた」そうです。外岡にとって疋田は「文章も丸写しみたいにしたし、僕の生き方も疋田さん抜きには考えられない。何かを考えるときは、疋田さんだったらどう考えるか、と思い巡らします」という絶対的な手本でした。
やがて「新聞で美しくシンプルな文章を書けるということが分かった。(略)『クセがないけど個性がある』というのがいい文章。それを疋田さんに教えていただいた」と振り返ります。そして「疋田さんに教えられたことを伝えたい」と考えて、及川の提案を受け本書の語りを引き受けた、といいます。
本書に通底しているのは、外岡が一人の記者として優れていただけでなく、組織人としても希有な才能を発揮し続けたことです。新潟支局で一年先輩だった高橋和志は、編集局長時代の外岡を、こう語っています。「何といっても彼は怒らないし、人の悪口を言わない。とにかくデスクたちの話をよく聞きました。デスク会で丁寧に丁寧に話を聞いたうえで、明快に判断していた。一線の記者の話もよく聞こうとした。だから記者・デスクに信頼されました」
そして荒波がたびたび押し寄せても、外岡の信念は揺らぐことはありませんでした。外岡は編集局長時代を振り返り「僕の役割というのは、横、つまり編集局以外の販売とか広告とか、その盾になるということと、上からの圧力とかを止めること。その二つなんですよ、一番大事なことは。上から、横からの圧力に抵抗できない場合は辞めるしかない」また「普段、編集は社論を気にして報道する必要はない」とまで、編集会議で公言するほどでした。
外岡の考えは憲法についても明晰でした。朝日新聞では社会の右傾化もあって、現実主義=憲法九条を変えるべきではないか、集団的自衛権を容認する、という考えが広がっていきます。しかし外岡は「憲法九条は変えるべきじゃない」と一貫していました。「憲法とは自国に対する指針、戒めであると同時に他の国に対する約束だ。(略)変えるだけの必然性とか論理、つまり説得力をもってほかの国に論旨を展開しなければならない。それがなくて、ただ現実が乖離しているというだけで変えることはできない」と考えていたからです。それは朝日新聞の社会における立ち位置を自覚して、むしろ引き受けようとしていたからではないでしょうか。外岡は「朝日はいわばゴールキーパーの役割を持っていた。そこを開けちゃうと、シュートは素通りになってしまう」と、危惧していたからです。
じつは外岡が退社後の2014年、ある方面から「(朝日新聞社の)社長になってもらえないか」という話があったそうです。外岡は「あれだけ苦労して辞めたのに」ということで、断ります。もし外岡が社長になっていたらと、夢見る人も多いのではないでしょうか。外岡はこれからの新聞社の組織を「もっと緩やかな集団で、ゲリラ的に取材する記者たちをゆるやかに束ねるような形に組織が変わっていかないと」と構想していました。
本書は、外岡秀俊という類いまれな記者の個人史でありながら、それはまた崩れゆく朝日新聞のもう一つの社史でもあり、そして何より阪神・淡路大震災、9.11(アメリカ同時多発テロ)、湾岸戦争、イラク戦争、東日本大震災という激動の現代史と、その中で一人のジャーナリストが何を考えて、何を書き、難局でどのように振る舞ったかの、かけがえのない同時代史です。
どんな業種でも売り上げか減少すると、組織は内向きになり、無駄な組織改革と社員管理だけが強まっていきます。そんな時代に堂々と抗って、新聞記者の仕事をまっとうした外岡の記録は、読者にささやかな勇気と、多くの指針をきっともたらすでしょう。

外岡秀俊という新聞記者がいた
及川 智洋 著 田畑書店 2024年5月11日発売
四六判 上製 448ページ 定価 3,300円(税込)
CコードC0095 ISBN 978-4-8038-0436-2