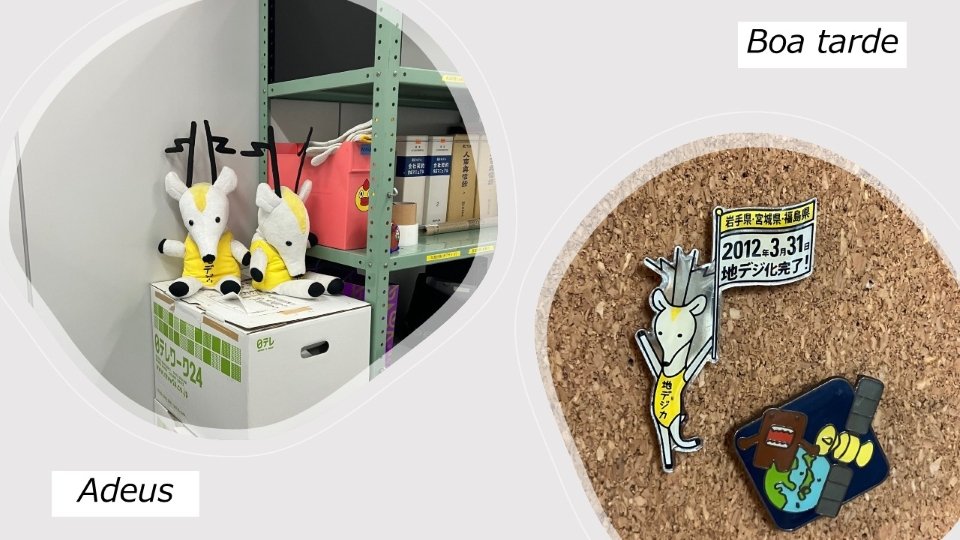2025年6月30日をもって「地上放送課」がなくなりました。
総務省が組織改編を行い、情報流通行政局の地上放送課(地上課)と衛星・地域放送課(衛地課)を廃止し、7月1日に「放送業務課」と「放送施設整備促進課」を新設したためです。
本稿「総務省の歩き方」①に、放送ジマの解説をさせていただいたので、「古い情報のままでは民放online読者のみなさまにご迷惑をおかけする」と考え、"上書き"する機会を頂戴しました。
<図1 総務省の組織改編で変わる課(2025年7月1日)>
これまで情報流通行政局のうち放送担当部局(「情流局の"放送ジマ"」)は、地上波、衛星、ケーブルテレビなどと「放送サービスの種類」で課や室が分かれていました。それぞれ映像・音声をとどける「伝送路」が異なっているためで、旧「有線テレビジョン放送法」のように法律も放送サービスの種類で分かれていた時代がありました。
しかし、法律は2011年までに放送法に一本化。また、この10年で地上波局も衛星局もコンテンツ配信に本格的に取り組むようになりました。そこで今回、総務省は組織を、許認可、放送インフラ整備、大規模災害対応といった「機能別」で仕切りなおしたわけです。新組織の「放送業務課」には、"地上課"と"衛地課"が持つ許認可や指導・監督権限が寄せられました。番組・マスメディア集中排除原則・外資規制・訂正放送にからむ放送法の運用、字幕・解説・手話放送の制度も移りました。
放送業務課は、「放送のソフト事業を俯瞰し、放送事業の発展を企画する」という目的が付されました。テレビ局にとりの最大注目点の「放送事業者におけるガバナンス確保に関する検討会」の他、4K8K推進なども担当するというので、かなり大きな課になります。
一方の放送施設整備促進課には、NHKと民放の間で進む中継局共同利用やブロードバンド代替、中継局関連の補助金やケーブルテレビの光化・2ルート化事業などが、"地上課""衛地課"から移管されます。また、2024年9月の奥能登豪雨などの教訓を活かし、大規模災害時に地上波中継局が倒れても、避難所などでBS・CSまたは通信でテレビ報道が見られるようにする取り組みが現在すすんでいますが、これも各課に跨っていた事項が、この課に集約されました。放送インフラ、すなわち「ハード」の担当ということになります。
<図2 各課の所管事項を水平に切り分け>
図2でも一目瞭然のとおり、ソフトとハードの上下分離。放送政策課のNHK関連事項も一部がソフト・ハードに分かれて移されました。
上下分離という言葉は、通信・放送融合などとともに、放送業界では禁句の時代が長かったといいます。竹中平蔵総務相の私的懇談会(「通信・放送の在り方に関する懇談会」、通称"竹中懇")から議論が始まり、2011年には放送法を改正。地上波テレビ局は上下分離が選択できるようになったものの、実例はわずか1例、現在は0です。
そして、安倍政権下の2018年、規制改革推進会議が上下分離をあらためて持ち出してきた時には、放送業界は「真意は別にある」と見て、かなりの警戒モードでした。それが今や、テレビ局自体が、自社系PF(プラットフォーム)やTVer、そして大手配信PF等々、「伝送路(ハード)を選ばずにソフトをお届けする」ことを大切にする時代になりました。
上下分離という言葉への警戒感・忌避感も薄らいだところでの組織改編、というふうにも見えます。
「放送外」「新領域」の担当部署も
<図3 新設された2室と所管事項>
一気に2つの課を新設する大改編ですが、目玉は実は「配信サービス事業室」です。放送業務課に置かれます。
テレビ局が動画配信への取り組みを加速化させているのに合わせるように、放送ジマも動画配信を所管する部署を設けたことになります。NHKのネット活用業務にからむ許認可・指導監督に加え、動画配信PFとの関係構築にも取り組む模様です。
配信サービス事業室は、総務省組織規則にも書き込まれた「省令室」。いずれは「課」になる可能性もありそうです。
もう1つ。放送政策課に「新事業領域創造推進室」が置かれました。ここは「放送」概念の見直し議論のほか、コンテンツ振興課が所管していたプロミネンス(顕著性確保ルール)や視聴データ活用、また、オリジネータープロファイルなど、放送と通信の境界領域にある政策・制度の検討を担当するといいます。「省令室」より軽い「訓令室」ではありますが、「いつでも機動的に法改正に入れるぞ」という意気込みを感じさせる組織立てです。
略称は施設課?、整備課?...
最初にご紹介した放送業務課と放送施設整備促進課。ずいぶん古めかしい名前だなと思いつつ、名前の由来を取材してみました。
まず、放送施設整備促進課は、2年前に総合通信基盤局にできた「基盤整備促進課」の放送版という理解がよさそうです。それぞれ、放送施設と電気通信網の「整備・維持に関する総合的政策の企画・立案・推進」が仕事であると総務省組織令で定めています。双子というか、2年違いのきょうだい。
<図4 所管事項がほとんど同じ>
基盤局のほうは略称「基盤課」だというので、放送ジマのほうは、どう呼ぶのか。
組織改編・人事異動の前日、6月30日に総務省をウロウロしていたら初代課長に出くわしたので訊いてみたところ......
「インフラ課、がいいと思います~」 これで決まりですね。
昔の名前...、ひと回りして新しい?
一方の放送業務課、その名前は由緒正しいもの(?)でした。情報流通行政局の前身である旧郵政省放送行政局でNHKと民放を監督していた「業務課」は1984年に誕生。1991年には、NHK担当の第一業務課と、民放担当の第二業務課に分離。そして4年後の1995年には後者が地上放送課となりました。41年ぶりに昔の名前に(ほぼ)戻ったわけです。
<図5 民放を担当する課の名称の変遷>
ある関係者は「内閣法制局に『放送事業課』という名前を提案したが却下された。『電気通信事業部』はあるのになあ」と少し悔しそうでした。省内では「地味? 役所の名前なんて、そんなものだよ」とか、「むしろ、新しくないですか」といった声も聞かれました。
1990年代は、世界でデジタル化の動きが起き、日、独、仏で衛星デジタル放送が開始。そんな時代ですので、第二業務課が「地上放送課」に衣替えした背景にもデジタル化の動きもあるように思えましたが、本稿締切までに詳しい事情を知る方にはたどりつけませんでした。
そこで、ここからは司馬遼太郎ばりの想像力を働かせます。
・郵政省「放送行政局」は、地上波・衛星波のデジタル化を推進する課を作ることにした。
・課の数は上限が決まっているので、NHK担当の第一業務課を「特定放送業務室」に格下げし、技術課の「デジタル放送技術開発室」を課に格上げ。
・"第一"がなくなったので、民放担当の"第二"をそのままにできず「地上放送課」にした、
......ということなのかもしれません、どうでしょう?(笑)
放送業界や受像機メーカーの慎重姿勢が働き、2000年頃に日本が打ち上げる予定の放送衛星は一度は「アナログのままでいい」と決まりました。しかし、国際事情に通じた技官らが必死に巻き返して、デジタル技術を載せることになった.....、そんな話も耳にしました。
当時を知る総務省元幹部は「放送行政局は長くやっている人が多く、業界にも強く言えないようだった。通信畑の中でも優秀とされる官僚が何人も放送行政局に投入された」と言います。
<図6 1990年代デジタル放送の動き>
その後、デジタル技術自体の急発展もあり、放送のデジタル化をめぐる議論は前進。国の財政支援スキームも見えてきて、地デジ化は2000年代の試験放送→本格放送への道筋がつきました。
デジタル放送技術開発課は発足から3年後、放送技術政策課に再び吸収され、なくなりました。その「ざぶとん」を使って、NHKを担当する「国際・特別地上放送課」が新設されましたが、同課も省庁再編までの2年半の命でした。
「寂しい」なんて言っていられない
地上放送課という名称がなくなること、さらに言えば、そのことがほとんど話題にならないことに一抹の寂しさを覚えて、この取材を始めましたが、1990年代には技術発展に合わせ組織改編が活発に起きていたことが分かりました。
省庁再編以降の放送ジマは、地域放送課を室にして、コンテンツ振興課を加えた以外、大きな変動はなく、このたびの、ほぼ四半世紀ぶりの組織改編は少し遅すぎた、とも言えそうです。
1990年代のデジタル化の時と同じように今回も、時代の要請・業界の変容に合わせて、放送ジマが姿を変えた。そのぐらいに受け止めるのが妥当と感じました。
総務官僚らを慌てさせるぐらいに、テレビ局はどんどん進化したいと思います。
なお本稿は個人的意見で、文責は私にあります。
※このほかの「総務省の歩き方」はこちらから