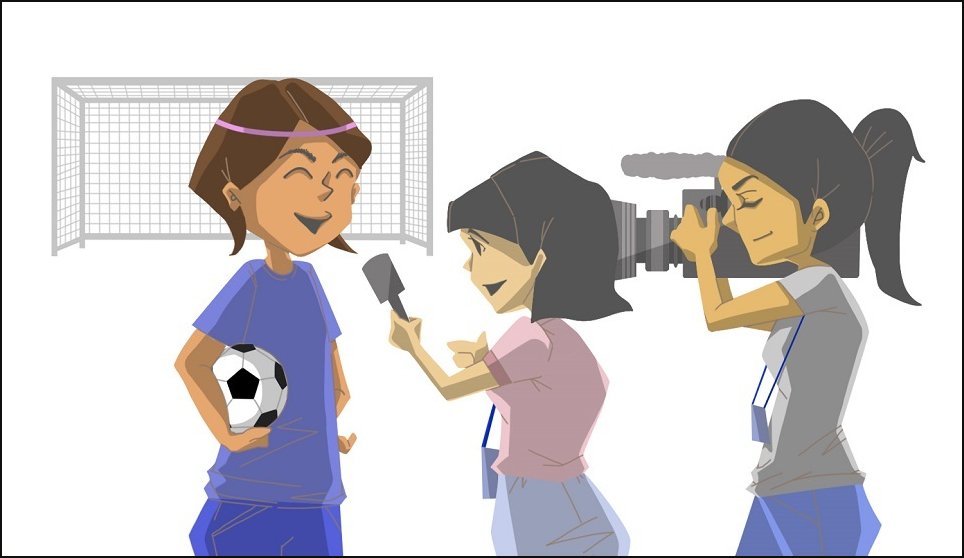米国の報道分野で、全国的に成長を見せている数少ない領域の一つがスポーツである。当然、求人も比較的多く、近年はスポーツ報道に特化した科目やカリキュラムを設ける大学が増えている。インターンシップも同様だ。しかし、勢いのある業界ゆえ、参入には厳しい競争が伴う。だからこそ、有望な学生を獲得・育成すべく、大学もスポーツ・ジャーナリズムに力を入れているわけだ。先行研究によれば、スポーツキャスターは一般ニュースの担当者よりも仕事への満足度が高く、「燃え尽き」(burnout)のリスクも低いと指摘されている。
そこで今回紹介するのは、若手を対象に、スポーツ担当の放送人のキャリア形成に大学教育とインターン経験がもたらす影響を調べた調査である。アメリカの2人の研究者による共著で『Journalism & Mass Communication Educator』(2021年夏号)に掲載されたものだ。調査では、経験5年以内のローカル放送局のスポーツ報道担当76人を対象に、58項目にわたるアンケートを実施した。その結果、総体的に、大学のスポーツ・ジャーナリズム教育とインターン経験は就職の手助けとなっており、かつ仕事への高い満足感につながっていることが分かった。
就職前の実務経験が有効
まず、半数(38人)が関連科目・コースを有する大学卒で、うち22人は経験が1~2年であり、専門的に学んだ者が業界に入るという最近の傾向を裏付けている。また、スポーツに特化した教育を受けていない者を含め、83%強が「大学生活と現職に関連性がある」と答えている。学外での体験的活動を提供・促進する大学も多く、実に90%がスポーツを伝える放送人としての資質が教育により高まったと考えている。大学で学んだことが仕事に直結しているわけである。インターンも同様で、ほぼ全員ともいえる94%が経験しており、約28%はインターン先に就職している。観客にプレゼントするTシャツをたたむ、アーカイブ用に過去の映像を整理する、スタッフの食事を調達するなど、報道と関係の薄い業務に不満を持つ者もいたが、総じて就職前の実務経験が有効だという知見が得られた。
また、仕事に対する認識では、82%強が大いに、14%強が中程度に「好き」、反対に「やや嫌い」はわずか1%(1人)で、満足度は極めて高い。自由回答では、後述する人員不足による長時間労働や給与水準などへの不満はあるものの、「5年以内に他業種に移る可能性がある」と答えたのは5人だけで、ほとんどがやりがいを十分に感じていることが分かった。
ストレスに耐え活躍目指す
ただし、彼らのような駆け出しの多くが、日常業務に多大なストレスを感じていることも判明した。スポーツ部門が2人以下という職場が77%強で、約66%が地域のイベントを十分に伝えきれていないと感じている。こなす業務も多岐にわたり、75%が自身でカメラを操作、88%強は生中継をすることがあり、75%がツイッター、さらに50%強がフェイスブックと局のウェブサイトを毎日複数回更新している。約70%は給与に不満を持ち、質問に答えた61人の平均年収は約2万9,400ドル(約338万円)。全体の約10%にあたる8人は副業を持ち、レストランや飲食宅配業で働く者までいた。仕事自体には充実感を覚えながらも、苦労も決して少なくないことが分かる。
この背景として、アメリカのスポーツ産業が桁違いに巨大であること、ゆえに放送においても担当者は花形で、かつ通常は地方の小規模な局からキャリアを開始し、経験を積みながら大きな活躍の場に移る、という事情がある。アルバイトをしながらでも多忙や薄給に耐えられるのは、それだけ将来に期待が持てるからだろう。
大学のありようも、日本とはかなり異なる。時流に沿った職業訓練に注力する米国に近づくべきか否か自体、大いに議論の余地はある。しかし、そもそもはるかに規模の小さい日本のジャーナリズム教育・研究界で、スポーツを意識した取り組みは極めて少ない。今後も世界で活躍する日本出身のアスリートが次々に現れ、国内でも多種多様な運動に興じる機会が増えるとすれば、それにかなう良質な報道人の育成と研究は、放送界、また大学にとっても今後の課題となろう。