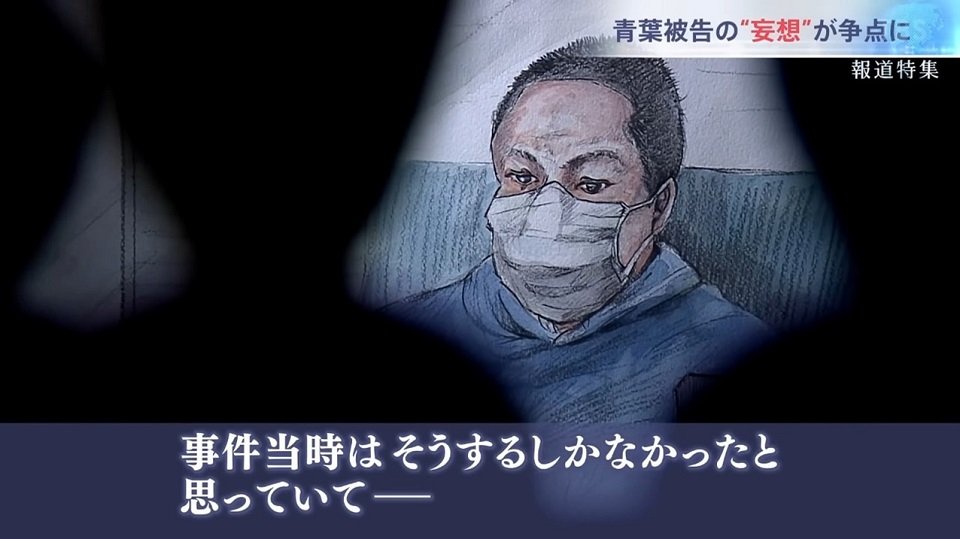民放連では、民間放送の価値を高め、それを内外に広く伝えることに力点を置いた「民間放送の価値を最大限に高め、社会に伝える施策」を策定し、2022-2023年度の2年間にわたり取り組んでいる。その具体的取り組みとして、報道委員会(委員長=大橋善光・読売テレビ放送社長)は、報道現場を熟知する担当者によるシリーズ企画「民放報道の現場から」を始めることとした。報道に関するトピックや実情などを、定期的に掲載する。
6回目は、毎日放送(MBS)の記者で、2019年に発生した「京都アニメーション放火殺人事件」を継続して取材してきた森亮介さんに、取材を通じて感じた報道の仕事の意義を寄稿していただいた。
社員36人が死亡、32人が重軽傷を負った京都アニメーション(京アニ)放火殺人事件は2019年7月18日に発生した。平成以降最悪となる36人の命を奪った青葉真司被告(控訴中)の凶行を、京都地裁は極刑をもって断罪した。143日間に及んだ長期審理をどう取材したのか報告する。
青葉被告の"妄想"の正体......取材で明らかになったこと
23年9月に始まった裁判。青葉真司被告が語ったその犯行動機は、不可解で身勝手ともとれるものだった。
(青葉被告の法廷での言葉)
「自分が書いた小説を京都アニメーションにパクられた。闇の人物ナンバーツーが京アニに盗作を指示した。事件当時はそうするしかなかったと思っていて、たくさんの人が亡くなるとは思っていなかった」

<搬送されるマスク姿の青葉被告>
青葉被告が抱き続けた「妄想」。裁判で争われたのは、犯行が「妄想」に支配されていたかどうか。つまり「刑事責任能力の有無や程度」だった。検察と弁護側とで、主張は真っ向から対立した。
青葉被告はなぜ事件を起こし、どのように「妄想」を抱くようになっていったのか。私は彼の半生をたどることにした。すると、その背景が見えてきた。
埼玉県さいたま市(旧浦和市)。青葉被告は45年前、この町で生まれた。9歳のころ、両親が離婚。父親に引き取られアパートで暮らしていた。体格がよい、活発な子どもだったが、家では父親から日常的に虐待を受けていたという。
地元の定時制高校に進学し、皆勤で卒業。しかし、20代は人間関係がうまくいかず仕事を転々とした。行き詰まる生活。そんな中、人生を大きく変える出会いがあった。
(青葉被告の法廷での言葉)
「京アニのアニメを見て『今時こんなすごいアニメはないだろう』と驚いた。文庫本を大人買いして、2日くらいで全部読んだ。なんとか自分でも書けないかと」
無職だった31歳のころ、京アニの代表作『涼宮ハルヒの憂鬱』の原作小説と出会ったのだ。
強い感銘を受け、小説家になることを志した。しかしその志が、のちに事件へとつながる「妄想」を生み出すことになる。
その一つが、実在する「京アニの女性監督」をめぐる妄想だった。インターネットの掲示板サイトで出会ったと勝手に思い込んだ。実際に青葉被告本人が一方的に書き込んだ、掲示板サイトへの投稿が残されている。
(実際の書き込み内容)
「異常なほどの色気」「ホレさせるだけホレさせて」
そして、全く接点もない「女性監督」への感情について、法廷では「恋愛感情だった」と述べた。しかし、妄想の世界で、2人の関係は徐々に悪化。やけになった青葉被告は12年、茨城県内のコンビニエンスストアでおよそ2万円を奪う強盗事件を起こし、逮捕された。京アニ事件を起こす7年前のことだった。懲役3年6カ月の実刑判決を受け、刑務所に収容された青葉被告。そこでも、新たな「妄想」と出会った。
( 青葉被告の法廷での言葉)
「『闇の人物ナンバー2』。ハリウッドやシリコンバレー、官僚レベルにも人脈がある。闇の世界に生きる、フィクサーみたいな人」
青葉被告は、「闇の人物ナンバー2」という架空の存在から監視されていると思い込むようになる。刑務所内では問題行動も目立った。それでも出所後、小説を完成させ、京アニ主催のコンクールに応募した。ところが、結果は落選。闇の人物が京アニに落選を指示し小説のアイデアが盗まれたとも主張した。落選の後、インターネットの掲示板に、「裏切り者やパクった連中は絶対に許さない」 と投稿していた。
そして19年7月。京都へと降り立った。訪れたのは事件の3日前だった。計画を練り上げるためだったという。

<台車を押す青葉被告>
京都アニメーションを下見し、犯行用具を購入。道を尋ねたり店員に話しかけたりするのは最小限に抑えた。「証拠を残したくない」という理由だった。ガソリンスタンドでは、給油目的を「発電機に使うため」と嘘もついたという。ところが犯行直前、スタジオの前に着いた青葉被告は、その場に座り込む。葛藤が突然こみ上げてきたからだと話した。
(青葉被告の法廷での言葉)
「ためらった。自分みたいな悪党でも小さな良心があった。ただこの10年間、働いて、やめさせられて、刑務所に入れられ、小説を送ったら叩き落されてパクリもあった。『光の階段』を登る京アニに比べ、自分の半生はあまりにも暗い。やはり、ここまできたら、やろうと」
逡巡した13分間。引き返す時間は十分あったはずだったが、計画は実行された。京都地裁は判決で、こうした行動について、以下のように判断した。
(京都地裁の判決の一部)
「青葉被告にはたしかに『妄想性障害』があり、犯行動機の形成には影響した。ただ、直前に逡巡していることからも、犯行を思いとどまる能力は多少低下していた疑いは残るものの、著しく低下していなかった」
法廷では、遺族らが自らの子と対面した際の想いなども語った。
(亡くなった社員(当時22)の母親)
「前歯の形で娘だとわかりました。『熱かったね』と頬ずりをして、キスをしました。『もう子どもじゃないんだから』と嫌がったと思いますが、許してくれたと思います」
一方で青葉被告は法廷で、謝罪はしたものの、持論を展開する場面も目立った。
(青葉被告の法廷での言葉)
「私の小説をパクったりしたことに、京アニは良心の呵責も何もなく、被害者という立場だけなんでしょうか?自分は罰を受けなければなりませんが、京アニが私にしたことは不問なのですか」
判決を不服として、青葉被告と弁護士は、それぞれが控訴。青葉被告と判決後に面会した遺族によると、青葉被告は「鑑定医には全て妄想で片付けられてしまったことについて話したい」と述べたという。
実名か匿名か......遺族それぞれの思いと選択
今回の裁判では、「被害者の匿名」が認められた。匿名での審理を希望した遺族と、実名での審理を希望した遺族、それぞれの思いも取材した。
匿名での審理が認められたのは、19人の遺族ら。通常、匿名審理は被害者保護の観点から性犯罪事件などが主に想定されているため、殺人事件では極めて異例な対応といえる。
一方、妻の寺脇(池田)晶子さん(当時44)を亡くした夫(51)は、迷わず実名での審理を選んだ。「妻が仕事を頑張っていたこと、母親としても頑張っていたことをみんなに知ってほしい」と語った。

<寺脇(池田)晶子さん>
匿名を選んだ被害者は、法廷では「1の2」「1の6」などと名前が番号に置き換えられるため、青葉被告にも名前が伝わることはない。匿名を選んだ遺族は、法廷でこう語った。
(『1の16』の犠牲者の父親 法廷での意見陳述)
「私は『1の16』の被害者の父です。この裁判で名前の秘匿許可をいただいたことについて、こうした選択肢を与えていただいたことを裁判所に感謝いたします。娘が先に人生を終えると思ったことはなく、娘が先立ったことで自分の生きる意味も大きく失われてしまった気持ちです」
同じく匿名を選んだ遺族は、私の取材に対してこう話した。
(息子が犠牲になった父親)
「息子の名前が裁判で数字で呼ばれることについてはなんとも思わない。それはわれわれが望んだことだから」
一方で「公開が原則」の法廷で被害者の匿名が認められたことに疑問を呈する声もあがった。ジャーナリストの江川紹子氏らは京都地裁に対して、安易に匿名措置としないことなどを求めて要望書を提出した。
(司法情報公開研究会 江川紹子代表)
「もちろん遺族の気持ちはとても大事にされなければいけないと思います。ただ被害者の方たちもそれぞれ人格を持って社会の中で仕事をされていた。この事件の被害者になったことがその方の名誉を損なうものでは全くありません。秘匿決定は、できるかぎり抑制的であるべきだし、厳格に考えるべきではないかと思います」
寺脇(池田)晶子さんの夫。裁判の最中、23年11月、実名審理を選択したことについてあらためて尋ねると、手紙で胸の内を明かしてくれた。
(寺脇(池田)晶子さんの夫の手紙より)
「亡くなった妻の裁判に、実名で向き合う。私たちはそんな覚悟を持って挑んだものの、ものすごくつらかったのも事実です。でもだからといって、実名審理をやめようとは思いません。私たちは向き合うと決めたから逃げない。そんな想いで今、裁判に臨んでいます」
事件から今年で5年。2審の裁判は今後、大阪高等裁判所で開かれることになる。
取材を通じて感じたこと
青葉被告の半生をたどった取材から見えてきたのは、私が取材前に想像していた「凶悪犯」としての素顔ではなく、むしろその真逆だった。明るく活発だったという少年時代のほか、埼玉県庁でアルバイトをしていた高校時代は人間関係も順調で皆勤で卒業もした。決して特別な人間ではなかったのだ。
しかし、徐々に歯車が狂い始め、自ら孤立を深めていき、凋落の一途をたどっていった。誰しもが青葉被告と同じような立場になり得る、とまでは思わない。
ただ、青葉被告が凶行に走っていくまでの長い人生の過程を見ていると、それを他人事には思えなかった。だからこそ、私は青葉被告のこうした半生を伝えることに意味があるとも思った。
放送後、そうしたメッセージを理解して受け止めてもらえた声もあった一方で、「加害者擁護の偏向報道」「こんな犯罪者を美化してどうするのか」などの意見も多く出た。さまざまな意見があって然るべきだ。ただ、反対意見を恐れて「加害者報道」を止めてはいけない。被疑者・被告がどういった人間で、なぜ事件を起こしたのか、同じようなことを繰り返させないためには社会がどう変わらないといけないのか。そうした投げかけや議論のきっかけを提供することが、私たちの仕事だとあらためて考えることができた。
また、実名・匿名取材では、報道の永遠のテーマでもあるだけに、なかなか自分なりの答えを見つけることができず、何度も立ち止まり、葛藤した。
ただひとつ、実名や顔出しでの報道によって世の中の仕組みや制度がより良い方向に変わった事例も多々ある以上、記者としてはできる限り丁寧に、取材対象に対して説明を尽くす努力は必要だと思う。
一方で、安直な意見かもしれないが、こうした殺人事件の遺族らが裁判に実名・匿名で臨む自由は、性犯罪などに限らず、より広く認められてもよいのではないかと思った。今回の取材を通じて、遺族の悲しみや無念さは、言うまでもなく、計り知れないものがあると感じたためだ。
裁判では、延べおよそ80人にも及ぶ遺族や負傷者らが、被告人質問・意見陳述・書面の読み上げによって胸の内を明かした。耳を塞ぎたくなるような悲痛な訴えに、傍聴席からは終始、すすり泣く声が聞かれた。「実名か匿名か」を迫られる局面での取材の際も、「報道の原理原則」が徐々に通用しなくなっている現代だからこそ、これまで以上に立ち止まって考えてみようと私は思う。