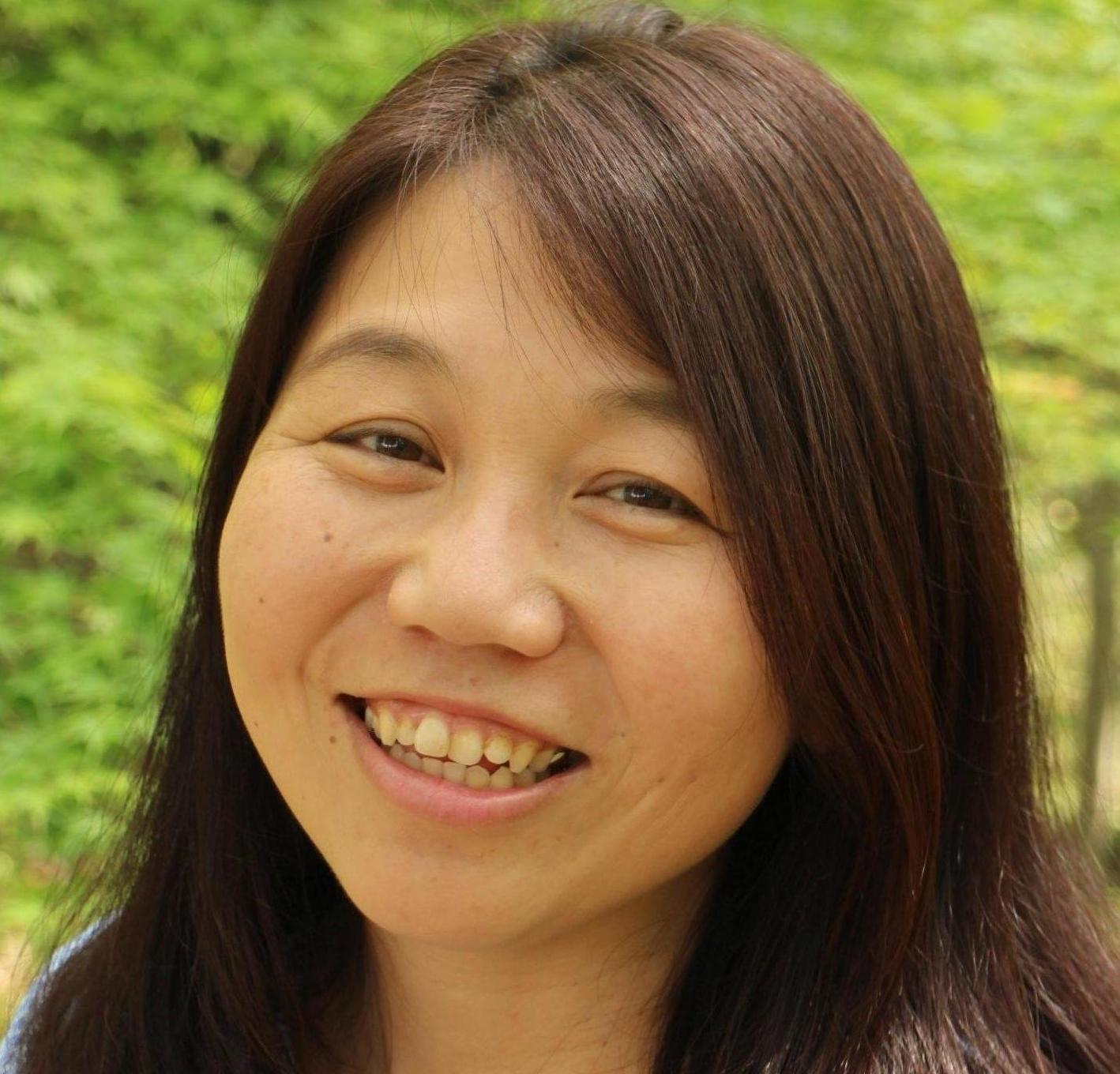ローカル局が「地域密着」「長期取材」による優れたドキュメンタリー番組を放送していることは知られていますが、その局以外の地域の視聴者が目にする機会が少ないという現状があり、ドキュメンタリー番組の存在や価値が社会に十分に伝わっていないという声も聞かれます。
そこで「民放online」では、ノンフィクションライターの城戸久枝さんにローカル局制作のドキュメンタリーを視聴いただき、「鑑賞記」として紹介しています(まとめページはこちら)。ドキュメンタリー番組を通して、多くの人たちに放送が果たしている大切な役割を知っていただくとともに、制作者へのエールとなればと考えます。(編集広報部)
『生ききる~俳優と妻の夜想曲』
北海道テレビ放送(テレビ朝日系列「テレメンタリー2025」で2025年2月22日放送)
人は残された時間がわずかだと知ったとき、何を選択し、どう生きるのか。そして、その時、家族はどうするのか。本作は、北海道で、がんの闘病をしながら舞台に立ち続ける演出家で俳優の斎藤歩さんと、同じく俳優の妻、西田薫さんが、病と向き合いながら生きていく日々を追った作品だ。
斎藤さんは、どこか達観したように言う。「死ぬまでどう生きるか。与えられた生みたいなものを生ききる」。薫さんは、そんな夫に寄り添いながら、どこか不安な表情を浮かべる。二人の関係は、家族であるとともに、同志のようでもある。
舞台人としての斎藤さんは厳しい。つらい体に鞭打って、自ら舞台に立ち続けている。だが自宅のリビングで夫婦の時間を過ごすときは、一転穏やかな表情を見せる。カメラの前だからか、あるいは俳優だからなのか。カメラ越しの夫婦の会話は、静かだ。
2024年12月、病状が悪化。医師によると残された時間は2、3カ月という。そのなかで、薫さんの東京での舞台が迫っていた。30年ぶりに復活した東京サンシャインボーイズ。かつて薫さんが所属していた劇団だ。稽古や公演のため4カ月は家を空けなければならない。二人の話し合いがこの作品のクライマックスだ。今の状況で斎藤さんを一人置いていけないと、舞台をあきらめようと考える薫さんに、斎藤さんはいう。「おれが病気になってから あんたが、これをあきらめるというならば、おれは、おれの残りの人生はかなりつらい」。最後の瞬間はそばにいられないかもしれないけれど......それでも妻の舞台を尊重したい。舞台人として、夫として斎藤さんは薫さんを思う。薫さんは妻として、さみしがりやの斎藤さんを心配する。そばにいたい気持ちと、そばにいてほしい気持ち。「しょうがないじゃん」「しょうがないけど......」。脚本ではない「生ききる」ことを決断した夫婦の優しくも強い思いが伝わってくる。
薫さんが東京に立つ朝。「じゃあね」とタクシーに乗ろうとする薫さんを抱き寄せる斎藤さん。「頑張ってね」「頑張る」。言葉は決して多くはない。だが、そこには、同じ舞台に生きる同志として、そして人生をともに生きる相棒としての覚悟があった。タクシーを見送る斎藤さんの後ろ姿で番組は終わる。
与えられた生をどう「生ききる」のか。人それぞれ違うだろう。生ききろうとする夫と、寄り添う妻。多くを語りすぎない、静かだが胸にくる良質なドキュメンタリーである。
『老いて、笑って~寄り添う人はそばにいる~』
北日本放送(日本テレビ系列「NNNドキュメント'25」で2025年2月9日放送)
私はライターをしながら、デイサービスでも勤務している。先日、近所で散歩する利用者の方とそのご家族に偶然会った。夫の後を追う家族は少し疲れているようだった。迷いながらも「こんにちは!」と声をかけてみる。彼女は一瞬怪訝な表情を見せたが、勤め先を伝えると、「あら、ご近所なの?」と表情をやわらげた。夫とどう向き合っていいのか悩まれている人だった。「歩けなくなったら困るからね」と少し元気になって去っていく彼女の後ろ姿を見送りながら思った。2025年、日本人の5人に1人が75歳以上となる時代に突入した。きっと同じ悩みを抱えている家族は多いだろう。
富山県射水市。介護施設の施設長をつとめる松浦佳紀さんは、介護職員で作る爆笑劇団を立ち上げた。きっかけは、「認知症の接し方がわからない」という家族からの問い合わせだった。認知症のおじいちゃんを演じて23年。おじいちゃんと家族の間で繰り広げるちょっとおかしな日常が、会場を笑いに包んでいく。
施設の利用者の方々に声をかけるときも、松浦さんは笑いを忘れない。そして松浦さんの声かけに、高齢者の笑顔が増えていく。おばあちゃん子だった松浦さん。介護職に就いたとき、早くに亡くした祖母と接するように声をかけた。食事の前に話をしながら笑わせることによって、それまで食事があまり食べられなかった方が、全部食べられるようになった。介護にも笑いが大切だと気付くきっかけとなった。
介護施設の利用者も家族も、抱えている事情はさまざまだ。「本当は私が最期まで見てあげるのが一番という心苦しい気持ちはあった」と話していた女性の家族は、施設で最期を迎えたとき「ばあちゃんは幸せだった」と安堵の表情を浮かべた。2024年1月1日に起こった能登半島地震で施設が被災し、居場所をなくした高齢者を松浦さんの施設は受け入れた。その中の一人が、能登島で暮らす水口ハマ子さん。ふるさとを離れて不安気な水口さんに、松浦さんはやさしく声をかける。「元気でおらんといけんね」。能登の施設が再開し、水口さんがふるさとに戻っていった。
「家族はどうしても昔と認知症になったギャップが受け入れられない。思い出がいっぱいある」と松浦さんは言う。認知症の家族の介護はつらい。一人で悩みを抱える家族も多いだろう。だからこそ、笑いに力が、寄り添う存在が必要なのだ。私たちは老いとどう向き合っていけばいいのか。この番組は、これからの超高齢化社会を正面から捉え、私たちが進むべき道へのヒントを与えてくれた。
『時給10円という現実~消えゆく農民~』
山形放送(第39回「民教協スペシャル」で2025年2月8~15日に全国の民教協加盟局で放送)
2024年の夏、店頭からコメが消えた。当たり前に食べていたコメが手に入らない......。「令和の米騒動」と呼ばれるこの事態で、コメがどれだけ大切なのかを思い知らされた。今、日本のコメ農家は激減している。「本当になくなっているんだから。いないんだから、農家が。これを政治家のみなさんには、知らなかったとは言わせないよ」。国会議員たちを前に、語気を強めるのは、ドキュメンタリーの主人公、山形のコメ農家、菅野芳秀さんだ。
コメ農家の跡取りとして生まれた菅野さんは、農業に未来を感じず、東京の大学に進学した。大学3年生のとき、成田空港建設に反対する三里塚闘争に加わり、逮捕された。独房で90日を過ごしたあと、一年遅れで大学を卒業、その後、ふるさとで就農した。妻、佐智子さんとの出会いは三里塚だ。食生活の変化で深刻なコメ余りから行われた減反政策に最後まで反対したが、集落のために受け入れた。農薬の空中散布がはじまると、集落に声をかけ、減農薬のコメを買ってもらうことを東京の生協と話をつけ、置賜(おきたま)地方全域での農薬空中散布を廃止することができた。海外との交流から思いつき、生ごみを堆肥として活用し、町の台所と田畑をつなぐ長井市のレインボープランをはじめた。農業を始めて半世紀。菅野さんの歩んできた道は、国、地方、そして農業に携わる人々の歴史そのものだ。
大学の客員教授となり、講義で学生たちに農家の現状を伝え、東京の高校生を農業体験で受け入れる。菅野さんの活動の根底には、子どもたちが生きる未来に大切なものを残したいという思いがあるように感じる。長年の過酷な農作業で体を壊し、今は農作業の中心は長男の春平さんが担っている。農作業に黙々と取り組む春平さんの姿が印象的だ。祖父の時代から一生懸命続けてきた田んぼを守りたい......だが「現状はもう不可能だというのが目の前にきている」と春平さんは言う。春平さんの静と、菅野さんの動。二人の対比は、農家の苦悩と怒りを表しているように感じる。
コメ農家の年間所得から経費を差し引いた農業所得は1万円。それを平均労働時間で割ると、時給は10円になる。衝撃的な数字である。「農家がコメをつくってくれるならば、農家の境遇なんか改善しなくていいと、そういう無関心が農家を時給10円の世界に放り込んで生活破綻させている」。菅野さんの叫びが苦しい。コメ農家がいなくなれば、日本のコメはなくなる。私たちは日本のコメを食べられなくなる。他人事ではない。この番組が突きつけた厳しい現実を直視し、これからを考えなければならない。