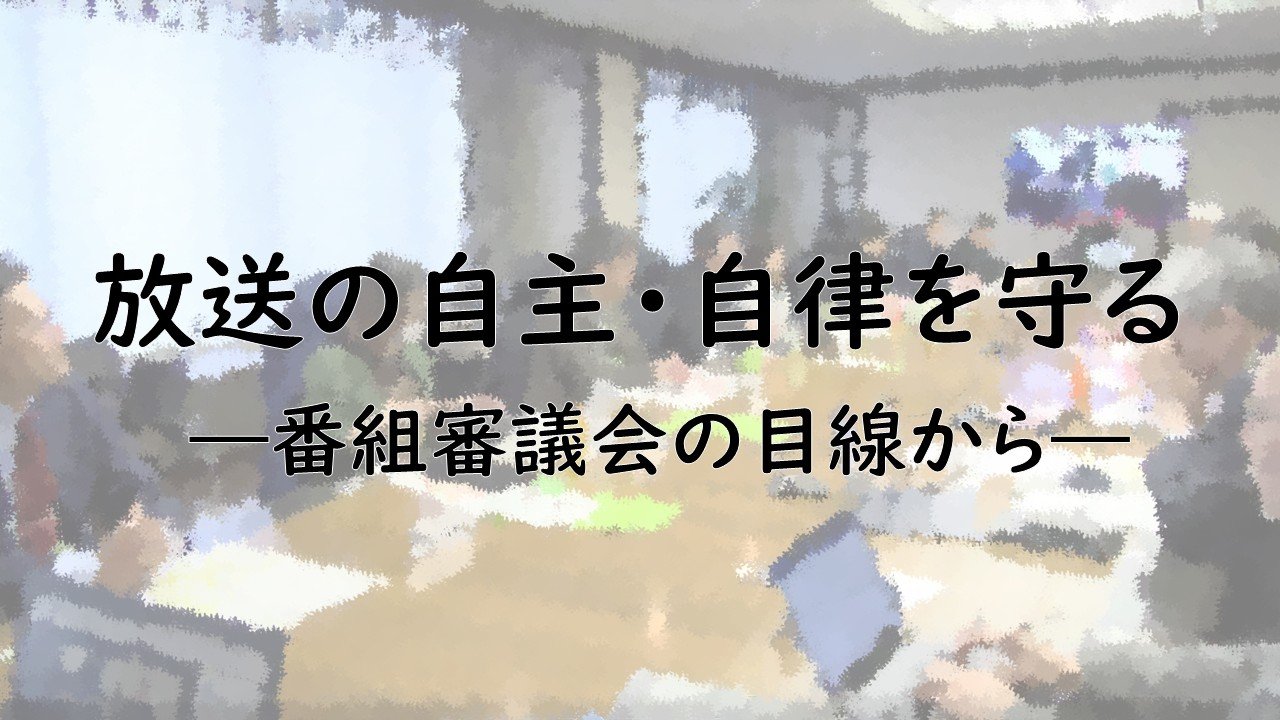各放送局のウェブサイトには必ず「番組審議会」というページが設けられており、年に複数回の審議が行われ、その審議概要が掲載されています。審議をしているのは、大学教授や弁護士、経営者、作家やタレントなどの複数の方で、各局の番組や、番組の適正に向けた多様なテーマなどに関して、さまざまな意見が述べられています。なぜ、こうした審議が放送局で行われているのか。その役割や意義は何なのか。各局の実際の番組審議会の様子なども紹介しながら、全7回のシリーズでご説明したいと思います(まとめページはこちら)。
今回はその第1回目として、法律上の位置づけなどを中心にご説明します。
放送法と「自主・自律」の精神
まず、テレビ・ラジオの放送には「放送法」という法律による規制があります。この法律の目的は次のように書かれています。
|
(目的) |
「第二号」ですが、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保する」となっています。
放送法は、全部で200条近い条文がありますが、それらの規定によって、「放送の不偏不党」と「真実」「自律」の3つを、法律が保障します、と宣言している部分です。
この中に「自律」という言葉があります。つまり放送局が"自分で自分を律する"というやり方を保障する、となっています。なぜ、自律を法律で保障するのか、という点について、ほぼ総務省の解釈だとされている『放送法逐条解説』(2020、情報通信振興会)という解説書では、次のとおり説明されています。
|
放送は言論媒体であり、放送についても憲法で定める基本的人権である言論の自由が保障されるべきであることは言うまでもない。しかし、この自由も絶対的なものではなく、その濫用が許容されず、その行使が一定の公共の福祉に適合すべき制約を有している。 |
放送法が制定されたのは1950(昭和25)年です。直前の第二次世界大戦の反省に立って、国に放送の内容に干渉させない、「放送は自主・自律でいくんだ」という強い気概を感じさせる内容です。
この精神は、例えば、放送法第5条で、「放送事業者は(略)放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない」と、放送局自らが番組基準を定め、それに従って編集をする(番組内容を決めていく)という条文となるなど、今回のテーマである「番組審議会」に関する条文にもつながっています。
番組審議会に関する放送法の規定
放送法第6条には、次のような規定があります。
|
(放送番組審議機関) |
まず、第1項で、放送事業者は、「放送番組の適正を図る」という目的のため、番組審議機関の設置を義務付けられています。これが通常、「番組審議会」と呼んでいる組織です。設置の主体は各放送局とされています。
次に、第2項に番組審議会の役割が書かれており、「放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議する」「放送事業者に対して意見を述べることができる」とされています。
そして、第6項で放送局は、番組審議会からの答申や意見を「放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努める」とされています。
ここで強調したいのは、放送番組の内容については、放送局が自ら作った番組審議会で適正化を図るという、まさに「自主・自律」の仕組みとなっていることです。
さらに、放送法第7条で「委員7人以上で構成」(ラジオ社は「5人以上で構成」)とされ、委員については「学識経験を有する者のうちから、当該放送事業者が委嘱する」との規定があり、放送局による「第三者機関」という位置づけとなっています。
欠くことができない組織
ここまでご説明してきましたとおり、番組審議会は法定の機関ではありますが、放送番組に対して放送事業者に直接、考えを述べることができ、放送の自主・自律的な取り組みを進めるうえで欠くことができない組織だといえます。
特に、いわゆる「番組問題」などが起こったときには、番組審議会に第三者の立場から、厳しい内容も含めて意見を出していただく。そして、それを放送事業者が受け止め、自主・自律で改善していくことにつなげる。
こうした対応をきちんとすることで、放送法の精神でもある「表現の自由」を守り、国による表現への介入をさせない、ということにもつながるものと考えています。
なお、民放連では、各局の番組審議会のウェブサイトに容易にアクセスできるよう、「番組審議会ポータルサイト」を開設しています。ぜひ、このポータルサイトから各局のウェブサイトへ、そして、その取り組みをご覧いただければと思います。
●民放連「番組審議会ポータルサイト」https://j-ba.or.jp/council/
次回の第2回は、外部の専門家から見た「番組審議会」を掲載する予定です。