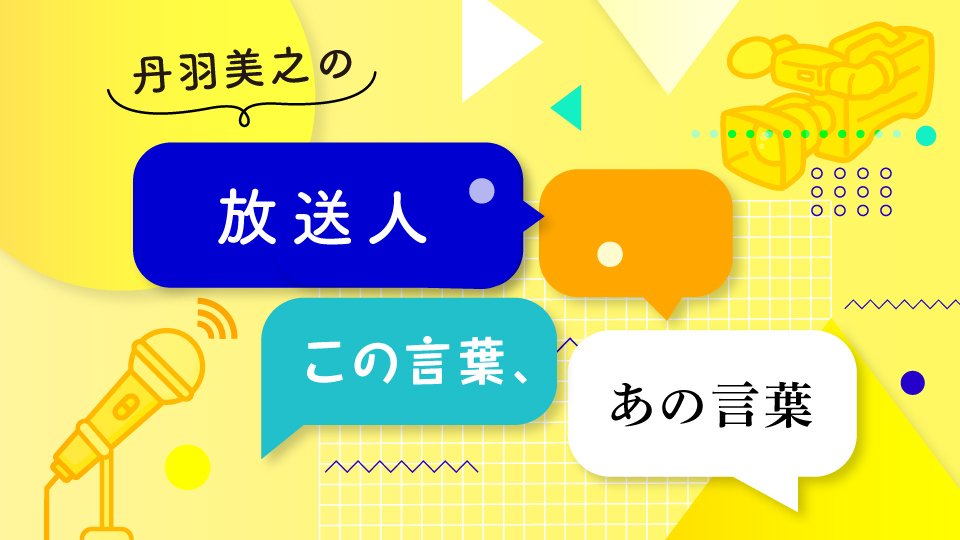面白い番組、優れた番組の背後には魅力的な作り手や演じ手がいます。その人たちが残した印象的な言葉は番組制作の極意を伝えるとともに、一種の演出論や映像論、社会論とも言えます。連載【放送人 この言葉、あの言葉】はこれら珠玉の言葉の数々を、東京大学でメディア論の教鞭を執る丹羽美之さんの視点で選んでいただき、毎回ひとつずつ紹介していきます。4回目は映画監督としてテレビ・ドキュメンタリーの分野でも多くの名作を残した大島渚さんの「この言葉」です。(編集広報部)
『愛のコリーダ』(1976)や『戦場のメリークリスマス』(1983)などで有名な映画監督の大島渚(1932~2013)は、テレビで数多くのドキュメンタリーを手がけたことで知られる。日本兵として戦った韓国籍の傷痍軍人を描いた『忘れられた皇軍』(1963)、ダム建設に反対する「蜂の巣城」の攻防を記録した『反骨の砦』(1964)、韓国の民主化デモで傷ついた少女を取材した『青春の碑』(1964)など、テレビ史に残る名作の数々を『ノンフィクション劇場』(1962~68、日本テレビ放送網)で発表した。

<映画『少年』(1969)撮影中の大島渚/ⓒ大島渚プロダクション>
大島をテレビの世界に引っ張り込んだのは日本テレビの名物プロデューサー・牛山純一(1930~97)である。民放ドキュメンタリーの草分けとされる『ノンフィクション劇場』を立ち上げた牛山は、「松竹ヌーベルバーグ」の旗手と謳われたこの新進気鋭の映画監督とコンビを組んで、テレビに新風を吹き込もうとした。大島にとってもそれは劇映画とは異なる新たな表現への挑戦だったに違いない。意気投合した2人は、その後も多くの仕事を共にした。大島は牛山との仕事について次のように回想している。
私たちのドキュメンタリーの主なテーマは「アジア」あるいは「アジアの戦争」です。これは、二人の人生のなかで共通して一番大きなものとしてありましたから、これに関するいいテーマを探し出すと、彼は私に依頼したんです。仕事に関しては、彼は全く口をはさまず、私がやりたいようにやらせてくれました。結果として、これらの仕事は、牛山さんのドキュメンタリーのある意味でのバックボーンをなすものになったと思います。¹
アーカイブ・ドキュメンタリー『大東亜戦争』
『大東亜戦争』(前・後編)は、そんな大島・牛山のコンビによる戦争関連のドキュメンタリーの中でも、ひときわ異彩を放つ存在だ。この番組は、「大東亜戦争」と呼ばれた先の大戦の顚末とメディアの嘘を、戦時中のニュース映画や記録映画のフィルムだけを再構成することによって浮かび上がらせる。「アーカイブ・ドキュメンタリー」の先駆けと言えるだろう。『ノンフィクション劇場』を引き継いだ『20世紀アワー』(1968~69、日本テレビ)で、1968年12月8日・15日の2週にわたって放送された。
番組は岸信介元首相の揮毫による「大東亜戦争」というタイトル文字に続いて、次のような説明書きから始まる。「このフィルムはすべて大東亜戦争当時撮影されたものである/言葉 音 音楽もすべて 当時 日本人によって録音されたものである/外国から購入したフィルムもすべて 当時の日本人の言葉でつづった/これは私たち日本人の体験としての大東亜戦争の記録である」。
大島がこだわったのは、戦争当時の記録をそのまま使うことだった。主な素材として用いられたのは、1940年に国策映画会社として設立された日本ニュース映画社(1941年に「日本映画社」に改組)による『日本ニュース』である。日本側の映像がないものは、連合軍側が撮影したフィルムを使用した。また映像だけでなく、音声についても、戦争当時のものを使うという徹底ぶりだった。戦時中のニュース映画の音をそのまま使い、音が不足している部分は、大本営発表と新聞の社説で補った。
この番組を観ていると、軍国主義の時代に舞い戻った気分になる。「大本営発表〜」という声が耳から離れなくなり、その響きに同調している自分に気づいてドキッとする。平凡なアーカイブ・ドキュメンタリーであれば、映像は過去のものを使ったとしても、それにつけるコメントは現在の立場から書かれることが多い。しかし、大島はあえて解説や反戦的なコメントを一切つけず、戦争当時の映像と音だけで番組全体を構成した。戦争プロパガンダの恐ろしさを身をもって感じさせること、それこそが大島の狙いだったのだろう。
戦争は常に勝者の側から記録される
『大東亜戦争』について、大島はその著書『体験的戦後映像論』の中で、もうひとつ重要な指摘をしている。
だが、今私が言おうとしているのはそのことではない。私が言いたかったのは、そんなふうに戦争の時点そのものに固執してフィルムをつくろうとした私にとって、材料になる記録フィルムの不足は致命的だったということである。ことに戦争の後半になると日本側のフィルムはほとんどなくなってしまうのである。戦争においては、勝っている時だけ映像を持つことができるのである。敗者は映像を持つことができない。²
戦争当時のフィルムだけで番組を作ろうとした大島を困らせたのは、戦況が悪化するにつれて、日本側が撮ったフィルムがどんどん少なくなっていくことだった。冷静に考えればわかることだが、そもそも死闘を繰り広げ、敗走する兵士や従軍カメラマンに、カメラを回す余裕などあるはずもない。仮に撮ったとしても、敗北の記録ではプロパガンダとしてほとんど役に立たない。戦争の後半になると、フィルムの不足もあっただろうが、日本側ではそもそも戦争を撮ろうとする意志が失われていったのだ。
実際、日米の形勢が逆転する岐路となった1942年6月のミッドウェー海戦以降、日本側のフィルムは極端に少なくなり、映像の迫力も失われていった、と大島は言う。逆に、戦況を優位に進めた連合軍側は、戦果をアピールする目的で克明な記録を大量に残した。サイパン島の崖から飛び降りて自決する日本人女性の姿は米国側によって撮影されたものだ。戦争末期の沖縄戦や、広島・長崎に落とされた原子爆弾の映像も米国側が撮影したフィルムしか残っていなかった。
戦争は常に勝者の側から記録される。敗者の側から見た歴史はなかったことにされる。これは戦争報道に必ずつきまとう問題である。もちろん、ここで言う「敗者」には、戦勝国か敗戦国かを問わず、戦争プロパガンダの犠牲となったあらゆる人々が含まれる。勝者はどんな目的でその映像を撮ったのか。そこには何が映され、何が映されていないのか。映像に残らなかった敗者たちの声にどう耳を澄ますのか。過去の戦争であれ、現代の戦争であれ、映像に残されたものだけを観ていては、戦争の真相は浮かび上がってこない。
戦後80年がたったが、世界ではいまも戦争や紛争が続いている。戦争プロパガンダは決して他人事ではない。かつてのフィルムの時代とは比べものにならないほど、映像は生活の隅々にまで入り込み、人々の感情に深く訴えかける。フェイクや真偽不明な映像の断片が瞬く間に世界を駆けめぐり、人々の認識を根底から塗り替えていく。勝者が作り出す饒舌な映像に抗って、敗者への想像力をいかに取り戻すことができるか。「敗者は映像を持たない」という大島の言葉は、今もそう問いかけているように思われる。

<映画『新宿泥棒日記』(1969)の撮影風景/ⓒ大島渚プロダクション>