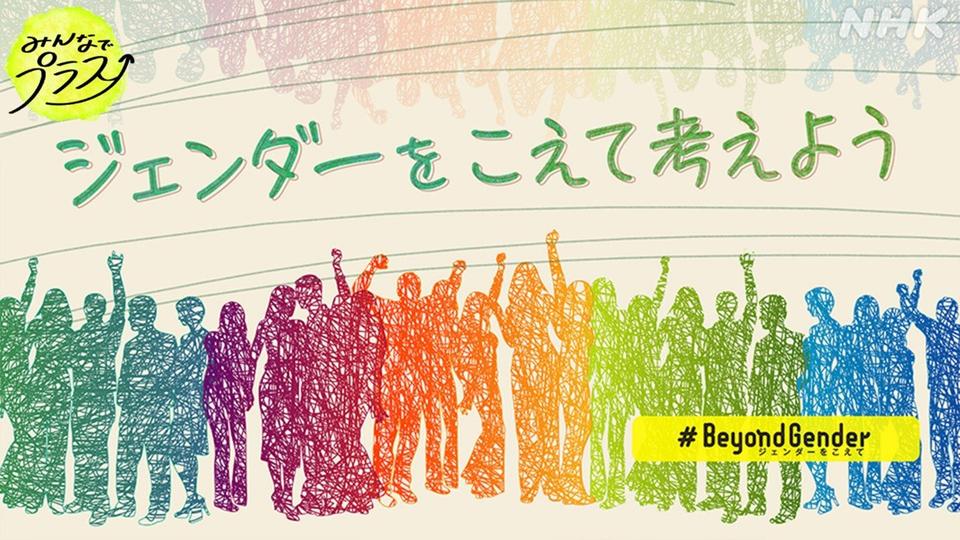民放onlineはあらためて「人権」を考えるシリーズを展開中です。憲法学、差別表現、映画界における対応、ビジネス上の課題、性的マイノリティへの対応、リスペクト・トレーニングなどを取り上げてきました。9回目は、NHKが2020年から継続して発信している「#BeyondGender」の取り組みと、その延長線上で実現した在京民放テレビ社との連携キャンペーンの成果を、NHKエンタープライズの原田由香里シニア・プロデューサーに執筆いただきました。なお、原田さんは今年10月のマスコミ倫理懇談会全国大会 の「ジェンダー発信」分科会でも報告されています。あわせて読みください。(編集広報部)
同じ"焦り"をもつ現場の連携が発端
性別に縛られず、誰もが"ありのままの自分"で生きられる社会になるように、ジェンダーについて考える情報を継続的に発信して、社会の意識と行動変容につなげる――。
この目標を掲げて2020年秋にスタートしたNHK「#BeyondGender ジェンダーをこえて」(以下「#BeyondGender」)プロジェクト。現在、『クローズアップ現代』『あさイチ』『ハートネットTV』をはじめ、報道から生活情報、福祉、ドラマまでさまざまなジャンルの25超の番組が連携し、ジェンダーの課題と解決の手がかりを年間通じて放送とインターネットで発信している。
プロジェクト発足前年の19年から、私はNHK報道局で『クローズアップ現代+』の企画・制作にあたっていた。性暴力の根絶をめざして被害者らが公共の場で声をあげる「フラワーデモ」が全国に広がり始めるなか、私たちが設けた意見投稿フォーム「性暴力を考える」には日々、被害者から独りきりで抱えてきた苦しみを吐露する声が届いた。
取材をとおして見えてきたのは、性暴力が誰もの身近で起き得る実態と、「あなたにも非がある」など周囲の心ない言葉によるセカンドレイプの根深さ。そして、その背景には社会の"ゆがんだジェンダー意識"があり、社会で性暴力は"ないこと"にされてきたことを痛感した。
この"社会"は"メディア"に置き換えられるのではないか......。強い焦燥感に駆られながら、私はディレクターや記者たちと、性暴力の実態を掘り下げる番組を数カ月おきに企画し放送した。
同じ頃、他の部局や番組の制作現場から、「ジェンダーがテーマの企画はタブー視されやすく、発信したくても発信しにくい」という話を聞いた。「それならば番組横断プロジェクトを組むことで発信しやすい環境をつくろう」と、仲間と手分けして20以上の部局の職員に呼びかけたところ、100人超から賛同を得た。その2カ月後、「#BeyondGender」は始動した。
プロジェクトでは毎年、「国際ガールズデー」「LGBTQカミングアウトデー」「国際男性デー」「女性に対する暴力撤廃の国際デー」が制定されている秋と、「国際女性デー」のある春に、集中発信キャンペーン(以下、一部を除き外部サイトに遷移します)を据えている。ジェンダー関連の番組本数は毎年約50本ずつ増えており、23年度は250本を超えた。関連サイトでは180本に上る放送連動記事を公開している。
番組や部局が連携することで企画を出しやすくなり、発信力も強化された。さらにプロジェクトを介して、ジェンダー問題に通じたプロデューサーが他部局から依頼を受けて番組や原稿を"複眼試写"するなど、コンテンツの改善にもつながっている。
組織の垣根をこえた連携と発信
21年の春、日本テレビ放送網(日本テレビ)の「ジェンダーチームプロジェクト」メンバーが、「#BeyondGender」について知りたいとNHKを訪ねてくださった。その時、日本テレビでも「ジェンダー問題について、もっと発信していくべき」と考える社員たちが自発的に取り組んでいることを知り、その場で思わず「一緒に発信しませんか」とお誘いした。
それから6人ほどでオンライン定例会を重ね、10月11日「国際ガールズデー」にあわせ、「これからの、テレビとジェンダー」と題してオンライン座談会を開催。視聴者の皆さんから寄せられた「テレビのジェンダー表現」をめぐる疑問や意見を紹介しながら、両局の制作者たちが感じている課題や改善の手がかりを話し合い、その模様をNHKはウェブ記事で、日本テレビはYouTubeで配信した。
組織をこえた連携を通じて、自分たちの取材・制作の視野が広がるだけでなく、自局の番組を視聴する習慣のない人たちにも大切な情報を届けることができると実感した。
翌22年には媒体をこえた連携の可能性を探るべく、当時、ジェンダーをテーマに積極的に発信していた雑誌『VOGUE JAPAN』(以下『VOGUE』)にも声をかけ、3月8日の「国際女性デー」にあわせ、生理・更年期について考えるリアル座談会を企画した。産婦人科医をゲストに迎え、視聴者の皆さんから寄せられた悩みや疑問に答えながら、NHKと日本テレビ両局のアナウンサーと『VOGUE』編集者が語り合い、その模様をNHKはEテレ『ハートネットTV』などの放送とウェブ記事に、日本テレビはYouTube配信に、『VOGUE』はウェブ記事に展開した。
日本テレビを通じて、その他の在京民放で同じ志をもつ記者やアナウンサーらともつながり、23年から毎年春の「国際女性デー」にあわせ、NHKと在京民放テレビ(日本テレビ、テレビ朝日、TBSテレビ、テレビ東京、フジテレビ、TOKYO MX)の計7局で女性の健康と生き方をめぐる情報を、「#自分のカラダだから」「#国際女性デー」などの共通ハッシュタグを付けてウェブ記事やSNSで発信している。共通ハッシュタグを付けることで情報は自由に局の垣根をこえ、そのテーマに関心のある人たちへ届く。
24年春には前述の7局のアナウンサーや記者が就活生にむけて、自分の就活や働き方について語る座談会をリアル開催。その模様をNHKが特集番組『あのころのわたしへ』で伝え、動画や記事も発信した。

<NHK総合テレビ『あのころのわたしへ』(2024年3月31日放送)>
今も25年春に向けて、7局の担当者がオンライン会議で隔週集まり、発信テーマや共通ハッシュタグの検討を重ねている。今後はさらに地域放送局やテレビ以外の媒体、自治体、教育機関などとの連携も広げていけたらと、みんなで考えている。
「声をあげやすい空間づくり」と
「声なき声と考える発信」をめざして
部局や組織をこえた連携を進めるなかで、私たちが大切にしているのは「声なき声」に耳を傾け、課題解決の手がかりを一緒に考えることだ。
「#BeyondGender」ではコンテンツへの感想や意見、悩みや思いを投稿できる専用ページを設けている。寄せられた声は制作現場と共有したり、特定のテーマで体験談や意見を募集したりして、次の企画につなげている。民放と合同で開催する座談会もすべて、投稿ページに寄せられた意見や疑問に答える形で登壇者が語り合う演出を貫いている。
放送連動記事ページに届いた意見も含め、これまでに視聴者の皆さんから寄せられた声は3,000件超。その一部は記事や関連番組で紹介している。投稿専用ページに届いた声の8割は10代から50代の現役世代。性別は女性が6割近く、男性が2割強、それ以外や無回答が2割弱(24年2月現在)。最近は男性からの声も目立つようになった。
投稿されたコメントはすべてプロジェクト窓口が事前に目をとおし、特定の個人・組織の誹謗中傷につながる表現や、真偽・根拠が不確かな情報がないかを確認する。誰もが安心して声をあげられる空間を整えることで、「独りきりで抱えてきた思いを誰かと共有したい」「声をあげてみよう」など意識変容につながればと考えている。
制作現場を叱咤激励するコメントもたくさん届く。「まずはテレビ局内のジェンダー意識を問い直すべき」「ジェンダー表現にもっと気をつけて」「自分と同じ悩みをもっている人がいると知って励みになった。これからももっと発信してほしい」など。こうした声は制作現場の意識喚起や行動変容に少なからずつながっている。
これからも部局・組織をこえて連携し、課題解決に向けて社会とメディアが共に考え、語り合えるきっかけと機運を作り出していきたい。