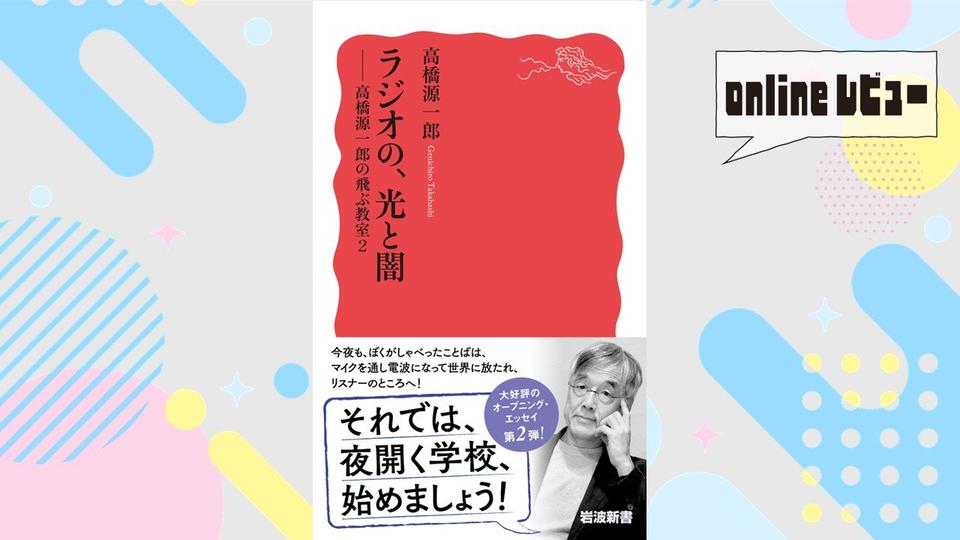「onlineレビュー」は編集担当が気になった新刊書籍や映画、ライブ、ステージなどをいち早く読者のみなさんに共有すべく、評者の選定にもこだわったシリーズ企画です。今回は、作家の高橋源一郎さんがNHKラジオ第1放送で5年以上続けている『高橋源一郎の飛ぶ教室』(金、21:05~21:55)のオープニング・エッセイをまとめた第2弾『ラジオの、光と闇――高橋源一郎の飛ぶ教室2』(岩波新書、2025年4月刊)を、同番組にご出演された経験もある作家の鈴木涼美さんに紹介いただきます。(編集広報部)
6年目に突入したNHKラジオ第1『高橋源一郎の飛ぶ教室』はいつも、「こんばんは。作家の高橋源一郎です」と始まる。その言葉に続く大体3分間くらいの高橋氏の独白形式の「はじまりのことば」が「それでは、夜開く学校、『飛ぶ教室』、始めましょう。」で締められると、今度は進行を務めるアナウンサーと会話しながら本について語ったりゲストを迎えたりするコーナーを進めていく。「本」と「人」から社会や生き方を考える同番組の、冒頭3分のオープニング・エッセイ。最初の2年分を集めた『髙橋源一郎の飛ぶ教室――はじまりのことば』(岩波新書、2022年11月刊)に続く2年分を集めた第2弾が本書だ。
最近観た舞台や映画の話、引っ越しのエピソード、SNSで話題になった海外ニュース、その日に取り上げる本に纏(まつ)わる逸話、飼っていた犬や子育てに関する記憶。年の暮れにはその年の訃報を振り返る。テーマは放送回によってさまざまで、馴染みのない固有名詞が出てくることもあれば、著者の人生を覗き見した気分になることもある。そして多くの場合、著者の声で読まれるのは、著者自身の言葉だけではなく、何か演劇の台詞や誰かが演説した内容、著者の記憶のなかで話している両親、もちろん小説や誰かの書いたもの、など、あらゆるところで書かれたり話されたりした言葉が引用される。それらは著者自身が心を動かされたり強烈に記憶に残っていたりする誰かの言葉だ。
特別好きだった話は是枝裕和監督の映画『怪物』(2023年)がカンヌ国際映画祭で脚本賞を受賞した際、坂元裕二氏が記者会見で話した「生活していて、見えないことがある」という言葉を引用して始まる。そこから著者の「見えなかったこと」に関する記憶が辿られる。軽度知的障がいの知人と出かけた先でのこと。トイレの場所を聞かれたので指をさして教えたのだが、その知人が戻って来る様子がない。心配になって見に行くと、「MEN」と「WOMEN」と書かれた扉の前で知人に「どちらが男用かわからないので、教えてくれる人が来るのを待っていたんだ」と小さな声で告げられる。
はっとした気づきはほかにもたくさんある。「詩が書けない」という著者の悩みから、詩人から小説家への転向はあっても、あまり逆はないことが指摘される。なぜ小説を書き続けるのか、なぜ詩が書けないのか、「できないことには、たいてい大切な秘密があるのです」。この話は放送で聴いた時のことも覚えていて、やはり詩が書けない、詩人に憧れはあるがなれる気がしない私はしばらく「秘密」について考えていた。
本になり、エッセイとして読んではっきりとした読み応えがあり、心に残る問いかけがあり、はっとする一文があるのだけれど、それでも雑誌に書かれた、あるいは本のために書き下ろされたエッセイとはどこか違うはずなのだ。これらはラジオに乗せて声として届けるために書かれたものである。
それぞれのエッセイには念を押すように冒頭の「こんばんは。作家の高橋源一郎です。」と末尾の「それでは、夜開く学校、『飛ぶ教室』、始めましょう。」が添えられている。それらの一文が目に入るたびに、エッセイが電波に乗って、声としてリスナーに届けられたものであることが思い起こされる。だがそもそも私たちにとって、言葉を声として聴くとはどんな経験と言えるのだろうか。
私の個人的な意見では、本を読むのとラジオで聴くのでは、受け取った私のなかで記憶される、そのされ方に大きな違いがある。本に書かれた一文は文字で、そしてそれを読んだ自分の心に響いたその響きが記憶される。文字を読む場合、多くの場合それは手書きではないので、文体に個性があっても記憶される文字に特徴があるわけではない。実際に、あの一文はサガンのものだったかデュラスのものだったか、みたいな記憶違いは私には結構ある。ラジオで聴いたものは、それを話していた人の声と記憶が切っても切り離せない。声のまま心のなかに残る。本で読むよりストレートな記憶のされ方なのだ。
幸いにも私はゲスト出演者として『飛ぶ教室』に何度か呼んでもらったことがあり、楽屋のラジオで、自分の出演時間を待ちながら聴いた「はじまりのことば」もいくつか覚えている。自宅のラジオで聴くのと同じように聴くのだが、それでもその直後には顔を突き合わせて話したからか、声はさらに輪郭を伴って記憶されている。いつも「はじまりのことば」の余韻のなかで、スタッフが急いで呼びに来るまで次のコーナーも聴き入ってしまうのだった。
多くの言葉が引用され、著者自身の言葉でも語られる全編をとおして、感じられるのは著者の持つ、言葉への圧倒的な期待と希望、そしてそれを持つからこそ自覚的にならざるをえない言葉の恐ろしいまでの力。それはまさに言葉を声にして放送することの、光と闇だ。序文でも触れられるルワンダの「千の丘ラジオ」は、最も恐ろしいラジオの力としてとある放送回でも話されたものだ。声として記憶されるラジオでの言葉は、本より時にストレートに人の心をかき乱し、問い返す暇なく彼らの何かをかき立てる。違う民族を虐殺したルワンダの民の手には実際に、民族対立を煽った放送がなされたラジオが握られていたのだから。
ちなみに、本書のために書き下ろされたであろう「ラジオの、光と闇――「まえがき」ではなく......」という序文は、ラジオで話された回と同じ、しかし表記が違う、「こんばんは。作家のタカハシゲンイチロウです。」で始まる。それが書かれたものであると念を押されるように。彼の作品に登場する「タカハシさん」という「現実の自分より自由でいい加減でフワフワしている」キャラクターについては本編でも話題になるが、カタカナの「タカハシさん」は書かれた文章でしか表しえない。書かれた本には書かれたなりの力と魅力があるものだ。
ラジオの、光と闇――高橋源一郎の飛ぶ教室2
高橋源一郎著 岩波新書 2025年4月18日発行 1,166円(税込)
文庫判/260ページ ISBN978-4-00-432062-3
このほかの【onlineレビュー】の記事はこちらから。