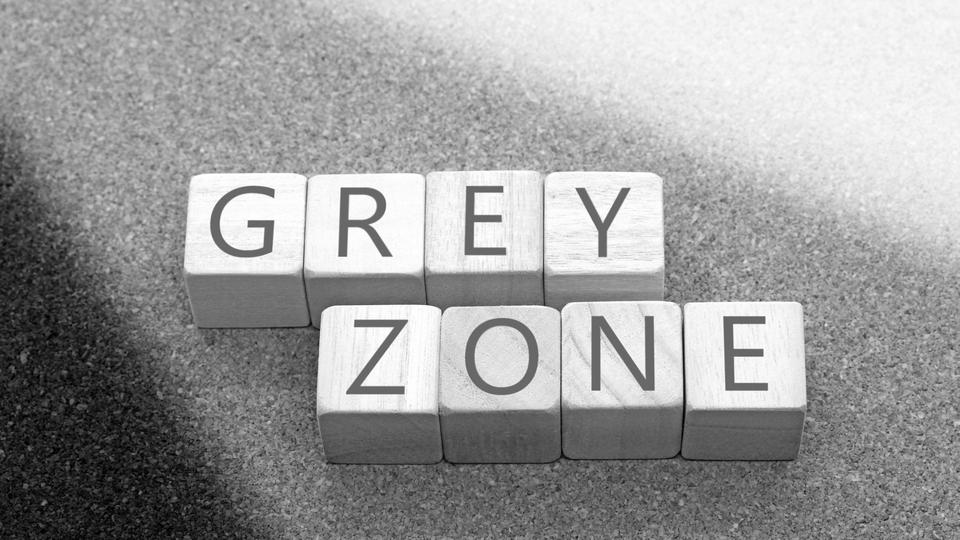この数年来、芸能・エンターテインメント界が長らく抱え込んできた、弱者への抑圧やハラスメント、性暴力などが大きく報道されるようになり、また被害を受けていた立場の人々が正当に告発できる環境も少しずつ生まれるようになった。こうした機運をさらに継続的な流れにつなげ、またこれまで放置・温存されてきた問題に根本から向き合っていくためには、各種エンターテインメントの送り手、受け手の双方が、どのような言葉を紡いでいくかも重要になる。
芸能の実践者からの真摯な問い
そうしたなか、芸能の実践者側の語りとして今春、注目されたものの一つに、2月15日に「文春オンライン」に掲載されたお笑いコンビ「ヤーレンズ」¹ のインタビュー² があった。芸人への密度の濃いインタビューを数多く手がけてきたライター・西澤千央の手による同インタビュー記事では、お笑い界のホモソーシャル性の指摘、自身を含め無自覚な女性蔑視的な要素があるのではといった自省、またそれらの問題についてお笑い界から能動的な発信が乏しいことなどが言及され、大きな反響を呼んだ。ダウンタウンあるいは松本人志の功績や、時代をつくった同業者の先達としての憧憬にふれながらも、そうした憧れだけを語ることに疑義を呈し、今日を生きる芸人として問うべき論点を指し示す、フラットなバランスの語りだった。
同記事に対しては、現在形の問題について真摯な言葉を紡ぐヤーレンズの二人への好意的な反響が多くみられた一方、松本人志の性加害報道をリードしてきた「週刊文春」の関連メディアである「文春オンライン」内で配信された記事であったことから、松本をめぐる報道に関して、彼らを「文春派」と目して批判、敵視するような反応もまた少なくなかった。あらためていうまでもなく、当該の事象において重要なのは、あらわになったエンターテインメント界の根深い問題、あるいは社会全体が明確に是正しようとしてこなかった抑圧を省みて問い直すことであり、議論を党派性に収斂させたり、なんらかの二項対立の物語に落とし込んだりして単純化すべき性質のものではない。
このインタビュー記事への反響については、2月17日放送分の『ツギハギ月曜日~ヤーレンズのダダダ団!~』(ABCラジオ)³ で、ヤーレンズの二人の口から補完的な言及がなされている。そのなかで着目すべきは、前述した「文春派」のように彼らを党派性でまとめようとする反響に対して、二人が総体としての"文春"という記号に対する個人的な好悪感情と、同インタビュー企画へのスタンスとを区別して語っていた点である。二人は放送中、同記事で聞き手/書き手を務めた西澤への信頼を口にしたうえで、西澤との協業によるインタビュー記事であることにポジティブな価値を置き、他方で"文春"そのものに対しては必ずしも好意的な振る舞いを示しているわけではなかった。
集合的な成果物としての「インタビュー記事」
こうしたスタンスの表明はまた、インタビュー記事というコンテンツ一般について、一歩俯瞰したところから、よりこまやかな視座をもたらしてくれるものでもある。もとより、インタビュー記事とは、語り手、インタビュアー/書き手、編集者など、さまざまな志向や立場、所属の人間が関わり、総合的な調整を経て、マスメディアのコンテンツの一つとして世に出される集合的な成果物である。記事の成立に関わるおのおのの間で、必ずしもすべての見解の一致がみられるわけでもなく、また記事が掲載される媒体とのごく一時的な関わりをもって、個別の記事に登場する語り手の思想信条や「党派」なるものが決まるわけでもない。時には立場が明確に異なる者同士の対話によってこそ、建設的な議論が進展することは少なくない。そうした場を効果的に設けることもまた、メディアの重要な役割である。
このような視点は、目の前の事象を解釈するうえで、わかりやすい物語や結論を提供してくれるものではないかもしれない。ヤーレンズの語りは、憧憬の的であった先達への思いと、その人物をめぐって生じた業界内の深刻な問題との双方を、自ら受け止めて考えようとするもので、何らかの明快な結論を即座に導こうとする性質の語りではない。そうした慎重な態度はまた、実践者である彼らにとってのみならず、エンターテインメントを受容する消費者にとっても肝要である。何らかの対立図式的なストーリーを設定して、敵あるいは味方の立場を彼らに背負わせることは、彼ら自身の言葉から最も遠い態度である。
問われるマスメディアの発信手法
もっとも、SNSなどを基軸とする現在のメディア環境が、わかりやすい構図やストーリーを希求しやすく、そうした明快な物語によって人々の感情を動員する傾向にあることもまた間違いない。例えば、そのような情報環境におけるマスメディアの発信手法について、きわめて自覚的な整理を行っているのが、前述したヤーレンズの記事公開やラジオ放送と同時期、今年2月に刊行された、斉藤友彦『新聞記者がネット記事をバズらせるために考えたこと』(集英社新書)である。
共同通信社の記者としてキャリアを重ねてきた斉藤が同書で綴るのは、新聞記事において長年培われてきた執筆メソッドとは大きく異なる、デジタルメディアで記事を読み手に届けるための文章スタイルの模索だ。著者の斉藤は、情報を伝えることに最適化したスタイルだと従来思われてきた、新聞の執筆作法への「信仰」を一旦疑い、時代に応じた効果的な伝え方を根本から学び、それらのポイントを整理しようとする。ある面では、著者自身の試行錯誤を描くルポルタージュのようでもあり、またデジタルメディアで文章を書こうとする人々に向けた実践的なテキストでもある。
そして、この書籍で斉藤がデジタル記事執筆のポイントとして繰り返し示すのは、まさに「ストーリー」として記事を届けること、そして読者の「共感」を呼び込むことの重要性だ。もっとも、「バズらせるために」という煽り気味の書名とは対照的に、本書は地に足のついた誠実さで、現代の受け手にいかにストレスをかけずに読んでもらえるかを意識した整理を行っている。
だからこそまた、デジタルメディアで情報にふれることがスタンダードとなった今日の読者の傾向も、端々に浮き彫りになる。同書では、政治問題などを扱った記事へのモニターの感想として、「この記者が賛成派なのか反対派なのか、どちらかが分からなくてもどかしかった」という意見が寄せられたエピソードが登場する。斉藤は葛藤しつつも、これまで多くの新聞記事が習慣としてきた「公正中立」や「両論併記」のスタイルを自ら省みるが、こうしたモニターの反応は、書き手や語り手にすぐさま鮮明な旗色を見いだそうとする、受け手のあり方が象徴的にあらわれている。
あいまいなまま受け取り、吟味する
斉藤がそうした明快さや、感情の動員が先行するデジタルメディアの性格に警鐘を鳴らしながらもなお、マスメディアの記者として、「ストーリー」や「共感」を前提とする今日の受容のモードに順応しようとするのは、マスメディアが発信すべき情報が、記事の書き方のせいで人々に届かなくなってしまう事態を恐れるためだ。他方、マスメディアの受容に関して、感情の動員を放置してしまえば、先の「文春オンライン」への反応にみたように、多義的な記事内容を落ち着いて受け止めるのではなく、語り手に対して即座に特定の「党派」性を見いだし、勇み足で敵/味方の構図に落とし込むような拙速さをも呼び込んでしまう。この押し引きにおそらく終着点はなく、マスメディアの担い手はどこまでも模索を続けるほかないのだろう。
長らくメディア文化学などを専門にしてきた佐藤卓己(上智大学教授)は近年、あいまいな情報をあいまいなまま留め置き、その不確実性に耐える「ネガティブ・リテラシー」を提唱している。その背景にあるのはやはり、SNS等を中心とした今日のメディア環境が、「情動」を駆り立てる社会を生んでいるという現状認識だ(『あいまいさに耐える――ネガティブ・リテラシーのすすめ 』、2024年、岩波新書)⁴ 。ソーシャルメディアによって、多くの人々が情報の受信者と発信者・拡散者を兼ねる今日では、既存マスメディアのみならず、SNSにふれる一人ひとりが、社会の議論傾向を左右するアクターとして機能している。だからこそ、日々大量に現れる情報をすぐさま、情動を動員しやすい鋳型に流し込む前に、一旦、あいまいなまま受け取って吟味することが重要になる。それは、社会全体が目の前の問題を安直な「ストーリー」や「共感」へと単純化してしまわないための、集合的な知恵になるはずである。
¹ ヤーレンズ 2011年に楢原真樹と出井隼之介で結成されたお笑いコンビ。M-1グランプリ2023準優勝、M-1グランプリ2024ファイナリスト。民放ラジオで、TBSラジオ『パンサー向井の#ふらっと』(隔週木のレギュラー、8:30~11:00)、ニッポン放送『ヤーレンズのオールナイトニッポン0(ZERO)』(月1回最終土、27:00~29:00)、ABCラジオ『ツギハギ月曜日~ヤーレンズのダダダ団!~』(月、21:15~23:30)の3本のレギュラーを持つ。
² 「文春オンライン」のヤーレンズ インタビューはこちらでお読みいただけます(外部サイトに遷移します)。
³ ABCラジオ『ツギハギ月曜日~ヤーレンズのダダダ団!~』の2月17日放送分はこちらでお聴きいただけます(同上)。
⁴ 佐藤卓己著『あいまいさに耐える――ネガティブ・リテラシーのすすめ 』については飯田豊氏による書評もお読みください。