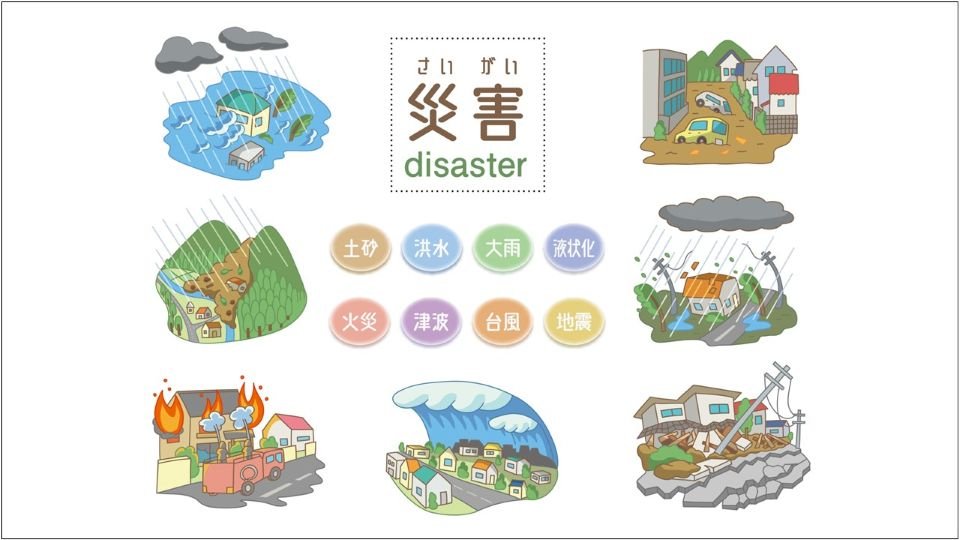総務省の「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会(以下、在り方検)」では、2025年2月から「広域大規模災害を想定した放送サービスの維持・確保方策の充実・強化検討チーム(以下、検討チーム)」を開催し、これまで5回にわたり議論してきた。6月6日には、①地上放送を維持するための方策、②ローカル局の放送が停波した場合の代替手段の確保、③被災者の視聴環境の確保、の3項目からなる論点整理案(外部サイトに遷移します。以下同じ。)を公表した。
筆者は1995年の阪神・淡路大震災以降、約30年にわたり、NHKで番組制作や放送文化研究所の研究活動で多くの被災地を訪ね、災害情報伝達や地域メディアの役割を考えてきた。本稿では、筆者の視点で、検討チームの議論の意義と課題を、能登半島地震の教訓を交えながら論じ、広域大規模災害に備えて放送局が取り組むべきことを考えてみたい(2025年7月1日記)。
1.検討チームの問題意識
検討チームの議論で繰り返し強調されていたのが、経済合理性を勘案したバランスのとれた災害対策、という趣旨の発言である。
災害が多発し、広域大規模災害の危険性が叫ばれる中、住民の命を守り、被災地の復旧・復興に伴走する放送メディアの役割はますます高まっている。そしてユーザーの情報入手手段や経路は多様化しており、放送局は人々の命を守る情報を届けるために、さまざまなネット活用に取り組むことも求められている。
一方で、放送局の経営環境は年々厳しくなっており、個社の取り組みには限界がある。そのため、メディア同士や自治体などと効果的な"連携"を図ることで"重層的"な災害対応の方策を考えようというのが、検討チームのベースにある問題意識といえよう。
2.検討チームの議論の意義
まず、検討チームの議論で、意義があると筆者が感じた点を述べる。
最大の意義は、南海トラフ地震(以下、南トラ)時の地上放送のリスクと真正面に向き合うことを、議論の出発点にしたことである。第1回会合で、事務局から、南トラ想定被害地域に存在する地上放送局の親局・中継局の数、ケーブルテレビのヘッドエンドの数が記された地図が示された(配布資料参照、図表1)。これを見て、南トラにおける放送局の厳しい現実を思い知ったという人は多かったのではないか。

<図表1 南海トラフ被害想定地域における地上放送局数>
能登半島地震では、中継局の電源維持のため、自衛隊のヘリコプターで燃料を運搬した。しかし、南トラの場合、この方策は実施したとしても限定的にならざるを得ない。また、能登半島地震でケーブルテレビは幹線や加入者線に被害を受け、輪島市では他局の応援を受けて仮復旧に約3カ月を要した。南トラでは、他局の応援が期待できない可能性もある。
こうした厳しい現実を踏まえ、検討チームが、地上放送が停波した際の代替(補完)手段にあげたのが、インターネット(以下、ネット)配信、衛星放送、臨時災害放送局(以下、臨災局)(臨時災害放送局の詳細はこちら)の3つであった。
図表2では、筆者なりに3つの手段の特性をまとめてみた。今回、この中で最も具体的な方策が示されたのが衛星放送の活用である。

<図表2 代替(補完)手段とその特性>
論点整理案では、東経110度CSで放送中のキー局系ニュース専門チャンネル「日テレNEWS24」「TBS NEWS」を、災害発生時にスクランブルを解除して提供することが示された。能登半島地震では、石川県の系列局の情報番組や特番を放送した実績もあったという。
広域大規模災害では、どの地域の親局・中継局が被災し、停波による代替が必要になるかわからない。そのため、大仰な準備をせず迅速に対応できる方策が選択されたことには意義があると感じた。大仰な準備が不要といえば、在り方検の衛星放送ワーキンググループでは、サブチャンネルの活用という意見も出ていた。たとえばNHK BS放送は、災害時に総合テレビ(被災局など)の同時放送を行う方策も検討に値するのではないだろうか。
課題は、テレビのほかに衛星放送を受信するアンテナが必要なことである。避難所の視聴環境の整備に関する放送局と自治体の責任分界点はあいまいなまま今日に至っているが、今回の衛星利用方策の導入を契機に、自治体、地上放送局、ケーブルテレビが率直に対話する場が各地で設けられることを期待したい。
3.検討チームの議論の課題①ネット配信
ここからは、筆者が検討チームの議論で踏み込みが足らないと感じた点を論じる。まず、衛星放送と共に代替(補完)手段としてあげられたネット配信についてである。
ただでさえ人員の少ないローカル局にとって、広域大規模災害時にどこまでネットを活用して情報伝達に取り組むべきか、は悩ましい。地上放送が視聴できない事態が発生した能登半島地震では、石川県の民放4局全てが、「権利許諾に関する問題が多数あったが、緊急時の対応として被災者に有用だと判断し(民放連研究所「能登半島地震時のメディアの役割に関する総合調査」報告書 P31参照)」、自社の情報番組のリアルタイム配信を実施した。被災地では、衛星ブロードバンドサービスのスターリンクが大量に運び込まれ、比較的早く通信環境が回復していた状況もあった。
検討チームの議論では、ネット配信にも地上放送の代替(補完)の役割を期待する積極的な意見と、スマホの消費電力や通信ネットワークの負荷を懸念する消極的な意見の双方が出された。また、配信以外のネットサービスとして、ウェブサイト、アプリ、SNSの話も出た。しかし、被災者には何が有効で、被災地の局は何をすべきで、被災地外の局はどんな遠隔支援ができるのかなど、議論は整理されないまま論点整理案に至ってしまった。
筆者の見解はこうである。発災前後の避難行動中は、命を守るため、刻々と更新される情報を入手し続けることが特に重要である。ラジオが最も有効であることを伝え続けると共に、補完としてradikoのアプリのダウンロードを呼びかけておくことは重要だろう。地上テレビ放送のリアルタイム配信は、発災前後の避難行動中に更新情報を入手するためには有効であるが、動画を視聴しながらの避難行動には危険が伴う。また、構成員が指摘したように、スマホの消費電力や通信ネットワークへの負荷も大きな課題だ。
筆者がNHK在籍中に行った能登半島地震の被災者調査の結果も紹介しておきたい。発災から1カ月間、ネット上の情報入手で上位を占めたのは、自治体のウェブサイトや公式LINE、その次が検索サイトやSNSであり、放送局を含めたマスメディアが発信する情報へのアクセスは極端に低かった(NHK文研ブログ 図9参照)。この結果から、被災者は、身近な情報をテキストで確認したいというニーズが高いことがうかがえる。逆に、県域の情報を映像で伝えるリアルタイム配信のニーズは、被災地では高くないともいえる。石川県の局の人からは、せっかく配信を実施したが視聴数は伸びず、被災地で視聴された実感は乏しかったとの声も聞いた。
これらはあくまで筆者の取材に基づくものであり、論点整理案にもある通り、「視聴ニーズの把握等の調査も行いつつ、引き続き検討することが必要」である。ただ主張したいのは、被災地のローカル局は目の前で困っている被災者のために何ができるかを最優先に考えるべき、ということである。そもそも南トラでは、通信が不通の状態が長期に続くことも予想される。日頃のサービスとして提供していないリアルタイム配信を、新たに立ち上げてまで行う余裕もないだろう。
では、ネット配信による地上テレビ放送の代替・補完は行わないのか。筆者は、その役割は、TVerのキー局系24時間ニュースや、テレビ朝日系のABEMA NEWSが担うべきだと考えている。衛星放送による代替と同じ発想だ。
ただし、被災地外での編成・制作の作業は、現地との温度差が生じがちである。今回の代替の議論を機に、衛星であれ配信であれ、キー局系ニュースチャンネルには、これまで以上に被災地視点での運営を心がけてほしい。
以上は、広域大規模災害を想定した現時点での筆者の考えである。風水害時や、平時のコネクテッドテレビも意識した今後の施策として、ローカル局がリアルタイム配信を実施する方向性を否定するものでは決してない。
4.検討チームの議論の課題②臨災局
臨災局をめぐる議論の課題にも触れておく。
臨災局とは、災害発生時、被害軽減などを目的に臨時かつ一時的に自治体等が開設するFM局のことで、これまで55局が開設されてきた。
今回の論点整理案では、臨災局の開設を促す2つの方向性が示された。1つ目は、開設に必要な無線従事者資格の緩和である。これまで、無線従事者が見つからず開設が難航した事例もあったため、改善につながると評価したい。2つ目は、災害時に臨災局の開設を希望する自治体に、優先的に使用できる周波数をあらかじめ通知する方向性である。すでに一部の総合通信局では取り組まれてきたが、全国展開となることは望ましい。
ただ、これらの方向性だけで開設が進むとは思えない。能登半島地震では臨災局が開設されなかったが、検討チームの構成員である石川県の担当者は、理由として、開局後の運営費への財政的な支援制度がないことを強調した。総務省との間で臨災局の開設支援協力協定を締結しているコミュニティ放送局の業界団体(JCBA)も、活動に必要な費用の財政補填を要望した。しかし今回、これらの意見が論点整理案に反映されることはなかった。
(編集広報部注:その後、輪島市町野地区の臨災局が2025年7月7日に開局した。民放online記事はこちら。)
筆者は長らく、臨災局の調査・研究をしてきたが、この制度は、助成団体による資金や、ボランティアの住民や支援者による善意でなんとか維持されている脆弱なものだと痛感してきた。地上放送の代替という"お題目"がついた今回こそ、実効性のある方策が出されると期待していただけに、残念であった。
検討チームの議論が開始されるまで、多くの地上放送局は、臨災局への認知も関心も低かったと思われる。ただ、「地上放送局が停波した時の代替」を、「AMラジオ放送を停波した時の代替」と置き換えると、AMラジオ局には少し身近に感じてもらえるのではないか。
2028年に向け、AMラジオ局はFM転換を模索中である。AM局は廃局したいが、AM波が届いていた地域全てをカバーするためにFM中継局を設置するにはコストがかかりすぎる、との悩みをよく聞く。カバーしきれない地域は、自治体に説明のうえ、radikoで代替することも制度として検討されている。ただ、災害に強いメディアと謳い続けてきたラジオ局として、自問自答する事業者も少なくないだろう。
筆者の提案は、このFM化の施策の中に、臨災局の仕組みを組み込むというものである。自治体と協力してあらかじめ臨災局を準備し、平時はradiko、有事は臨災局、というモデルを構築できないか。臨災局の設備は、複数のFM中継局の設置より安価になる見込みも高い。FM化と臨災局化のパッケージで、「経済合理性を勘案したバランスのとれた災害対策」を、自治体との連携で進めてみてはどうだろうか。
5.さらなるメディア連携に向けて
検討チームにおけるメディア連携の議論はハード面が中心で、情報伝達や報道などソフト面の議論を期待した筆者にはいささか期待外れであった。しかし、考えてみれば、ソフト面の連携は放送局の主体的な取り組みで進めていくのが健全である。
2025年にもさまざまな連携の動きがみられる。5月には北海道で、NHKと民放5局が災害時のヘリコプターの運用の分担や映像を共有する連携を開始した。中京、福岡に続く3例目である(「北海道モデル」については、民放online記事参照)。また、阪神・淡路大震災から30年目を機に「関西 民放NHK連携プロジェクト(以下、関西プロジェクト)」が開始され、若手を中心に局の垣根を超えた議論が続けられている。
こうした連携の動きが高まる中、筆者は、さらに踏み込んだ連携に歩みを進めるべきだと強く感じている。1つ目は、災害報道の分野全般において、ヘリ取材のように、取材の分担や素材の共有を進めることである。メディアスクラムや報道空白地の問題を社会に晒し続けることは、放送局への不信をさらに深めることになるというのは、多くの放送人が自覚するところであろう。筆者はこれまで、多くの災害関連のシンポジウムを企画したが、その全てで、登壇者は変革しなければならないと明言した。にもかかわらず現状は変わらない。筆者も忸怩たる思いを持ち続けている。
2つ目は、避難行動後の応急・復旧期に情報が増大する中、行政情報やライフライン情報など、どの放送局が収集しても同様の内容のものについては、クラウド上に集めて各局が利用できるような連携施策をとることである。局ごとに担当を決めて収集する方法もあると思うが、筆者は、全国に基盤を置き、人員も圧倒的に多いNHKが情報を収集し、民放にも共有する枠組みを作るべきではないかと考える。この枠組みは、偽・誤情報の発見から打ち消し報道にも応用できるだろう。
NHKと民放の連携は、中継局の共同利用や、還元目的積立金のファンディング活用などさまざまな形で進んでいるが、広域大規模災害に対応するための連携方策にも力を入れるべきではないか。こうした方策の議論には、放送局の主体的な取り組みを超える内容もある。総務省のイニシアチブに期待したい。
前出の関西プロジェクトでは、「緊急報道における映像の共有、災害情報を伝える共通のポータルサイトなどに加え、こうした連携がなぜ必要なのか、その意味まで深めるグループもあった(阪神・淡路大震災30年「関西 民放NHK連携プロジェクト」活動報告〔放送文化基金〕 参照)」という。現場の若い人たちの連携が、放送局の経営や業界の体質を変革させる起爆剤になることを期待している。
おわりに
図表3は、筆者の視点で、災害と地域メディアの役割をまとめたものである。災害とメディアを考える際には、情報をどう届けるか、という議論に偏重しすぎて、メディアとして何をすべきか、という議論がおざなりになりがちだ。参考になれば幸いである。

<図表3 災害を巡る4つのフェーズと地域メディアの役割>
また筆者は、情報をどう届けるか、に加えて、孤立した被災地から情報をどう吸い上げるか、にも関心を抱いている。ネット活用を単なる情報の伝送路としてではなく、双方向のネットワークと捉えれば、災害対応としてできることは各段に増えてくる。また、こうした発想は平時における地域課題解決にも応用できるため、ローカル局の新たな事業機会の創設や企業価値の再構築にもつながるだろう。また別な機会にあらためて論じたい。